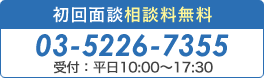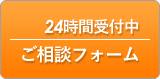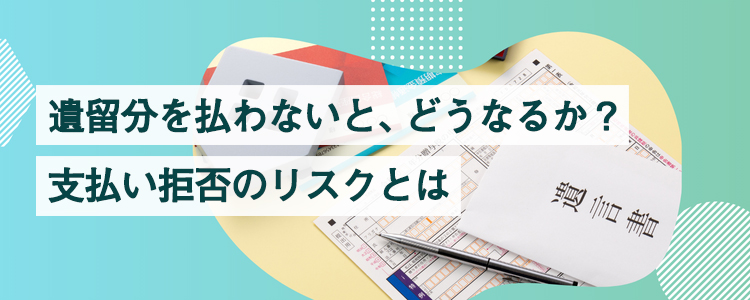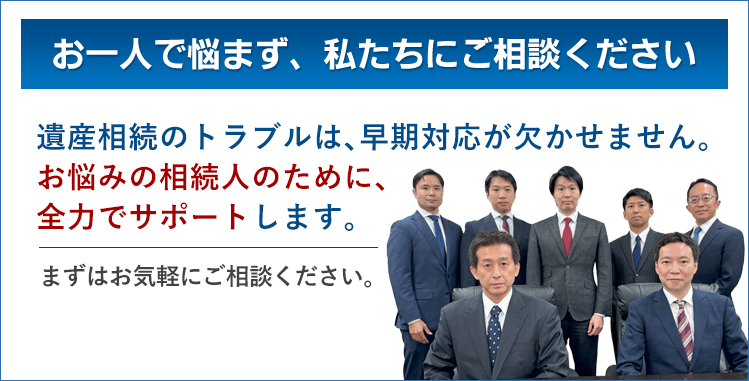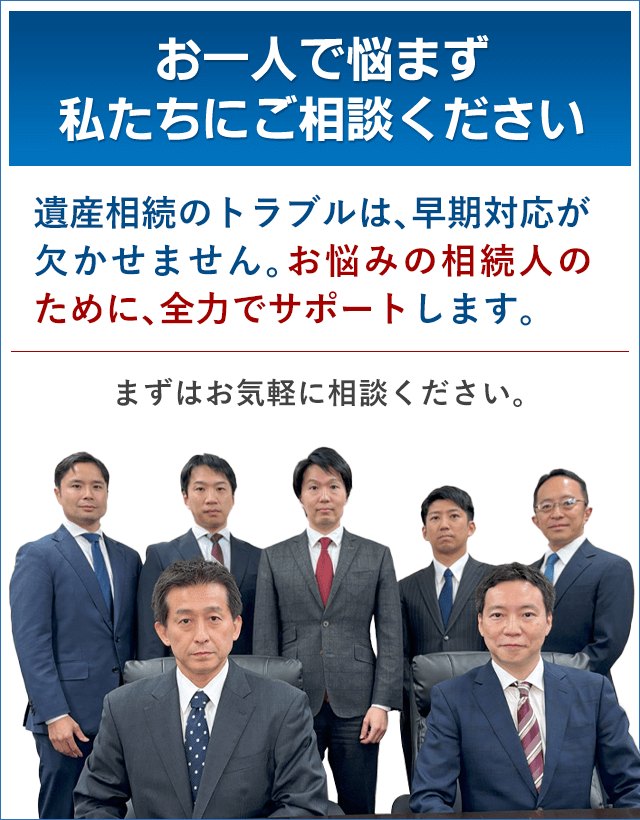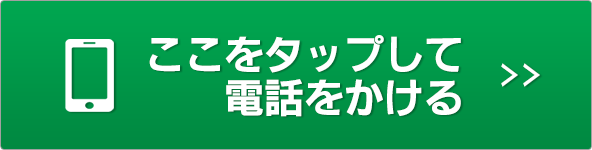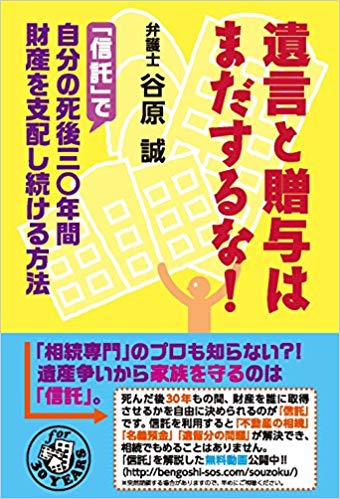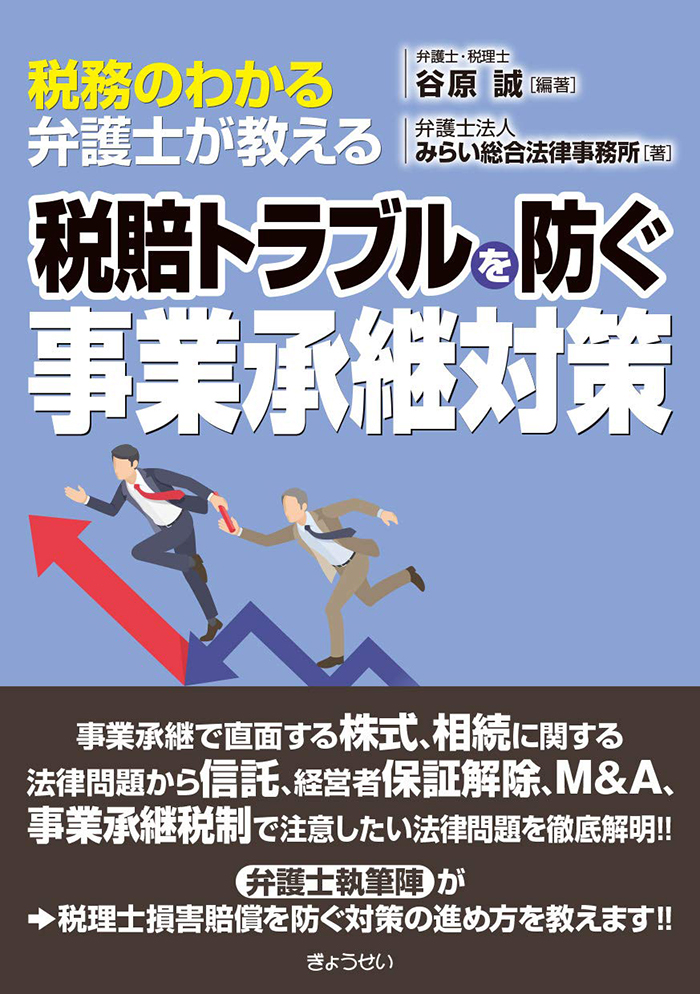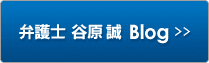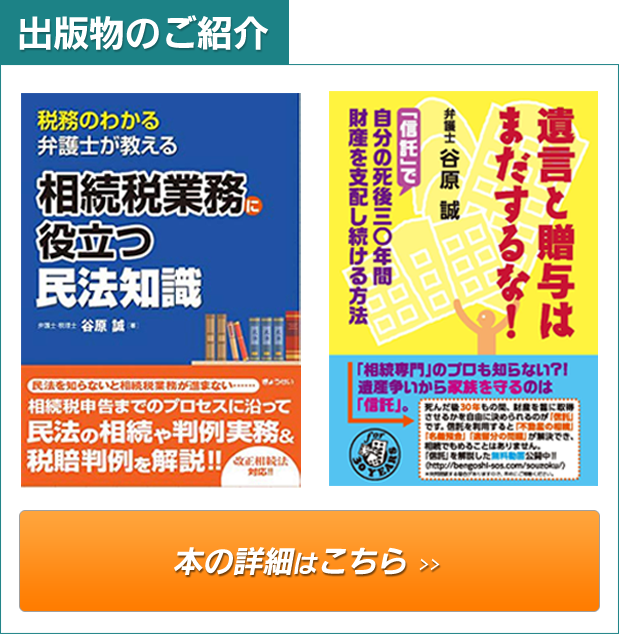遺留分を払わないと、どうなるか?|支払い拒否のリスクとは
たとえば、被相続人(亡くなった方)の遺言書に他の兄弟の名前と相続財産は記載されているのに、相続人の1人であるはずの自分の名前がない場合、どうすればいいのでしょうか?
逆に、遺言書に自分の名前はあるが、他の相続人であるはずの人の名前がない場合、どうなるのでしょうか?
また、ある日突然、聞いたこともない人物から遺産相続に関する内容証明郵便が届いたら?
そこで問題となるのが「遺留分」です。
本記事では、一定の法定相続人が、最低限の相続財産として請求できる遺留分について、
- ・他の相続人から請求された場合の対応
- ・遺留分を支払わなくていいケース
- ・遺留分を支払わなかった場合に起きる
問題 - ・遺留分を支払えない場合の対応
などのポイントを中心に解説していきます。
他の相続人から遺留分を請求されたが払いたくない、といった問題を抱えた方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
目次
まずは相続の遺留分について
簡単に解説します!
遺留分の支払いについて解説する前に、まずは遺留分の基礎知識について簡単にお話しします。
※遺留分についての知識をお持ちの方は、次章の「遺留分を請求されたときの対応」からお読みください。
なぜ相続分を受け取れない?
~遺言書の効力とは~
遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先される、ことになっています。
そのため、遺言の内容によっては法定相続人なのに遺産の相続分を受け取ることができない場合があるのです。
たとえば、次のようなケースがあります。
被相続人(亡くなった人)が「愛人にすべての遺産を相続させる」と遺言書に書いたため、息子である自分は法定相続分を受け取ることができなくなった。
遺言書に「遺産はすべて長男に…」とあったため、長女である自分と妹は法定相続分を受け取ることができなくなった。
ここで「遺留分」が重要なポイントになってきます。
参考資料:No.4132 相続人の範囲と法定相続分
(国税庁)
そもそも遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人(配偶者や子、父母など)が最低限の相続財産を請求して、受け取ることができる「一定割合の留保分」のことです。
そして、相続人が、遺留分を請求できる権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
※条文は、民法第1042条~1049条に規定されています。
※遺留分侵害額請求権は改正民法による名称で、2019年7月1日より以前の旧民法では「遺留分減殺請求権」とされていたものです。
・遺留分とは、どのようなものか?
遺留分とは、遺産相続の権利がある人が「最低限、これだけの割合は受け取ることができる分」と言い換えてもいいでしょう。
遺留分は誰が受け取れるのか?
遺留分の権利を持つ人は次のとおりです。
- ①配偶者
- ②子
- ③直系尊属(父・母など)
すべての相続人に遺留分の権利があるわけではないことに注意が必要です。
※被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
※法定相続人である子が死亡している時は、その子(孫)が代襲相続人として遺留分を請求することができます。
※相続が発生した時点では胎児であっても、生きて生まれたときは遺留分が認められます。
・兄弟姉妹に遺留分がない理由と遺産を
受け取る方法
遺留分請求の対象となる財産
とは?
遺留分を請求できる財産には次の種類があります。
遺贈する財産
故人の遺言で指定された人に、被相続人(亡くなった人)の遺産の一部、または全部を譲る(承継する)ことを「遺贈」といいます。
相続との違いとしては、遺言書によって、相続人や特定の個人以外にも遺産を受け継がせることができるという点があげられます。
そのため、法定相続人の遺留分侵害額請求の対象になります。
死因贈与する財産
自身の財産を誰かに無償でわたす、譲ることを「贈与」といいます。
「死因贈与」とは、贈与する人(贈与者)と受け取る人(受贈者)の間の契約という形での合意に基づくもので、贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます(民法第554条)。
生前贈与した財産
生きているうちに、配偶者や子ども、第三者などに財産を移譲することを「生前贈与」といいます。
生前贈与は贈与の一種のため、遺留分侵害額請求とは関係ないように思う人もいるかもしれませんが、法定相続人(配偶者・子ども・直系尊属など)の遺留分が侵害されている場合、贈与された人(受贈者)に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
※法定相続人への生前贈与が特別受益になる場合は、原則、相続開始前10年以内の贈与が対象になります。
※それ以外の場合は相続開始の1年前以内に生前贈与した財産が遺留分侵害額請求の対象に含まれます。
※ただし、それぞれ贈与者(被相続人)と受贈者の双方が、遺留分侵害になることを知って贈与を行なった場合は、1年以上前に行なわれた贈与も対象になります。
複数の相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合、その相続人の受けた贈与などの利益のことを特別受益といいます。
特別受益があった場合には、その財産を相続財産に持ち戻して遺産分割をすることになっています。
ただし、相続開始の時から10年を経過した場合には、原則として持ち戻しはありません。
・簡単に遺留分を請求する方法
【5ステップ】
遺留分の割合を一覧表で確認
受け取ることができる遺留分の割合は、相続人とその組み合わせによって変わってきます。
わかりやすい一覧表を作成したので、まずは確認してみてください。
<遺留分の割合の早見表>
| 相続人 | 遺留分合計 | 配偶者の 遺留分 | 子供の 遺留分 | 親の遺留分 | 兄弟の 遺留分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | - | - |
| 配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | - | 1/6 | - |
| 配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 子供のみ | 1/2 | - | 1/2 | - | - |
| 親のみ | 1/3 | - | - | 1/3 | - |
| 兄弟のみ | - | - | - | - | - |
| 遺留分 合計 | 配偶者の 遺留分 | 子供の 遺留分 | 親の 遺留分 | 兄弟の 遺留分 |
|---|---|---|---|---|
| 相続人:配偶者のみ | ||||
| 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 相続人:配偶者と子供 | ||||
| 1/2 | 1/4 | 1/4 | - | - |
| 相続人:配偶者と親 | ||||
| 1/2 | 1/3 | - | 1/6 | - |
| 相続人:配偶者と兄弟 | ||||
| 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 相続人:子供のみ | ||||
| 1/2 | - | 1/2 | - | - |
| 相続人:親のみ | ||||
| 1/3 | - | - | 1/3 | - |
| 相続人:兄弟のみ | ||||
| - | - | - | - | - |
なお、遺留分の金額は、相続財産の総額に遺留分の割合をかけて算出します。
・遺産の分配割合・分配方法を判断する
ための知識
時効期間を過ぎると遺留分は
請求できなくなる
法律上、一定の期間を経過してしまうと、権利自体が消滅してしまう制度があります。
これを「消滅時効」「除斥期間」といい、遺留分の場合は次のようになっています。
- ①「相続開始と遺留分侵害の事実」を
知った日から1年以内(消滅時効) - ②相続開始や遺留分侵害の事実を知らずに時が過ぎた場合は、相続開始から10年以内(除斥期間)
※除斥期間とは、法律関係を速やかに確定させるために、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度で、遺留分請求では10年間を過ぎると権利自体が消滅してしまうので注意が必要です。
・遺留分減殺請求権(遺留分侵害額
請求権)の時効
知って納得!遺留分を請求されたときの対応
では次に、視点を「遺留分を請求された相続人側」に立って、どう対応していけばいいのかについて解説していきます。
遺留分を支払わないと
どうなるのか?
遺留分は法律(民法)で保証されている権利です。
そのため、たとえ遺言があったとしても、遺留分を奪うことはできません。
法律上の要件を満たしている場合、遺留分を相手側から請求されたのに支払わないと次のことが起きる可能性があります。
調停や訴訟を起こされる
遺留分の支払いを無視したり、拒否していると、相手側は「遺留分侵害額請求調停」の申し立てを行なう可能性があります。
また、調停の申し立てを無視していると、訴訟を提起される可能性があります。
※調停=裁判所を介して、双方の合意を図る手続き。
※訴訟=当事者の合意によらず、裁判所の判決によって紛争の解決を図る手続き。
財産を差し押さえられる
調停や判決で決定された遺留分の支払いを拒否した場合、相手側は裁判所に強制執行の申し立てをして財産を差し押さえることができます。
たとえば、預貯金の差し押さえであれば、裁判所からの債権差押命令が発令され、申し立て時に特定した金融機関(支店)にあるあなたの口座の預貯金が差し押さえられてしまうわけです。
つまり、遺留分を請求された場合は基本的に支払う必要があるということになります。
遺留分は拒否できないのか?
遺留分は、権利を有する相続人が、遺留分侵害額の請求をしなければ受け取ることができません。
つまり法的には、請求がなければ支払わなくてもいいということになります。
しかし、相手側からの遺留分の請求が正当なものであれば、支払いは拒否できません。
具体的には、次の3つの条件を確認しましょう。
遺留分を請求する権利がある
相続人かどうか
相手が、被相続人(亡くなった方)の「配偶者」、「子(代襲相続人を含む)」、「父・母など直系尊属」であれば、遺留分を請求する権利があります。
しかし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の請求権はありません。
また、「相続欠格」「相続廃除」になった人、「相続放棄」をした人も遺留分は認められません。
「相続欠格」
被相続人を死亡させたり、遺言に関する脅迫や詐欺をしたり、遺言書の偽造・変造・破棄・隠ぺいをした場合など、遺産を不正に手に入れるために法を犯した人が相続人の権利を失うことを「相続欠格」といいます。
「相続廃除」
被相続人を虐待したり、屈辱を与えたという人に対して、被相続人は自分の意思で相続人の権利を失わせることができ、これを「相続廃除」といいます。
「相続放棄」
被相続人の財産を取得することを相続人が望まない場合、自ら相続する権利を放棄することを「相続放棄」といいます。
相続放棄をした場合は、初めから相続人ではないことになるので、遺留分も認められません。
・相続の承認・限定承認・放棄とは?
遺留分侵害額請求権の時効期間が過ぎていないか
前述のように、遺留分の請求権の時効は1年間、除斥期間は10年間です。
ただし時効というのは、ただ期間が経過することで消滅するわけではないことに注意が必要です。
遺留分侵害額を請求される側が、時効を主張することで、はじめて消滅する、ことを覚えておいてください。
ですから、時効期間を過ぎているなら、消滅時効の成立を主張しなければいけません。
遺留分請求額は正しいか
相手側の請求金額が正当なものかどうかも確認する必要があります。
遺留分は、おおまかには次の計算式で算定します。
遺留分の基礎となる財産の総額
× 遺留分の割合 = 遺留分
※遺留分の基礎となる財産の総額は次のようになります。
+ 贈与分(これまでに贈与された分)
- 債務(マイナス分)
<遺留分の計算例>
遺産の合計額が1億2,000万円の場合…
・相続人が配偶者のみの場合
1億2,000万円の2分の1=6,000万円
・相続人が配偶者と子供2人の場合
配偶者:1億2,000万円の4分の1=3,000万円
子供1人あたり:1億2,000万円の4分の1を2人で分けるので=1,500万円
遺留分を支払わなくてもいい
4つのケースとは?
相続権・遺留分請求権がない
人からの請求
当然ながら、たとえ親族であっても相続権や遺留分請求権のない人から請求されても支払う必要はありません。
- ・被相続人の兄弟姉妹
- ・相続人の配偶者
- ・相続欠格になった人
- ・相続廃除になった人
- ・相続放棄をした人 など
※相続人廃除されている場合は、その人の戸籍全部事項証明書の身分事項の欄に「推定相続人廃除」と記載されているので、この部分を確認します。
※相続廃除されている場合でも、その相続人に子供がいる場合、代襲相続によって、その子供に相続権が移ります。
※なお、相続欠格になっていたとしても、戸籍に記載されたり、役所や裁判所から証明書が発行されたりすることはないため、確認する方法はありません。
※遺留分を請求してきた人が相続欠格に該当し、遺留分の請求権がないことを証明するためには、証拠書類の準備が必要になりますが、難しい作業になるため、相続に詳しい弁護士に依頼するのがいいでしょう。
遺留分を事前放棄している
人からの請求
被相続人の生前に遺留分放棄をしていた相続人が遺留分を請求してきた場合、遺留分の請求権がないため、遺留分を支払う必要はありません。
なお、遺留分放棄をしているかどうかを確認する方法は、申立てをした本人に審判書謄本が届くので、それを見せてもらうことになります。
遺留分請求権の時効が
過ぎている場合
時効や除斥期間が経過した後の請求に対しては、支払う必要はありません。
遺留分請求額が不当な場合
遺留分の請求額が不当な場合や法外な金額の場合は、遺留分を支払う必要はありません。
しかし、だからといって無視をしたり拒否するのではなく、まずは相手側との話し合いをするべきです。
遺留分を請求された場合の
手続きの流れについて
ここでは、相手側から遺留分を請求された場合の流れについて解説していきます。
内容証明郵便が送られてくる
口頭や文章(手紙やメールなど)で相手側から遺留分の請求が行なわれる場合もありますが、通常、法的に正式な対応をとる場合は内容証明郵便が届くでしょう。
内容証明郵便は、郵便局が当該書面の内容や発送日等を客観的に証明してくれるものです。
まずは内容を確認して、相手側の主張する内容を確認します。
遺留分権利者かどうかの確認
相手側が、遺留分権利者かどうかの確認を行ないます。
遺留分の計算をする
相手側の請求額が正しいものかどうか、遺留分の計算をして確認します。
なお、遺留分は2018(平成30)年の法改正により、原則として金銭での支払になっています。
相続財産に不動産や株式など評価が必要なものが含まれている場合などでは、計算が複雑になるので、正確で適切な金額を算定するには弁護士などの専門家に相談・依頼されることをおすすめします。
示談交渉の開始
相手側が遺留分請求権利者であることが確認できた場合は、当事者同士で示談交渉を開始します。
当事者同士で話し合っても感情的な対立などで交渉がまとまらない場合もあるでしょう。
その場合は、弁護士に依頼して代理人として示談交渉を行なってもらうこともできます。
調停の申し立て
示談交渉が決裂した場合は、相手側から調停の申し立てがなされるでしょう。
民事調停とは、簡易裁判所が指定する調停委員(民間人)などの中立的な第三者に間に入ってもらい、双方で話し合うものです。
調停が成立すれば「調停調書」が作成されます。
これは確定判決と同様の効力が生じるため、約束が果たされなかった時(遺留分の支払いがなされなかった時)には、強制執行も可能になります。
強制執行の前には、相手側が仮差押命令を申し立てる可能性もあるでしょう。
これは、支払われる遺留分を確保するために、相手側が一時的に財産を差し押さえるもので、請求された側には和解成立の圧力がかけられることになります。
訴訟の提起/強制執行
話し合いがまとまらない、あるいは請求された側が調停に参加しない場合、相手側は訴訟を提起してくるでしょう。
裁判で相手側の請求が認められれば、遺留分を支払わなければなりません。
遺留分を支払わない場合は、財産が差し押さえられ、強制執行により強制的に支払わされることになります。
預貯金の場合、金融機関が遺留分(請求額の限度内)を権利者に支払います。
不動産の場合は競売手続きを経て、処分されてしまいます。
また、給与の場合は、手取り額の4分の1が差し押さえの対象になります。
遺留分を請求された際に大切な
3つのポイント
遺留分を請求してきたのが権利を有する人で、時効期間が過ぎていない場合、次の3点を必ず確認してください。
適正な財産評価を行なう
前述したように、相続財産は現金に限りません。
不動産、株式、貴金属なども当然、財産になるため、これらを正しく評価することがとても重要になってきますし、裁判で争われるケースも多くあります。
遺留分を支払う側からすれば、できるだけ金額が低いほうがうれしい、という場合が多いでしょうから、財産評価を適正に、上手に行なうことが大切です。
遺留分権利者の特別受益を探す
特別受益には、次のものなどが該当します。
- ①遺贈された財産
- ②婚姻や養子縁組のために贈与された財産
- ③生計の資本として贈与された財産(生活費や家をもらったなど)
被相続人の生前に、遺留分を請求してきた人に特別受益があった場合、遺留分から差し引くことができるので、必ず確認しておくことが大切です。
遺留分を支払えない場合の
対応について
請求された遺留分を支払うだけの現金をすぐに用意できない場合もあるでしょう。
その場合は、「支払期限の許与(きょよ)」の申し立てを裁判所に行なうことができます。
これは簡単にいえば、支払期限を先延ばししてもらうことになります。
遺留分を請求された場合は
弁護士に相談してください!
ここまで相続における遺留分について解説してきましたが、難しいと感じた方も多いのではないかと思います。
そこで遺留分を請求された場合は、できるだけ早めに弁護士に相談・依頼することを検討していただきたいと思います。
相続や遺留分に詳しい弁護士に相談・依頼するメリットには次のことがあります。
- ・遺留分を支払わなければいけないかどうか判断してもらえる。
- ・法的な防御策や対処法を教えてもらえる。
- ・依頼者の代理人として相手側との交渉や裁判を行なってもらえる。
- ・依頼者に有利な形で解決してもらえる。
・遺留分を弁護士に相談する7つの
メリットと2つの注意点
弁護士法人みらい総合法律事務所では随時、無料相談を行なっています(※事案によるので、お問い合わせください)。
経済的な負担を少しでも軽減するためにも、まずは無料相談をご利用ください。
そこで「信頼できる」、「任せてみよう」と判断されたら、正式に依頼をするという流れで問題ありません。
遺産相続の遺留分は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡いただければと思います。