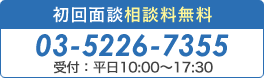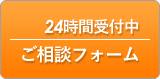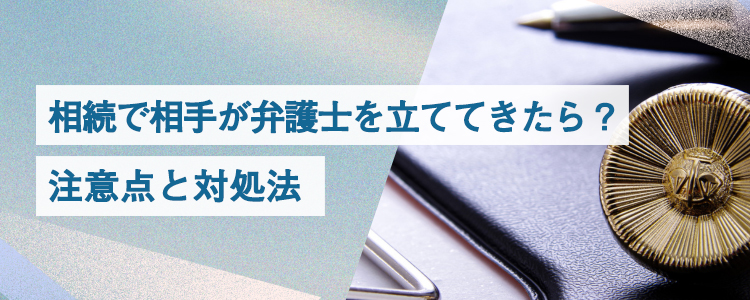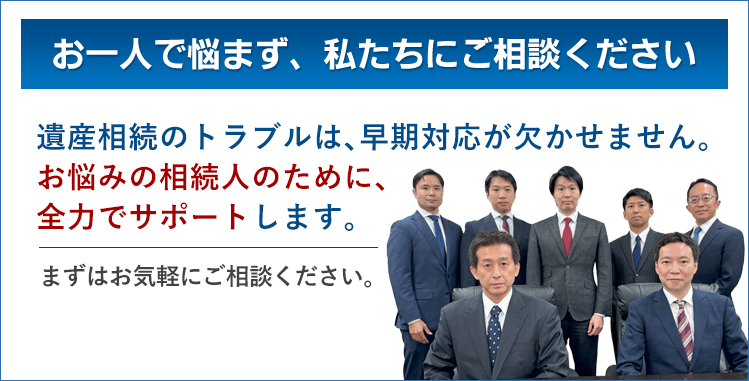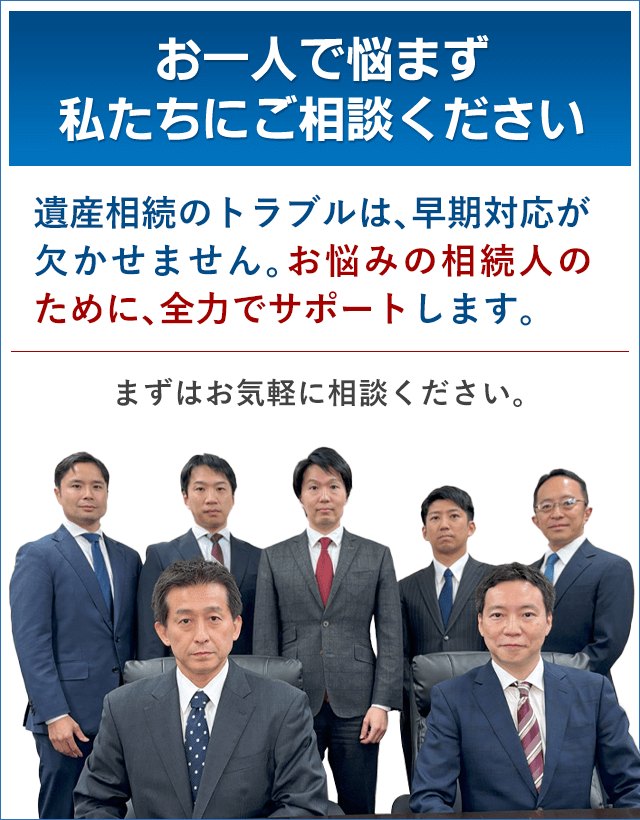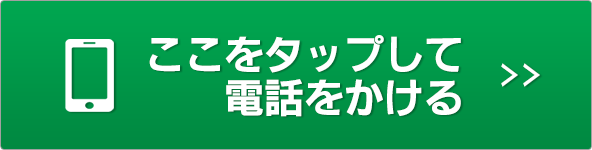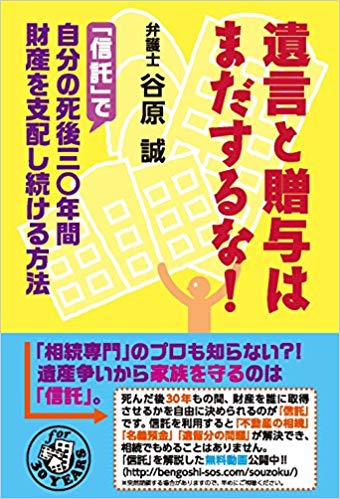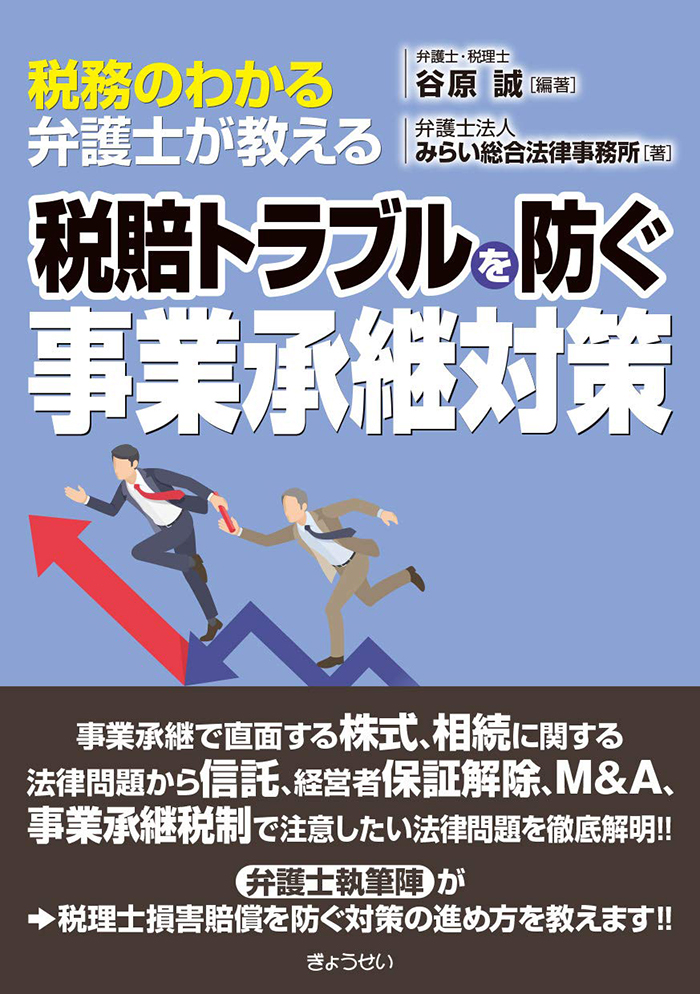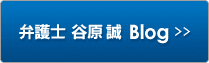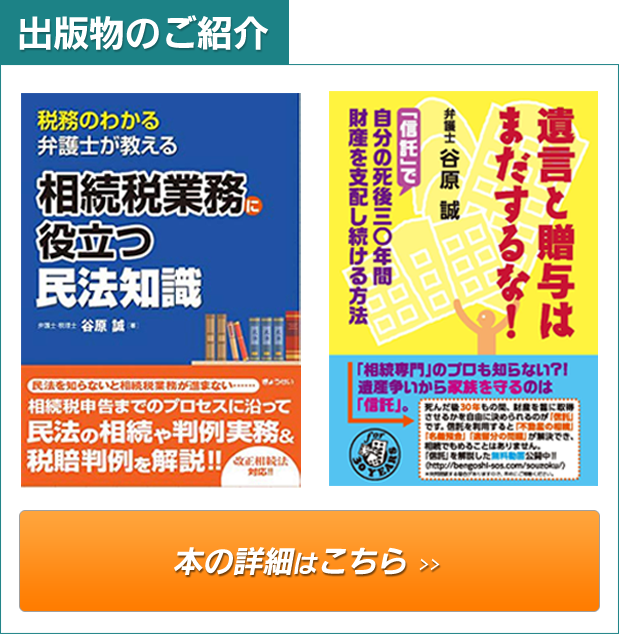相続で相手が弁護士を立ててきたら?|注意点と対処法
遺産分割などで、相手側(他の相続人)が弁護士を立ててきた場合の対応について解説します。
突然のことで驚く場合もあるでしょう。
また、今後の対応について不安を感じる場合もあると思います。
そこで本記事では、まず「相続の手続きと流れ」について簡単に解説します。
そして、あなたが「やるべきこと」と「やってはいけないこと」について、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
さらに、弁護士に相談・依頼するメリットや相続問題に強い弁護士の探し方も解説します。
ぜひ最後まで読んでいただき、相続で損をしないようにしていきましょう!
目次
遺産相続の流れと手続きを簡潔に解説
親が亡くなるなどして相続が発生すると、兄弟姉妹などの法定相続人の間で遺産分割を行なう必要があります。
何のもめごともなく話がまとまればいいのですが、相続では争いが生じてしまう場合があります。
できるだけスムーズに、早急に解決するには、まずは相続の基礎的な知識について知っておくことが大切です。
相続の手続きと流れ
①被相続人の死亡により相続開始
⇓
②遺言書の有無を確認
<遺言書がある場合>
公正証書遺言書や遺言が法務局に保管してある場合でなければ家庭裁判所の検認を受け、その後は遺言の執行。
<遺言書がない場合>
遺産分割をする必要があるため、負債額を確認したうえで、相続放棄するか、限定承認するかを決定(相続開始を知った日の翌日から3か月以内)。
・相続の承認・限定承認・放棄とは?
⇓
③準確定申告
納税者が亡くなった場合の確定申告(準確定申告)を行なう(4か月以内)。
参考資料:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告
(準確定申告)(国税庁)
⇓
④遺産分割協議
遺言書がなく、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議を行なう。
話し合いがまとまらない場合は、調停や審判に進む。
簡単に解説します。
弁護士がざっくり解説します。
⇓
⑤相続税の申告・納税
相続税の申告を行なう(被相続人が死亡したことを知った日=通常、被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内)。
他の相続人が弁護士を立ててきた場合の注意点と対処法
次に、遺産相続で他の相続人(兄弟姉妹など)が弁護士を立ててきた場合に、
- ・どのような対処すればいいのか?
- ・やってはいけない注意点とは?
というポイントについて解説していきます。
相手側の弁護士の対応を確認
する
相続人の間で遺産分割協議を開始し、進めていく過程で、相手側(他の相続人)が弁護士に依頼した場合、その弁護士が代理人となります。
相手側の弁護士から連絡が届くと思いますが、ここではまず、その弁護士がどのような対応をしてくるのかを見てみることが大切です。
弁護士の任務のひとつは、依頼人の正当な利益を実現することですが、弁護士によっては中立的な立場をとり、全体的な利益という観点から相続問題の解決を図る、つまり話をまとめようとしてくれる弁護士もいます(そのように見える場合も相手の弁護士は相手の最大利益を得ようとしていることを忘れないようにしてください)。
あわてて、ご自身もすぐに弁護士に依頼するのではなく、相手側の弁護士の出方、言い分を聞いて様子を見てみるのもいいと思います。
ただし、その弁護士は相手方の代理人であることを忘れてはいけません。
また、親族間の関係性、たとえば以前から仲が悪かった、関係が疎遠だったといったように、事情や状況はそれぞれの親族によって違うため、そのあたりも考慮し、判断されるのがいいでしょう。
相手側が弁護士を立ててきた
際に注意するべきポイント
相手側の弁護士からの連絡を
無視しない
相手側が弁護士に依頼した場合は、まずその弁護士から「受任通知」や「内容証明通知」が送られてくると思いますが、あなたはこれを無視しないでください。
無視していると、弁護士は「話し合いによる、遺産分割協議の成立の見込みがない」と判断して、すぐに遺産分割調停を申し立ててくる可能性があります。
<コラム①遺産分割調停とは?>
話し合いで遺産分割が整わない(解決しない)場合、または協議をすることができない時は、共同相続人は、家庭裁判所に対して遺産の分割を請求することができます(民法第907条2項)。
遺産分割調停は、調停委員の立ち合いのもとで合意を目指した話し合いを行なう裁判手続きで、家庭裁判所で行なわれます。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、資料などを提出する必要もあります。
参考資料:遺産分割調停(裁判所)
調停は、おおよそ月1回、平日の昼間に行なわれるため、仕事への支障が出る場合もあり、精神的な負担にもなります。
話し合い(遺産分割協議)で解決できるなら、それに越したことはないと思いますし、相手側の弁護士からの連絡を無視していれば、それだけ解決が遅れてしまいます。
弁護士からの通知書に回答期限がある場合は、その期限内に何らかの回答をすべきです。
あなたも弁護士を立てる準備をしているなら、弁護士に相談中である旨を伝えておくといいでしょうし、「回答にはもうしばらく時間がかかるので待ってほしい」といった連絡をしておいてもいいでしょう。
相手側の本人と直接交渉は
しない
相手側が弁護士を代理人として立ててきた場合、あなたは相手本人とは直接交渉しないようにしてください。
相手側の弁護士は、依頼者には「連絡がきても、直接交渉しないように」と伝えているはずです。
また、相手側の弁護士から届いた書面には、「今後はこちらに連絡してほしい」といった内容が記載されていると思います。
この段階では、あなたが相手の相続人に直接連絡しても、「弁護士を通してほしい」といった対応をしてくるでしょうから、話をしようとしてもムダ、意味のない行為ということになります。
相手側の弁護士への対応で
やってはいけないこと
弁護士からの質問にはその場で返答しない
相手側の弁護士と話をする際、質問された場合はその場で返答しないようにしましょう。
交渉に優れた弁護士は、主導権を握って話を進めながら、有利な展開に持っていき回答を引き出そうとしている可能性もあります。
ですから、相手の弁護士に有利な、つまり、あなたにとって不利になる回答を不用意にしないようにしなければいけません。
相手側の弁護士が用意した文書にはすぐに署名・捺印しない
これも①と同様、あなたが不利にならないように、書面にはすぐに署名・捺印してはいけません。
たとえば、相続に関わる代表的な文書に「遺産分割協議書」がありますが、一度、署名押印してしまうと取り消すことがほぼ不可能です。
遺産分割協議書には、「誰が」「どの遺産を」「どれだけ取得するか」といったことを記載しますが、この文書により、亡くなった方の預貯金引き出しや、不動産の名義変更が可能になるので、重要なものであることを認識していただきたいと思います。
相手側の弁護士から連絡が
こない場合は放置しない
あなたが、相手側の弁護士に連絡しても、連絡をしてこない、対応しようとしない場合があります。
じつはこれ、相手の戦略の可能性があります。
相手側が遺産分割をできるだけ先延ばしにしたいのかもしれません。
また、あなたを心理的に焦らせようとしている可能性もあります。
こうしたケースでは、あなたも早めに弁護士に相談・依頼するのがいいでしょう。
相続問題を弁護士に依頼する
メリットは大きい
- ・相手側の主張に納得がいかない。
- ・ご自身が不利な立場になっている。
- ・ご自身単独では相手側の弁護士との交渉を上手く進められない。
- ・交渉が決裂して遺産分割調停や審判に進んだ。
このような場合は、やはり弁護士に依頼して代理人になってもらうのがいいと思います。
なぜなら、次のようなメリットがあるからです。
遺産の全体像がわかる
相続人が、どういった遺産が、どのくらいあるのかを正確に把握するのは難しい場合があります。
たとえば、被相続人が亡くなった後に、相続人がまったく知らなかった預貯金口座が税務署から指摘される場合があります。
また、土地や建物、株式などを相続する場合、どのくらいの金額になるのか正確に評価するのは難しいでしょう。
その点、弁護士は、相続人本人では収集することが難しい情報を得ることができる場合があります。
金融機関や行政機関等に対して(弁護士会を通じて)、被相続人の財産に関する情報開示を求めることができる場合があるからです。
これを、「弁護士会照会」、または「23条照会」(弁護士法第23条の2に基づく)といいます。
弁護士会照会(23条照会)で情報請求できる財産には次のものなどがあります。
- ・預貯金
- ・有価証券
- ・自動車
- ・携帯電話の契約 など
なお不動産については、弁護士以外でも「名寄帳(なよせちょう)」という不動産の一覧表から調べることができます。
いずれにしても、弁護士に一括して調査してもらうことはメリットだといえるでしょう。
遺産分割協議で不利にならない
弁護士は法律と交渉のプロフェッショナルですから、相続の交渉相手が弁護士では、やはり分が悪いと言わざるを得ません。
そこで、あなたも弁護士に依頼して代理人になってもらうことで、相手側との交渉で不利になることがなくなります。
たとえば、次のような問題があった場合、相手側の主張が法的に妥当なものか判断し、交渉で的確に有利に対応することができます。
- ・相手側が法定相続分以上の要求をしていないか
- ・相手側が特別受益を受けていないか
- ・現物分割ではない分割方法(換価分割や代償分割など)によって遺産分割できないか
- ・寄与分の主張は妥当か
参考資料:No.4132 相続人の範囲と法定相続分
(国税庁)
・遺産分割はどのようにするか
相手側の弁護士とのやり取り
から解放される
交渉のプロである弁護士との交渉はシビアなものになる場合もあります。
相続の法的知識はあまりなく、シビアな交渉の経験のない方では、弁護士とのやり取りは大きなプレッシャーや精神的ストレスになるでしょう。
その点、弁護士に依頼して代理人となってもらうことで、あなたは難しい交渉事から解放されるのです。
早期解決が可能
できれば兄弟姉妹などとは争いたくないという方も多いと思います。
やはり相続に関する問題は、できれば早期に解決したいと思われるのではないでしょうか。
その点、相続に精通した弁護士であれば、感情的な対立を避けながら、できるだけ早期に相続問題を解決に導くことができるでしょう。
相続に関するさまざまな
手続きを任せることができる
弁護士に依頼することで、相続に関するさまざまな相談をすることができます。
さらには、遺産分割協議書の作成や各種相続手続きなども任せることができるので、依頼者としては安心して日常生活を送ることができ、仕事に注力することもできるのです。
- ・法定相続人調査
- ・相続財産調査
- ・相続放棄の申立代理
- ・遺言検認の申立代理
- ・遺産分割の代理
- ・調停・審判の代理 など
弁護士費用の相場を確認
弁護士に依頼するとなると、やはり費用がかかります。
依頼する案件の内容や法律事務所の違いによって、金額は変わってきますが、基本的に必要な弁護士費用の項目には次のものがあります。
- ・相談料
- ・着手金
- ・報酬金
- ・実費 など
相談料は30分5,000円が相場ですが、初回は無料で対応している事務所も多いと思います。
ちなみに、みらい総合法律事務所では、事案によりますが、初回面談60分以内は無料で行なっています。
※30分超過ごとに5,500円(消費税込)をいただくことになっています。
詳しい内容は、こちらの記事を参考にしてください。
・相続・遺産分割の弁護士費用の相場|
誰が払うのか?
弁護士がざっくり解説します。
相続に強い弁護士の探し方を
チェック
相談・依頼する際、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
相続問題の実務の経験がなかったり、浅い場合などでは、相談者が不利益を被ってしまう可能性もあります。
やはり、相続問題の知見と経験が豊富な「相続に強い」弁護士に依頼するのが、もっとも確実です。
- ・弁護士の実務経験年数
- ・相続問題に関する書籍の執筆経験
- ・わかりやすい説明力
- ・迅速で適切な対応力
- ・適正で明瞭な弁護士費用の提示
- ・人間的な相性も重要
詳しい内容は、こちらの記事で確認することができますので、ぜひご覧ください。
弁護士法人みらい総合法律事務所では、依頼者の経済的な負担を少しでも軽減するためのシステムを採用しています。
そこで、まずは無料相談の利用をおすすめしています(※随時開催していますが、事案によるので、お問い合わせください)。
実際の面談では、説明がわかりやすいか、案件の経験が豊富か、相性は合うかなどを確認してください。
事務員しか対応してくれない事務所はおすすめしません。
法律相談は弁護士しかできませんので、直接弁護士と話をしてください。
そして、「この弁護士なら信頼できる、任せたい」と判断されたら正式に依頼をしていただく、という流れで問題ありません。
遺産の相続でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。