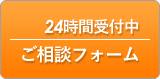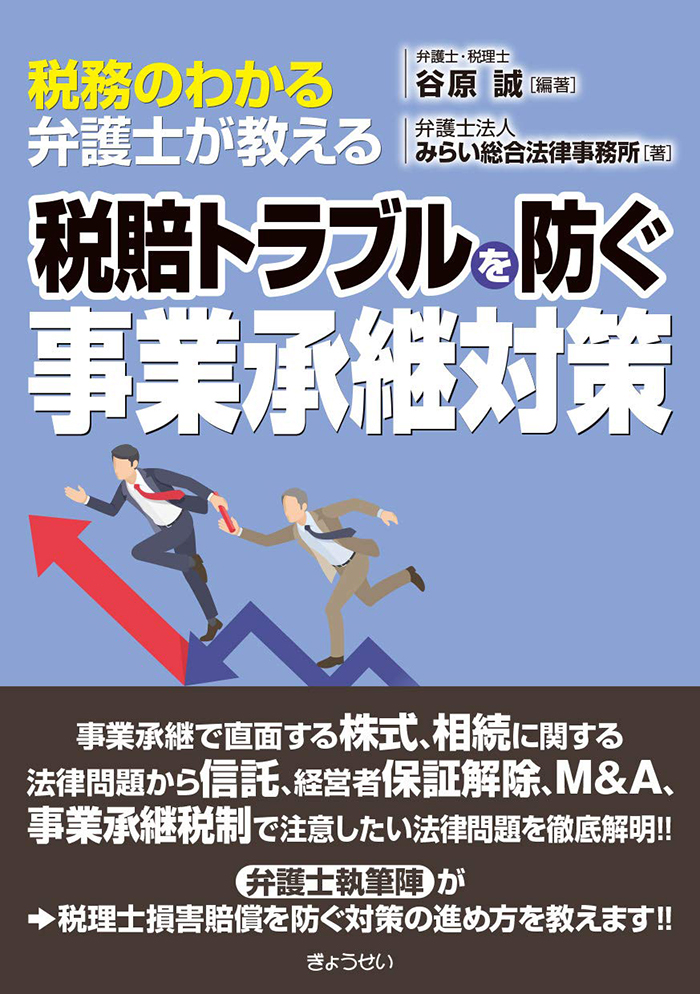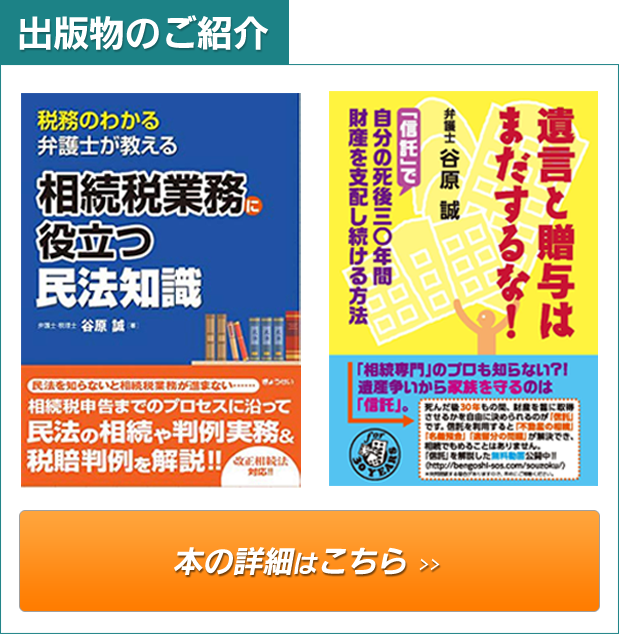簡単に遺留分を請求する方法【5ステップ】
目次
遺留分とはどのような制度か
遺産相続が発生した場合に、被相続人がすでに生前に財産を贈与していたり、遺言により他の人に遺贈または相続させている場合があります。
その場合、自分が相続する財産が全くなかったり、あるいは、とても少なくなってしまう場合があります。
このような場合には、「遺留分」という制度により、権利を確保することができます。
遺留分というは、被相続人の財産で、被相続人が自分の意思で処分しようとしても、一定割合で処分することができない、という割合のことです。
つまり、遺留分の権利を持っている人は、被相続人が全ての財産を贈与等していても、その中から、一定割合を確保することができる、ということです。
この遺留分の制度は、近親者の生活保障や被相続人の遺産形成・維持への貢献を考慮した遺産の再配分の意味を持っています。また、配偶者の遺留分については、実質的な夫婦共有財産の清算という意味も持っています。
遺留分の権利を行使すると、2019年7月1日以降に開始する相続については、遺留分に相当する金銭の請求をできることになります。
それ以前は、遺留分を行使すると、たとえば不動産が共有になってしまったのですが、相続法改正により、お金の問題として解決されることになった、ということです。
この記事では、遺留分を侵害された人が、遺留分を請求していくために必要な知識について解説しています。
【参考記事】
「遺留分とは、どのようなものか?」
遺留分は、どの程度もらえるか
では、遺留分の権利を持っている人は、誰でしょうか?
答えは、
①配偶者
②子
③直系尊属(父、母等)
です。
兄弟姉妹は、遺留分がありません。
また、相続欠格者や相続人から廃除された者、相続放棄をした者にも遺留分はありません。
子が死亡している時は、その子が代襲相続人として遺留分を有します。
次に、遺留分権利者は、どの程度の財産について、遺留分を主張できるのでしょうか?
次のようになります。
①直系尊属のみが相続人の場合 財産の3分の1
②直系尊属以外の者が相続人に含まれる場合 財産の2分の1
この割合を「総体的遺留分」といいます。
そして、この総体的遺留分を基礎として、法定相続分に従って、個別的遺留分を計算することになります。
たとえば、配偶者と子2人がいる場合、総体的遺留分は、2分の1となります。
そして、法定相続分は、配偶者が2分の1、子が4分の1ずつです。
そうすると、これに2分の1を掛けて、遺留分は、配偶者が4分の1、子が8分の1ずつ、ということになります。
遺留分の計算の方法
個別的遺留分を計算するには、まず、計算の基礎となる基礎財産を計算することになります。
基礎財産は、次のように計算されます。
基礎財産=(被相続人が相続開始時点で有していた財産)+(贈与財産)―(相続債務)
この基礎財産に、個別的遺留分を掛けて、遺留分侵害額を計算することになります。
計算の基礎となる贈与・遺贈の範囲
遺留分計算のための基礎財産は、被相続人が相続開始時点で有していた財産に贈与財産を加えますが、どこまでの贈与・遺贈を加えるのか、が次に問題となります。
2019年7月1日以降に開始される相続は、次のようになります。
(1)被相続人が相続人に対して贈与した場合
①特別受益に該当する贈与であり、
かつ、
②相続開始前10年間にされたものに限り、
その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入します。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、10年より前にされたものであっても、全て遺留分算定のための基礎財産の価額に算入します。
(2)被相続人が相続人以外の者に対して贈与した場合
相続開始前の1年間にされたものに限り、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入します。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、1年より前にされたものであっても、遺留分算定のための基礎財産の価額に算入することとなります。
ここで、「損害を加えることを知って」というのは、遺留分権利者に損害を加えるべき事実を知っていることで足り、加害の意思を有していたことを要しないとされています(大審院昭和4年6月22日判決)。
特別受益を受けた相続人が相続放棄をした場合には、はじめから相続人でなかったことになりますので、(1)ではなく、相続人ではない者として、(2)によって計算することになります。
生命保険金の受取人に指定されている者が生命保険金を受け取った場合、その生命保険金も基礎財産になるかどうかについて、判例は、否定しています(最高裁平成14年11月5日判決)。
遺留分を請求する相手は誰か?
では、遺留分権利者は、誰に対して遺留分を請求することになるのでしょうか?
これについては、次のように法律で定められています。
①受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担します。
②受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合において、その贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言者がその遺言に別の意思表示をしているときは、その順番に従います。
③受贈者が複数あるとき(同時贈与を除く)は、後の贈与に係る受贈者から、順次、前の贈与に係る受贈者が負担します。
したがって、遺留分権利者としては、上記の順番に従って、遺留分侵害額請求をすることになります。
遺留分の時効に注意!
遺留分で、一つ注意しなければならないことがあります。
それは、遺留分侵害額請求権には、消滅時効がある、ということです。
つまり、一定期限内に遺留分侵害額請求権を行使しないと、時効によって消滅し、永久に権利がなくなってしまう、ということです。
では、遺留分侵害額請求権の消滅時効は、何年でしょうか?
次のようになっています。
(1)遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
(2)仮に、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始のときから10年をしたときは、権利が消滅します。
ここで、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき」というのは、
①遺留分権利者が相続の開始および遺贈・贈与があったことを知り、
②その遺贈・贈与が遺留分を侵害するものであることを知る
ことです。
したがって、遺留分権利者は、遺留分を侵害されたことを知った場合には、すぐに行動を起こし、遺留分侵害額請求をする必要があります。
【参考記事】
遺留分侵害額請求権の時効とは
遺留分を請求する方法
では、遺留分権利者は、どのようにして遺留分侵害額請求権を行使したらよいのでしょうか?
5つのステップで説明します。
(1)遺留分を侵害されているか確認する
まず、遺留分侵害額請求をするには、自分の遺留分が侵害されていることを知ることが必要です。
そこで、被相続人の資産及び負債がどの程度あるのかを調査することになります。
遺言書を探し、他の相続人に確認し、銀行などに取引利益の開示請求等を行って、調査をしていくことになります。
また、生前の贈与も遺留分計算の基礎財産になりますので、生前贈与があったかどうか、なども調査することになります。
(2)まず遺留分侵害額請求をする
調査により、自分の遺留分が侵害されていることがわかったら、消滅時効がありますので、早めに対象者に対して、遺留分侵害額請求をすることになります。
具体的には、内容証明郵便で、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をします。
内容証明郵便は、どのような内容の手紙を送ったのか、を証明できる郵便で、かつ、相手に届いたことも証明できるものです。
遺留分侵害額請求権には、消滅時効があるので、権利を行使したことを証明できるようにしておく必要がある、ということです。
一旦、遺留分侵害額請求権を行使すると、金銭請求権が発生することになりますので、消滅時効期間が変わります。
金銭請求をすることができることを知った時から5年、あるいは知らなくても10年で消滅時効となります。
(3)遺留分侵害した贈与を探す
遺留分侵害額は、遺留分計算の基礎財産が大きくなればなるほど金額も大きくなります。
遺贈については、遺言書で明らかになりますが、生前に贈与した分については、調査が困難である場合もあるでしょう。
根気よく探してくことが必要です。
たとえば、昔所有していた不動産が相続開始時に所有していない、ということであれば、その所在地を探して不動産の全部事項証明書を取得して、誰に移転したのか、などを調査します。
そして、それが生前贈与でないのか、などを調査します。
(4)交渉する
いよいよ交渉開始です。
当事者同士で話し合いがつけば、それに越したことはありません。
受贈者や受遺者と交渉し、財産を評価し、いくらもらうのか、支払い期限はいつなのか、などについて話し合いを行います。
場合によっては、不動産など金銭ではないものをもらうことにより解決することもありえます。
この場合、法律的には、遺留分侵害額請求権を行使したことによって、金銭請求権が発生し、それを不動産などで代物弁済した、ということになります。
当事者同士で話し合いを行い、合意した場合には、「合意書」などの書面を取り交わします。
後で紛争にならないように、実印で押印し、印鑑証明書を取り交わしておく方が望ましいでしょう。
また、相手が支払ってくれない場合もあると思います。
その際に、すぐに強制執行できるように、公正証書にすることも検討しましょう。
強制執行受諾文言付きの公正証書にしておけば、相手が支払いをしない場合には、その公正証書に基づいて強制執行をすることができます。
(5)裁判を起こす
交渉が決裂した場合には、裁判を起こすことになります。
裁判となると、もはや素人では難しいので、弁護士に依頼することになるでしょう。
短くて半年、通常1年から2年くらいかかることを覚悟しておく必要があるでしょう。
相続に強い弁護士を探して依頼することをおすすめします。
もちろん、みらい総合法律事務所でもご相談をお受けしています。