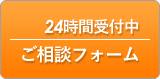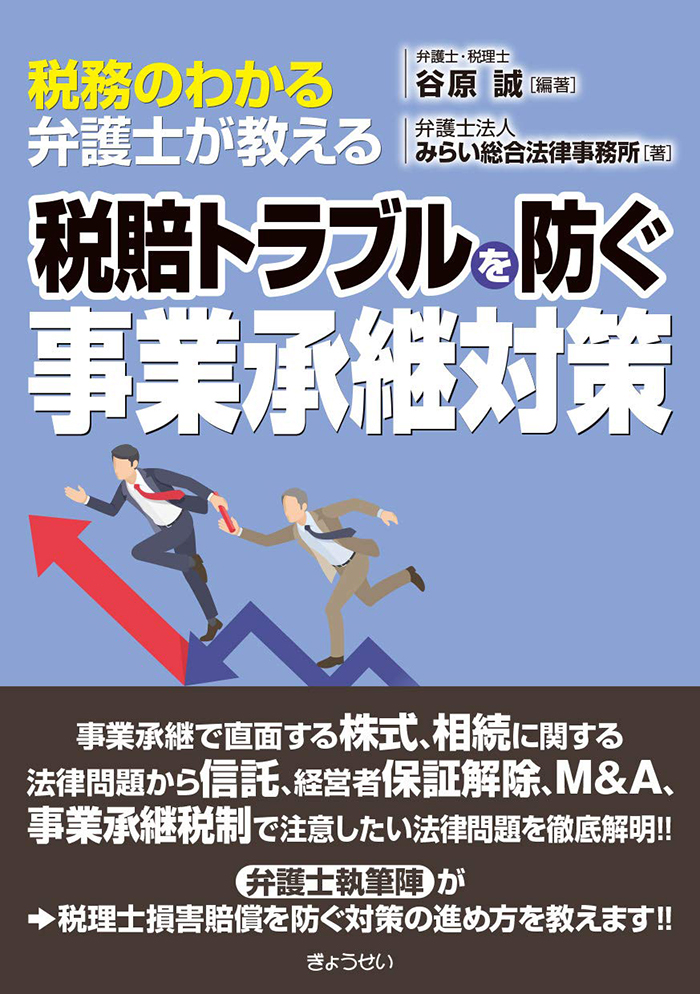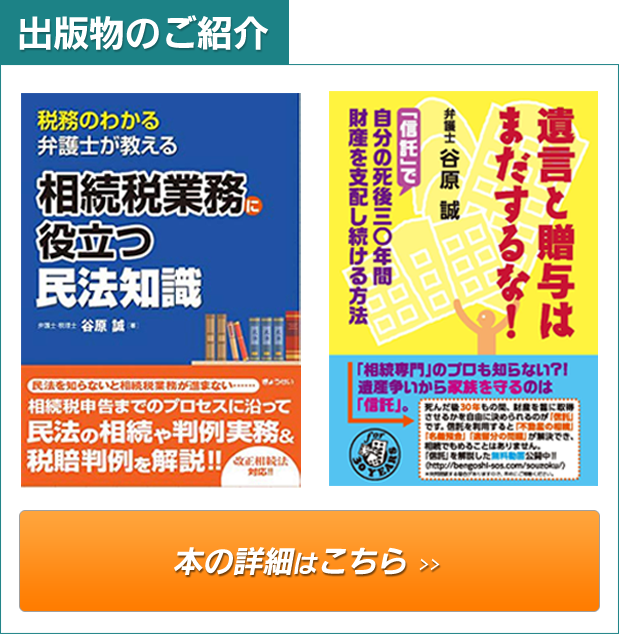遺言で注意しなければならないこと
目次
遺言を変更したいときは
一旦、遺言書を書き上げても、内容を間違って書いてしまったり、後で遺言の内容を変更したい場合もでてきます。
この場合も、遺言を変更するには要件が決まっており、その要件を欠くと遺言を変更することができませんので注意が必要です。
公正証書遺言以外の遺言の場合、次のように遺言を変更できます。
①遺言者は、変更箇所を指示する。
②変更した旨付記し、署名し、変更した箇所に押印する。
変更の要件を満たさないときは、変更が無効となって、遺言は変更がなかったものとして元の遺言のとおりの効力を有します。
財産目録を自書しなかった場合の目録加除訂正は、
①旧財産目録を新財産目録のとおりに訂正する旨の文言を自書し、
②新財産目録の1枚1枚に署名し、押します。
なお、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されてしまうので、変更はできず、新たな遺言で遺言を撤回するか、別の遺言をすることにより内容を変更することになります。
遺言の証人や立会人になれない人
公正証書遺言などでは証人が必要となります。
また、特別方式で立会人が必要となる場合があります。
しかし、誰でもよい、というわけではありません。
遺言で証人や立会人が必要な場合、次の者は証人や立会人になることができません(民法第974条)。
①未成年者
②遺言作成時の推定相続人および受遺者
③②の配偶者および直系血族
④公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
欠格者が証人や立会人になった結果、法律の要件を満たさなかった場合は、遺言は無効になります。
共同遺言は無効
2人以上の者が同一の証書で遺言をすると、遺言が無効になります(民法第975条)。
夫婦で1通の証書に遺言をするような場合です。
家庭裁判所による遺言書の検認
遺言書が発見された場合には、公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所による検認の手続をする必要があります。
相続開始を知った後、遺言書を発見した者は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の請求をしなければなりません(民法第1004条)。
家庭裁判所の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言書が封印されているときは、相続人またはその代理人の立ち会いを得て、家庭裁判所において開封される必要がありますので、勝手に封印を開封してはいけません。
家庭裁判所以外で開封したり、検認手続を得ないで遺言を執行した場合は、5万円以下の過料の制裁があります(民法第1005条)が、遺言が無効になるわけではありません。
家庭裁判所による検認の手続は、証拠保全を目的とするので、遺言書の有効性や効力については判断されません。
遺言書の有効性に疑問がある者は、検認手続後、訴訟等で争うことが可能です。
遺言書を保管又は発見した相続人の中には、遺言書に自己に不利な内容が書いていることを理由に、遺言書を破棄または隠匿しようとする人がいますが、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿は、相続人の欠格事由に該当します(民法第891条5号)。
相続法改正により新設された法務局による自筆証書遺言の保管制度が利用された場合には、検認は不要となります。
遺言の無効・取り消し・失効
遺言は、意思表示なので、一定の事由があるときは、その遺言は無効となり、または取り消しの対象となります。
以下に説明します。
方式違背
遺言は、一定の方式を備えることを要件とされていますから、法律で定められた方式に違反するときは、その遺言は無効です。
ただし、ある遺言の方式に違反して無効とされていても、他の遺言の方式を満たしているときは、他の遺言として有効となる余地があります。
たとえば、秘密証書遺言として作成したにもかかわらず、証人の人数が足りずに無効となった場合でも、自筆証書遺言としての方式を具備している場合には、自筆証書遺言として有効となります。
遺言能力を欠く場合
満15歳に達しない者による遺言は無効です(民法第961条)。
満15歳に達していても、意思表示である以上、意思能力のない者のした遺言は無効となります。
高齢で意思能力に不安がある場合には、医師の診断書等を取得し、意思能力に関する証拠を揃えておくことも検討することになります。
他にも、時間の経過とともに廃棄の可能性のある看護記録やカルテ等も取得しておくことも検討します。
認知症の進行を判断するには、長谷川式認知症スケール等もありますので、状況に合わせて判断します。
また、遺言者と面談して打ち合わせをするような機会があるのであれば、その面談時の会話を録音し、または録画等をしておくことも遺言能力の立証にとって有効です。
東京地裁平成29年6月6日判決(判例時報2370号68頁)は、アルツハイマー型認知症を発症していた被相続人が公正証書遺言をした事例において、長谷川式認知症スケールや医師の意見書、日常の行動などを検討したうえで、遺言の当時、遺言能力がなかったとして、公正証書遺言を無効としました。
成年被後見人は本心に復していることを証明する2人以上の医師の立ち会いを得て遺言を行うことができます(民法第973条1項)。
この場合、立ち会った医師は、遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければなりません。
ただし、秘密証書遺言の場合には、その封紙にその旨の記載をし、署名し、押印しなければなりません(同条2項)。
被保佐人は、保佐人の同意なしに遺言することができます(民法第962条)。
意思表示に瑕疵がある場合
遺言者の遺言が錯誤によるものである場合には、無効となります(民法第95条)。
また、第三者の詐欺または強迫により遺言したものである場合には、遺言者は遺言を取り消すことができます(民法第96条)。
遺言の内容に瑕疵がある場合
遺言の内容が公序良俗や強行法規に違反する場合には、その遺言は無効となります(民法第90条)。
また、遺言の内容の解釈ができない場合には、その遺言の内容を実現できないので、無効です。
被後見人による遺言
被後見人が、後見人の後見の計算終了前に、後見人またはその配偶者の利益になるような遺言をした場合には、その遺言は無効となります。
ただし、後見人が直系血族、配偶者または兄弟姉妹である場合は除きます(民法第966条)。
受遺者の死亡
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。
停止条件付遺贈の場合には、受遺者が条件成就前に死亡したときも、効力を生じません。
ただし、遺言者が反対の意思を遺言に表示したときは、それに従うことになります(民法第994条1項、2項)。
目的物の不存在
遺贈は、遺贈の目的である権利が遺言者の死亡のときにおいて相続財産に属しなかったときは、効力を生じません。
ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、遺贈の目的としたときは、その意思に従うことになります(民法第996条)。
特別方式遺言の失効
特別方式による遺言は、遺言者が普通方式による遺言をすることができるようになったときから6ヵ月間生存するときは、その効力を生じません(民法第983条)。