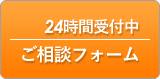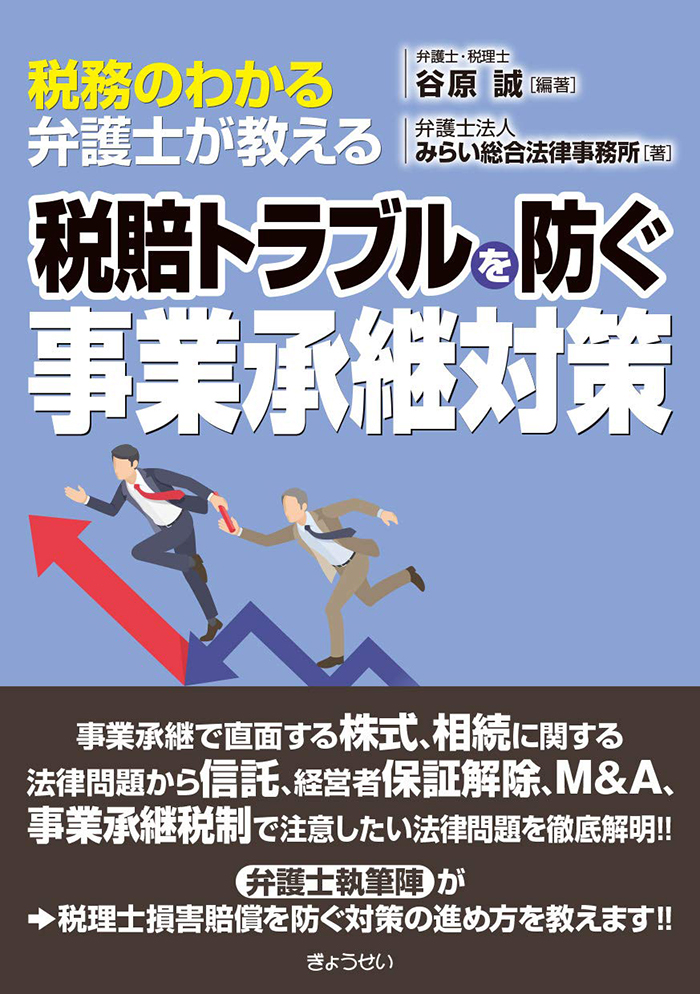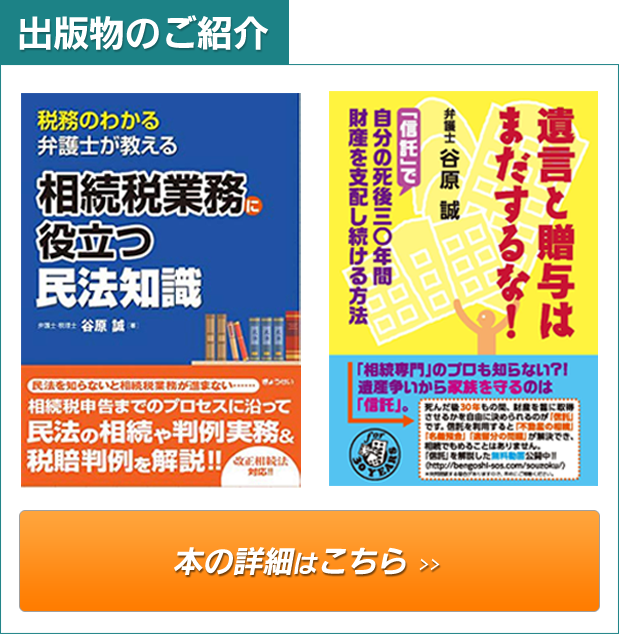親族が亡くなった場合、誰が相続人になるか?
どの順番で相続するか?
親族が亡くなったときには、相続が発生します。
相続が発生するというのは、亡くなった親族の財産が残された親族に承継されるわけです。
しかし、誰にどう承継されるかが決まっていなければ、喧嘩になってしまいます。
遺言書があれば、そのとおりに承継されることになります。
では、遺言書がない場合には、どうなるでしょうか。
遺言書がない場合には、相続財産は、遺産分割により相続人に承継されることになります。
そこで、いかなる範囲の者が相続人になるかを確定することが必要となります。
相続人となるのは、被相続人の配偶者および被相続人の血族です。
配偶者は常に相続人となります(民法第890条)が、血族については、相続人となるべき順序が定められています。
この場合の配偶者は、法律婚の配偶者であり、内縁配偶者を含みません。
内縁配偶者が被相続人の財産を取得するには、被相続人と死因贈与契約を締結するか、遺贈を受けるか、あるいは、被相続人に相続人がいない場合に特別縁故者として分与を求めることになります(民法第958条の3)。
なお、改正相続法では、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合などの特別寄与料の請求の制度を創設していますが、詳しくは、第9章で説明します。
血族相続人は、次の順序で相続人となります。
先順位の血族相続人がいない場合に初めて後順位の血族相続人が相続権を持ちます。
先順位の血族相続人がいない場合というのは、初めから存在しない場合、相続欠格(民法第891条)、廃除(民法第892条、893条)、相続放棄(民法第939条)の場合をいいます。
①第1順位 子(民法第887条)
②第2順位 直系尊属(民法第889条1項1号)
③第3順位 兄弟姉妹(民法第889条1項2号)
「子」は、分娩、嫡出推定、認知、養子縁組による場合があります。
普通養子は、実親の相続権と養親の相続権を持ちますが、特別養子の場合には、縁組によって実親との親族関係が終了するので、実親の相続権を喪失します。
胎児の相続については、すでに生まれたものとみなし、相続権を持ちます(民法第886条1項)。
ただし、胎児が死体で生まれたときは、生まれたものとはみなされなくなります(同条2項)。
胎児が生まれる前に遺産分割を行った後で、胎児が死体で生まれたときは、胎児に帰属するとされた財産についての遺産分割は無効となり、その財産について改めて遺産分割が必要になるので、胎児の出生を待って遺産分割を行うのが通常です。
被相続人に父母と祖父母がいるような場合には、親等の近い父母のみが相続権を持つことになります。
相続税の申告期限は、相続人が、その相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です(相続税法第27条1項)。
胎児については、「相続の開始を知った日」は、法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日とされています(相続税基本通達27-4●)。
胎児が生まれる前に他の相続人が相続税の申告書を提出する場合は、胎児は相続人の数には算入しないこととされています(相続税基本通達15-3)。
この場合に、後日胎児が生まれたときは、過大な相続税を申告していることになるので、胎児が生まれたことを知った日の翌日から4ヵ月以内に更正の請求を行うことになります(相続税基本通達32-1)。
代襲相続とは?
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があることによって相続権を失ったときは、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合にはその子に限ります)が、その者の受けるはずだった相続分を、被相続人から直接に相続することをいいます(民法第887条2項、889条2項)。
被相続人の「死亡以前」ということなので、被相続人と同時に死亡した場合も含まれます。
この場合の相続権を失って相続できなくなった者を「被代襲者」といい、被代襲者に代わって相続する者のことを「代襲相続人」といいます。
被代襲者は、被相続人の子(直系卑属)または兄弟姉妹に限られ、直系尊属や配偶者は含まれません。
代襲原因は、①相続開始以前の死亡、②相続欠格、③廃除、に限られ、相続放棄は含まれません。
代襲相続人の要件は、①被代襲者の直系卑属であること、②被相続人の直系卑属であること(被相続人の子が被代襲者の場合)、③相続開始時に存在していること、④被相続人から廃除された者または欠格者でないこと、です。
養子縁組の場合には、養子縁組の日から養子と養親との間に親子関係が発生します。
したがって、被代襲者が被相続人の養子である場合において、養子縁組前に生まれた被代襲者の子は、被相続人の直系卑属ではないので、代襲相続人とはなりません。
しかし、養子縁組前に生まれた被代襲者の子は、代襲相続人になります。
被相続人の死亡以前に、子が死亡している場合、孫が代襲相続人となりますが、この孫に代襲原因がある場合には、孫の子(曾孫)が代襲相続人になります(民法第887条3項)。
これを「再代襲」といいます。
ただし、兄弟姉妹については、代襲相続のみが認められ、「再代襲」は認められません。
これは、「笑う相続人」の出現を抑制するため、とされています。
代襲相続人は、被代襲者の相続順位に繰り上がって被相続人を直接相続しますが、代襲相続人が複数いる場合は、各自の相続分は被代襲者の受けるべきであった相続分を等分に相続することになります。
相続資格が重複する場合
養子縁組があることにより、相続権を重複して持つ結果となる場合があります。
この場合に、相続権の重複は認められるのか、という問題があります。
たとえば、被相続人が孫を養子にした場合を考えてみます。
被相続人の死亡以前に被相続人の子が死亡した場合には、被相続人の孫が代襲相続人となります。
また、養子は、独自に相続権を持ちます。
この場合、代襲相続人として被相続人の子の相続分を相続することと、養子としての相続分を相続することは両立するため、相続権の重複行使が認められます。
相続欠格者は相続できない
相続欠格とは、被相続人の意思と無関係に、一定の事由があれば、法律上当然に何らの手続を要することなく、相続権が剥奪される制度です。
相続人であっても、以下に該当する場合には、相続権がありません。
また、遺贈を受けることもできません(民法第965条、891条)。
①故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡させるか、死亡させようとしたために刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたことを知ったのに、告発・告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときは含まれない。
③詐欺・強迫によって、相続に関する被相続人の遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者
④詐欺・強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更をさせた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
ただし、破棄または隠匿が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、あたりません。
最高裁平成9年1月28日判決(民法百選Ⅲ52)は、破棄または隠匿した遺言書が、破棄または隠匿した者にとって有利であったことを理由に、欠格事由に該当しないと判断しました。
相続欠格の効果は、一身専属的であり、欠格者に直系卑属があり、代襲相続の要件を満たせば、この者が代襲相続人となります(民法第887条2項、3項)。
相続人の廃除とは?
特定の相続人について、被相続人が財産を相続させることを欲せず、かつ欲しないことが一般の法感情から考えて、もっともだと認められる事情があるときは、被相続人の意思により、家庭裁判所がその相続人の相続権を剥奪することができます。
これを「相続人の廃除」といいます(民法第892条、893条)。
相続人の廃除の対象となるのは、推定相続人(相続開始の際に相続人となるべき者)のうち、遺留分を有する者です。
したがって、兄弟姉妹は遺留分がないので、廃除の対象とはなりません。
なぜなら、兄弟姉妹に財産を取得させたくない被相続人は、他の者に贈与または遺贈をし、または兄弟姉妹の相続分をゼロと指定することにより、その希望を実現できるため、あえて廃除を認める必要がないためです。
相続人を廃除するには、
①相続人が被相続人に対して虐待又は重大な侮辱をしたこと
②相続人にその他の著しい非行がること
が必要です。
①の「虐待又は重大な侮辱」について、東京高裁平成4年12月11日決定(民法百選Ⅲ53)は、「民法第892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきである」としています。
そして、子供の頃から少年院送致を含む非行を繰り返し、暴力団員と同棲、婚姻し、父母が婚姻に反対していることを知りながら、父の名で披露宴の招待状を出すなどした行為が「虐待又は重大な侮辱」にあたるとしました。
また、大阪高裁平成15年3月27日決定(判例タイムズ臨時増刊1154号114頁)は、被相続人の多額の財産をギャンブルにつぎ込んでこれを減少させ、被相続人をして,自宅の売却までせざるをえない状況に追い込んだこと、会社の取締役を解任されたことを不満に思い、虚偽の金銭消費貸借契約や虚偽の賃貸借契約を作出し、民事訴訟になり、訴訟でも被相続人と敵対する不正な証言を行うことによって、高齢である被相続人に多大の心労を背負わせたことをもって、「著しい非行」にあたるとしました。
反対に、廃除を認めなかった裁判例として、東京高裁平成8年9月2日決定(民商法雑誌119巻6号969頁)があります。
この決定では、嫁姑関係の不和に起因して、被相続人と相続人が頻繁に口論し、その結果、暴力にまで発展しましたが、それは、相続人夫婦と被相続人夫婦の双方に責任があるというべきであり、被相続人にも相応の責任があるとみるのが相当であること、相続人は被相続人から請われて同居し、同居に際しては改築費用の相当額を負担し、家業の農業も手伝ってきたこと、被相続人は死亡するまで相続人との同居を継続したこと、から相続人と被相続人は家族としての協力関係を一応保っていたというべきで、相続的共同関係が破壊されていたとまではいえない、としています。
被相続人が推定相続人を廃除するには、生前に家庭裁判所に廃除の請求をするか、あるいは、遺言で廃除の意思表示をすることになります。
遺言による廃除の場合には、遺言執行者が被相続人の死後に遅滞なく廃除の申立をすることになります。
この場合には、廃除の効果は被相続人の死亡のときに遡って生じます。
なお、廃除された場合でも、相続欠格と異なり、被相続人から遺贈を受けることができます。
被相続人は、いつでも廃除の取消を家庭裁判所に請求することができますし、また、廃除を取り消さず、贈与や死因贈与、または遺贈をすることにより、廃除した推定相続人に財産を取得させることができます。
廃除の申立人は、廃除が確定した日から10日以内に、被相続人の本籍地の市区町村に推定相続人廃除届けを提出します(戸籍法第97条、63条1項)。
その結果、相続人の戸籍に廃除事項が記載されることになります。
相続税の申告書を提出した後に、廃除に関する裁判が確定し、課税価格および相続税額が過大となった場合は、裁判の確定を知った日の翌日から4ヵ月以内に更正の請求をすることができます(相続税法第32条1項2号)。