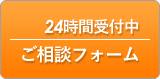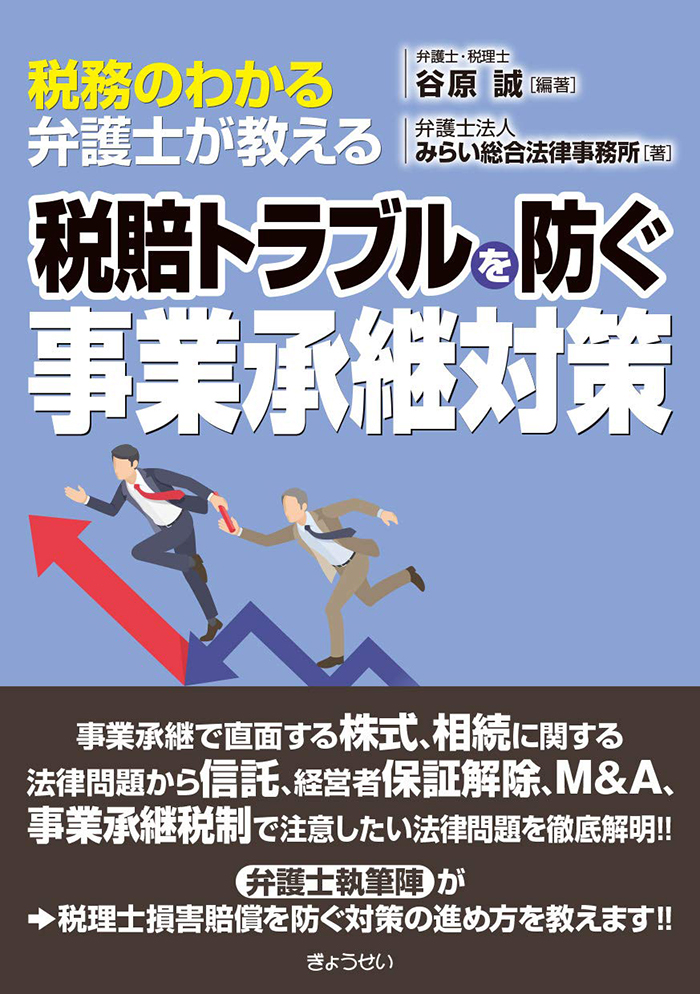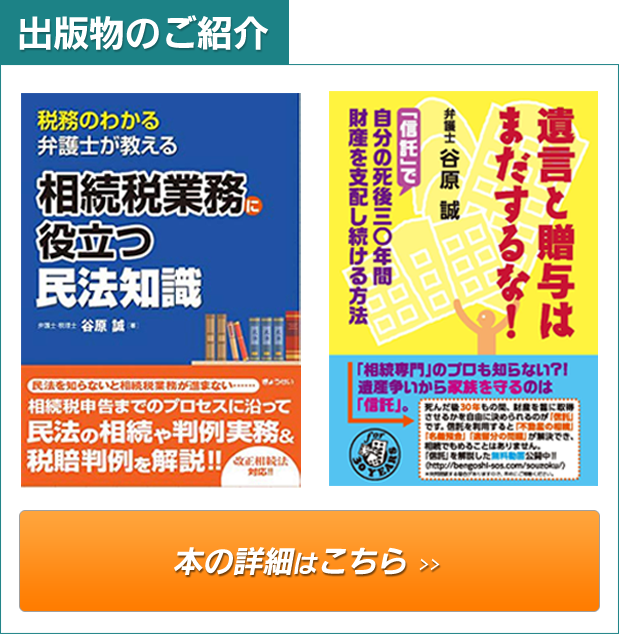相続財産には、どのようなものがあるか?
相続財産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
動産も不動産もあり、債権も債務も含みます。
国内にある財産も国外にある財産も全てです。
相続財産の中で注意すべきものについて説明します。
目次
祭祀承継
系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、相続の対象とならず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
被相続人が指定したときは、その指定に従います。
被相続人の指定もなく、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が決定することになります(民法第897条1項、2項)。
一身専属的権利義務
相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、承継されません(同条但し書き)。
一身に専属したものについては、法律に規定するものと、その性質上一身に専属したものがあります。
民法に規定するものとしては、次のようなものがあります。
①代理における本人・代理人の地位(民法第111条)
②使用貸借の借主の地位(民法第599条)
③委任契約における委任者・受任者の地位(民法第653条)
④組合における組合員の地位(民法第679条)
その性質上一身に専属した権利としては、身元保証契約における責任具体化前の地位、扶養の権利義務、親権などがあります。
ただし、判例の中には、上記に反する結論を出しているものもあります。
建物所有目的の土地の使用貸借について、東京地裁平成5年9月14日判決(判例タイムズ870号208頁)は、次のように判示しています。
「民法上、使用貸借契約は、借主の死亡によってその効力を失うとの規定が存する(同法599条)。
しかしながら、同規定は、使用貸借が無償契約であることに鑑み、貸主が借主との特別な関係に基づいて貸していると見るべき場合が多いことから、当事者の意思を推測して、借主が死亡してもその相続人への権利の承継をさせないことにしたにすぎないものと解される。
そして、土地に関する使用貸借契約がその敷地上の建物を所有することを目的としている場合には、当事者間の個人的要素以上に敷地上の建物所有の目的が重視されるべきであって、特段の事情のない限り、建物所有の用途にしたがってその使用を終えたときに、その返還の時期が到来するものと解するのが相当であるから、借主が死亡したとしても、土地に関する使用貸借契約が当然に終了するということにならないというべきである。」
また、建物を使用貸借している借主が死亡した事案について、東京高裁平成13年4月18日判決(判例時報1754号79頁)は、「民法599条は借主の死亡を使用貸借の終了原因としている。
これは使用貸借関係が貸主と借主の特別な人的関係に基礎を置くものであることに由来する。
しかし、本件のように貸主と借主との間に実親子同然の関係があり、貸主が借主の家族と長年同居してきたような場合、貸主と借主の家族との間には、貸主と借主本人との間と同様の特別な人的関係があるというべきであるから、このような場合に民法599条は適用されないものと解するのが相当である」と判示しています。
死亡保険金
被相続人を被保険者とする死亡保険金請求権については、受取人の指定の仕方によって、相続財産になるかどうかが異なります。
まず、被相続人自らを死亡保険金の受取人に指定した場合は、相続財産となり、相続人に相続されることとなります。
次に、特定の相続人を受取人に指定した場合は、死亡保険金請求権は、保険契約に基づき、保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであり、被相続人から承継取得したものではないとして、相続財産にならないとされています(最高裁昭和40年2月2日判決・民集19巻1号1頁)。
養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権またはこれを行使して取得した死亡保険金が、民法第903条1項(特別受益)に規定する遺贈または贈与に係る財産にあたるかいなかが争われた事案があります。
この事案において、最高裁平成16年10月29日判決(百選Ⅲ61)は、死亡保険金請求権は、保険契約に基づき、保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであり、被相続人から承継取得したものではないとして、相続財産にならないこと、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡したときに初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないことから、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたとみることができないこと、などから、特別受益に該当する遺贈または贈与にかかる財産にはあたらない、と判示しました。
ただし、その結果、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」としました。
そして、「特段の事情」の判断基準としては、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断」するものとしています。
そして、この事例では、「特段の事情」はないとして、特別受益性を否定しました。
ちなみに、この事例は、遺産総額が6399万7631円で、相続人の1人が受領した死亡保険金等合計793万5057円でしたので、遺産総額に対する割合は、約12%です。
同じく、持戻しの対象とはならなかった事例としては、大阪家裁堺支部審判平成18年3月22日(家裁月報58巻10号84頁)があります。
この事案は、遺産総額が6963万8389円で、死亡保険金が428万9134円です。
裁判所は、遺産総額に対する割合が6%余りにすぎないこと、長年被相続人と生活を共にし、入通院時の世話をしていたことを理由に持戻しの対象としませんでした。
これに対し、持戻しの対象としたものに、東京高裁平成17年10月27日決定(家裁月報58巻5号94頁)があります。
この事案は、遺産総額が1億0134円であり、相続人の1人が受領した保険金額が1億0129円でした。
裁判所は、遺産総額に匹敵する巨額の利益を得ていること、受取人の変更がされたとき、同居しておらず、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託するといった明確な意図もないこと、他の相続人らは保険金額1000万円の保険金を受領したのみであることなどから、持戻しの対象としました。
さらに、持戻しの対象としたものに、名古屋高裁平成18年3月27日決定(家裁月報58巻10号66頁)があります。
この事案は、相続開始時の遺産総額が8721万3883円であり、受け取った死亡保険金額は5154万0864円(相続開始時約61%、遺産分割時77%)となっていました。
裁判所は、遺産総額に対する割合や保険受領した妻との婚姻期間が3年5ヵ月程度だったことを理由に、持戻しの対象としました。
死亡退職金・遺族給付金
死亡退職金と遺族給付金は、法律上は相続財産ではなく、遺族が原始的に取得するものと解されています。
税法上は、被相続人の死亡によって、相続人その他の者が、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合には、その退職金等は相続または遺贈によって取得したものとみなされて相続税の課税対象となります(相続税法第3条1項2号)。
香典・葬儀費用
香典は、喪主に対する贈与と解されており、相続財産ではないとされています。
また、葬儀費用は、喪主が負担すべきであり、喪主は、葬儀費用を支出したとしても、相続財産に対して請求することはできないとされています。
税法上は、課税価格の計算上、取得財産からの控除が認められています(相続税法第13条1項2号)。
この場合に認められる葬儀費用は、葬式およびその前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるものです(相続税基本通達13-4、13-5参照)。
債権・債務
債権・債務は、相続財産を構成し、相続人に承継されます。
債権については、最高裁昭和29年4月8日判決(民法百選Ⅲ65)は、「相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。」と判示しています。
したがって、遺産分割の対象とはならず、相続開始によって、当然に相続人にその相続分に応じて承継されることになります。
可分債務も同様に、相続開始によって法定相続分に従って当然に分割承継されます(大審院昭和5年12月4日決定、民集9巻1118頁)。
共同相続人の1人が、相続財産中の可分債権について、その相続分を超えて債権を行使した場合には、他の相続人の財産に対する侵害となるから、侵害を受けて相続人は、侵害した相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償または不当利得の返還を求めることができるとされています(最高裁平成16年4月20日判決・判例時報1859号61頁)。
連帯債務者は、各自連帯して、債務の全部について債務を負いますが、連帯債務者の1人が死亡して相続が開始した場合には、その相続人らは、被相続人の債務が分割されたものを承継し、各自全部ではなく、その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となるとされています(最高裁昭和34年6月19日判決・民法百選Ⅲ63)。
相続税の計算において債務控除できるのは、次の場合です(相続税法第13条1項、14条1項)。
①相続人または包括受遺者が承継した債務であること
②被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
③確実と認められるものであること
④葬式費用
葬式費用については、次のものが葬式費用として控除できるとされています。
①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③①又は②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
葬式費用が債務控除の対象となるかどうかについては、相続税基本通達13および14において詳細に定められています。
金銭
金銭も当然相続財産ですが、当然に分割されるか、遺産分割が必要か、という問題があります。
金銭については、当然分割の対象とならず、遺産分割の対象とされています。
最高裁平成4年4月10日判決(民法百選Ⅲ63)は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない」としています。
預金債権
預金債権については、従前、可分債権であり、相続開始により当然に分割され、各相続人が相続分に応じて権利を承継することとされており、例外的に、相続人全員の合意がある場合に限り、遺産分割の対象となる、とされていました。
しかし、預金債権については、最大判平成28年12月19日が、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」と判示したことにより、遺産分割の対象となることが明らかにされました。
この結果、遺産分割がなされるまでの間、被相続人の医療費などの債務を被相続人の預金から引き出して支払うには、共同相続人全員の合意が必要となり、不都合が生じる結果となってしまいます。
そこで、2018年改正相続法では、預貯金債権についての仮払仮処分制度や仮払制度に関する規律を定めました。
ところで、被相続人名義の預金口座について、過去の取引履歴の開示を求めることができるかどうかについて、最高裁平成21年1月22日判決(民集63巻1号228頁)は、共同相続人の1人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる、としています。
賃料債権
相続財産に賃貸不動産がある場合には、不動産は遺産分割までの間、共同相続人の共有になります。
遺産分割までの間に賃料収入が発生しますが、その賃料については、相続財産には含まれず、各共同相続人がその相続分において分割単独債権として確定的に取得するとされています。
最高裁平成17年9月8日判決(民法百選Ⅲ64)は、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と判示しています。
したがって、相続財産に賃貸不動産がある場合には、相続税の対象ではなく、各共同相続人の所得税の対象となります。
そして、同判決は、「遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである」としています。
株式・投資信託受益権・国債
相続財産に株式会社の株式がある場合には、「株式は、株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し、株主は、株主たる地位に基づいて、剰余金の配当を受ける権利(会社法105条1項1号)、残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権と、株主総会における議決権(同項3項)などのいわゆる共益権とを有するのであって……、このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば、共同相続された株式は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである」(最高裁昭和45年1月22日判決・民集24巻1号1頁)とされており、遺産分割の対象となります。
同じように、投資信託受益権や国債についても、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象とされています(最高裁平成26年2月25日判決・民法百選Ⅲ66)。
株式については、相続開始によって、共同相続人の準共有となります。
この場合、会社法第106条は、「株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。」とされています。
そして、権利行使については、特段の事情のない限り、共有株主が持分の価格に従い、その過半数で決定するとされています(最高裁平成9年9月1日判決・判例時報1599号139頁)。
この場合、過半数を有する共有株主が勝手に決定してよい、というわけではありません。
過去の裁判例では、会社法106条に基づく共有株式の権利行使者の指定が、共同相続人間で協議がされていないものとして効力がないか、あるいは権利の濫用であって、許されないものとされた事例があります(大阪高裁平成20年11月28日判決、判例時報2037号137頁)。
裁判所は、「準共有が暫定的状態であることにかんがみ、またその間における議決権行使の性質上、共同相続人間で事前に議案内容の重要度に応じしかるべき協議をすることが必要であって、この協議を全く行わずに権利行使者を指定するなど、共同相続人が権利行使の手続の過程でその権利を濫用した場合には、当該権利行使者の指定ないし議決権の行使は権利の濫用として許されない」としました。
即死による損害賠償請求権
交通事故で被相続人が死亡したときなど、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被相続人の相続財産であるのか、相続人の固有の債権であるのか、が問題になりますが、判例では、即死の場合にも被害者が加害者に対する損害賠償請求権を取得し、その損害賠償請求権が死亡により相続される、とされていますので、相続財産と解されています。
税法上は、相続税関係の個別通達昭和57年5月17日付直資2-178で、以下のように定められています。
Ⅰ.被害者の生命侵害に基づく損害賠償金
交通事故等の不法行為による生命侵害があった場合において、その生命侵害に基づく損害賠償請求権は遺族およびその被害者(被相続人)自身について生じると解されていますが、相続税法上は、これらを区別することなくすべて遺族固有の請求権に基づくものとして相続税の課税価格に算入しないことにします。
Ⅱ.被害者の財産的損害に対する損害賠償金
被害者の財産的損害に対する損害賠償金については、通常の金銭債権と同様にその損害賠償請求権が相続されますから、相続税の課税対象にします。
債務の相続について
保証債務
通常の保証債務や連帯保証債務については、相続の対象となります。
限度額および期限の定めのない継続的信用保証債務については、特段の事情のない限り、保証人の死後に生じた債務について相続人は保証債務を負担しないとされています(最高裁昭和37年11月9日判決、民集16巻11号2270頁)。
なお、平成17年4月1日以降に締結された貸金等根保証契約で、個人が保証人になっているものは、限度額の定めがない場合または契約が書面でされていない場合は、無効です(民法第465条の2)。
身元保証契約における保証債務については、相続発生時に既に生じていた損害に限り保証債務を相続し、相続発生後に生じた損害については保証責任を負わない、とした裁判例があります(大審院昭和18年9月10日判決)。
個人的な信頼関係に基づくことが理由です。
ただし、身元保証人の推定相続人が当該労働者の雇い入れを使用者に懇請していた場合に、当該推定相続人が身元保証人を相続した場合には、身元保証人の地位が相続人に承継される、とした裁判例もあります(大審院昭和12年12月20日判決)。
賃貸借契約における保証人の地位は、相続人に承継される、とされています(大審院昭和9年1月30日判決)。
相続税の計算における債務控除において、保証債務および連帯債務は、次のように取り扱われます(相続税基本通達14-3)。
①保証債務については、控除しないこと。
ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。
②連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者(「弁済不能者」という。)があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除すること
納税義務
相続があったときは、相続人は、被相続人が有していた納税義務を承継します(国税通則法第5条1項)。
相続人が複数いる場合は、各相続人がその相続分に応じて按分計算した額を承継することになります(同条2項)。
ただし、所得税の青色申告の承認申請や減価償却方法の届出などの各種届出の効力は承継しません(最高裁昭和62年10月30日判決、判例時報1262号91頁)。
したがって、相続人が事業を承継する場合は、改めて青色申告の承認申請等の届出をする必要があります(所得税法基本通達144-1)。
消費税の簡易課税の届出書等の各種届出も同様です。
相続人のうちに相続によって得た財産の価額が承継した納税額を超える者があるときは、その相続人は、その超える価額を限度として、他の相続人が承継する納税額を納付する義務を負担します(同条3項)。
相続税の申告において、公租公課は債務控除の対象になります(相続税法第13条2項1号)が、相続人の責めに帰すべき事由により納付・徴収されるべき延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税等は債務控除の対象になりません(相続税法施行令第3条)。
被相続人の所得税等にかかる過納金の還付請求権は、相続財産を構成します(最高裁平成22年10月15被判決・民集64巻7号1764頁)。
契約上の地位
契約上の地位は、一身専属性のないものは、相続の対象となります。
したがって、賃貸借契約に基づく借主の地位も相続の対象となります。
この場合の賃料の支払義務については、不可分債務とされており(大審院大正11年11月24日判決、民集1巻670頁)、相続人全員が支払義務を負担します。
内縁の配偶者には相続権がありませんが、相続人がいない場合には、居住目的と賃借権については、内縁配偶者が承継することができます(借地借家法第36条)。
賃貸借契約の貸主の地位も相続の対象となります。
この場合の使用収益させる義務も不可分債務とされており、相続人全員がその義務を負担します(最高裁昭和45年5月22日判決、民集24巻5号415頁)。
土地建物の売買契約を締結したものの、引き渡し前に売主または買主について相続が開始したときの相続税における相続財産は次のように扱われます(平成3年1月11日付け国税庁資産税課税課情報第1号)
①売主に相続が開始した場合は、売買契約に基づく相続開始時における残代金請求権
②買主に相続が開始した場合は、土地建物の引渡請求権等とし、被相続人から承継した債務は相続開始時における残代金債務とする。
但し、土地建物を財産評価基本通達によって評価した価額による申告があったときは、それを認める。