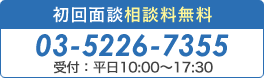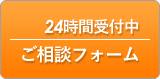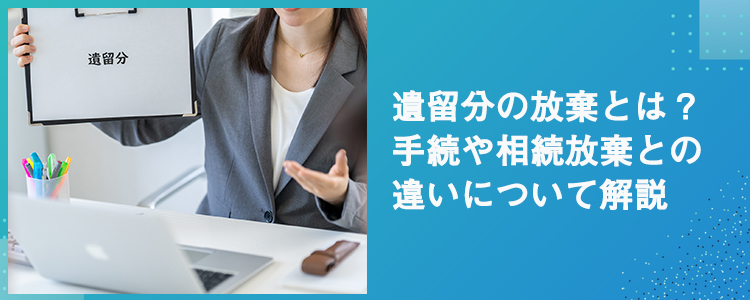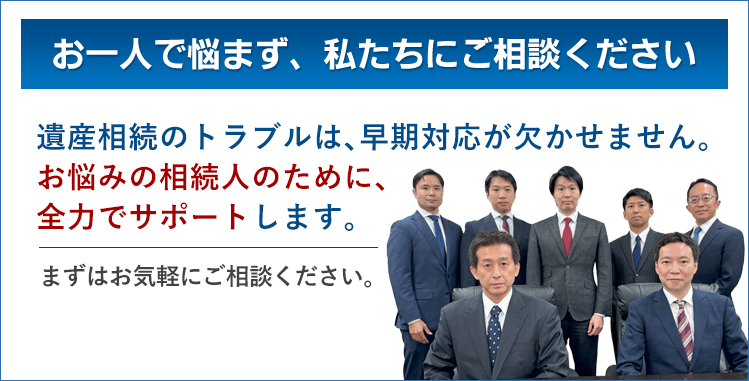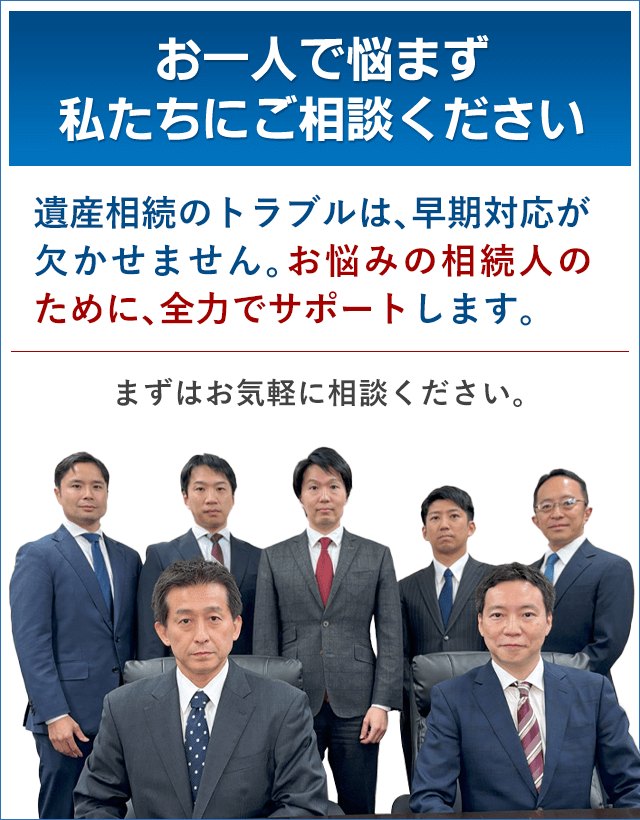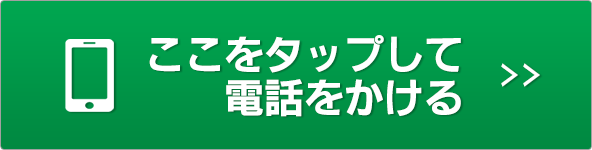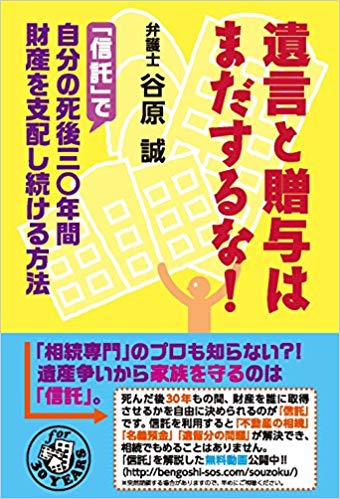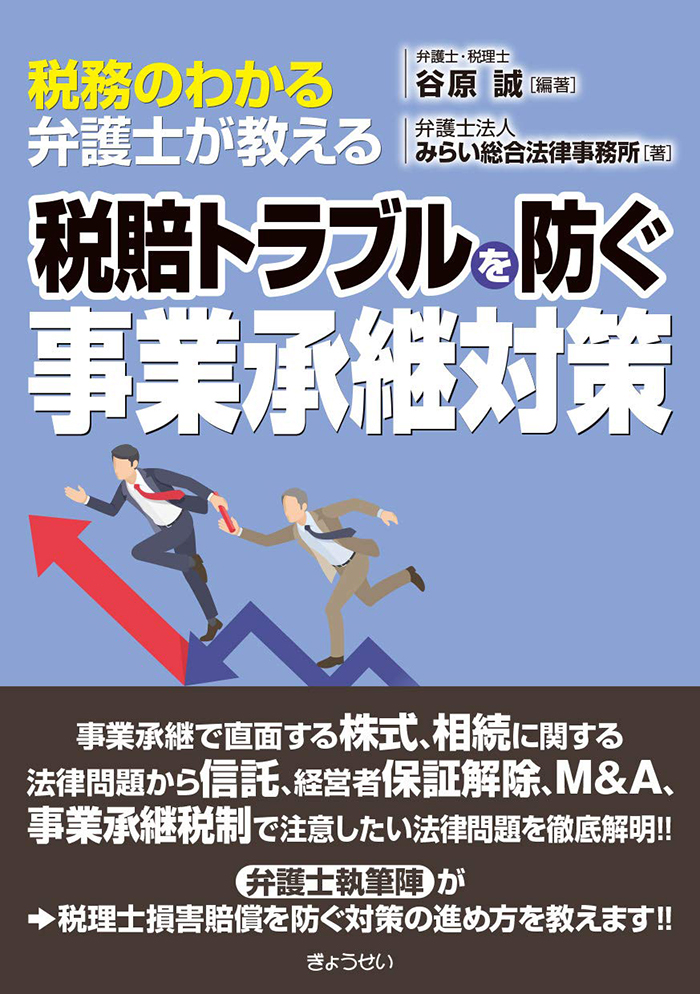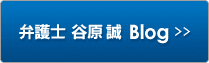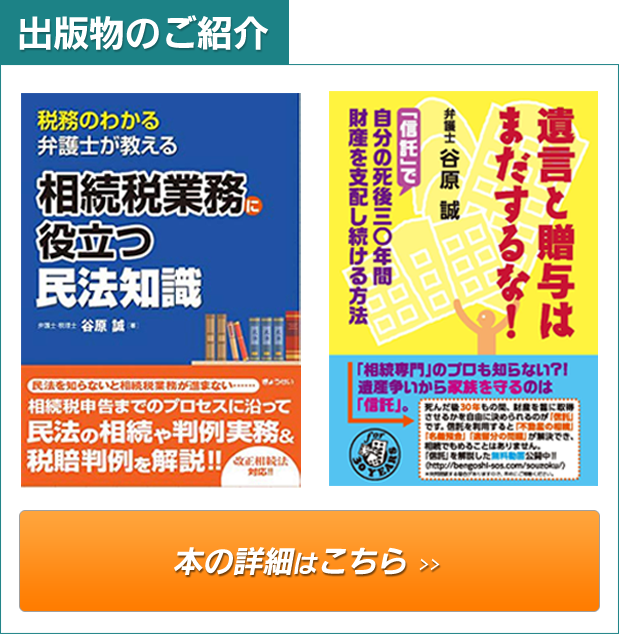遺留分の放棄とは?手続や相続放棄との違いについて解説
相続では法定相続人に一定の保障として遺留分が認められています。
しかし、何らかの理由で遺留分を放棄したいというケースもあるでしょう。
遺留分を放棄することは相続の放棄とは異なるものであり、手続きも異なります。
ここでは、遺留分の放棄と相続放棄との違いや、遺留分放棄するメリットや注意点、手続き方法など、遺留分の放棄について詳しく解説します。
目次
そもそも遺留分を放棄するとは
どういうことか?
亡くなった被相続人の遺産は、法定相続もしくは遺言書に従って相続が行われます。
相続が行われる中で、法定相続人には遺留分が認められていますが、遺留分とはどのようなものなのでしょうか。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に認められている最低限保障されている遺産の取得割合です。
被相続人が遺言書を残していれば、基本的には遺言書の内容に従った相続が行われますが、それでは相続人の生活が保障されない場合もありますし、相続人の協力によって被相続人の財産が維持増加ができた場合もあります。
そこで、法定相続人が遺留分に相当する財産を受け取られない場合、遺言書の内容に関係なく本来受け取ることができる遺留分を請求することが可能です。
この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
ただし、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者・直系卑属(子ども・孫)・直系尊属(父母・祖父母)です。
兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分は認められていません。
・遺留分とは、どのようなものか ?
遺留分の放棄とは
前述したように、法定相続人は遺留分によって最低限の保障された相続の権利があります。
しかし、この権利を法定相続人自らが手放すことも可能です。
このことを遺留分の放棄といいます。
相続が開始されてから遺留分を一度放棄すれば、遺留分を請求できなくなります。
ただし、遺留分放棄と相続放棄は異なるため、相続は行われます。
相続放棄との違い
遺留分放棄と相続放棄は混同されることがありますが、全く異なるものです。
相続放棄は、法定相続人が家庭裁判所に申述することによりはじめから相続人でないことになり、相続する権利を失う制度のことです。
相続放棄をすれば、法定相続人は相続する権利を失うため、被相続人の資産も負債もどちらも相続することが無くなります。
相続放棄の手続きは被相続人が亡くなった後に行うものであり、被相続人の生前には行えません。
一方で、遺留分放棄は遺留分を請求する権利を失うことのみを指します。
そのため、遺留分を放棄しても相続自体の権利は失われません。
遺言書で処分が指定されていない遺産の相続や、相続人として遺産分割協議に参加することもでき、負債も相続します。
また、遺留分放棄は相続放棄とは異なり、被相続人の生前でも死後でもどちらでも手続きをすることが可能です。
・相続の承認・限定承認・放棄とは?
遺留分の放棄はどのような
ケースで起こるのか
遺留分の放棄は、相続におけるトラブルを回避するために行われます。
遺留分放棄をすれば被相続人の思い通りの相続が行いやすくなり、死後に遺留分でトラブルになることが避けられます。
遺留分の放棄が行われる例を紹介します。
ケース①:事業継続への影響を避けるため
例えば、被相続人に配偶者と長男・次男長男がいて、長男に事業継続したいと考えているケースです。
相続によって長男が事業の全てを相続することに配偶者と次男が同意していても、事業を継続すれば配偶者と次男の遺留分を侵害するような場合があります。
こうした場合、被相続人の死後に配偶者や次男が遺留分損害額請求をすれば事業に支障をきたす可能性があるため、配偶者と次男に遺留分の放棄を求めることでトラブルを回避します。
ケース②:一定の法定相続人に相続を集中させたい
一定の法定相続人に相続を集中させたいと考える場合、遺留分放棄と遺言書を組み合わせることでトラブルを避けられます。
例えば、配偶者が他界して相続人が子供二人しかいない被相続人が、長男は自分で十分な資産を築いているため、長女に全ての資産を相続させたいと考える場合、長男に遺留分放棄を求めれば長女に相続を集中させられます。
また、長男は会社員として生計をたてられているものの、次男が障害を持っていて収入がない場合は、長男に遺留分放棄をしてもらうことで次男に財産を残せるので将来の不安が軽減されるでしょう。
遺留分を放棄するメリット
遺留分権利者が遺留分を放棄することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
被相続人や相続人、それぞれの立場からのメリットを解説します。
被相続人のメリット
遺留分放棄する最大のメリットは、相続開始後の遺留分に関するトラブルを回避できるという点です。
家族同士が自分の死後に相続で争うことを望まない方は多いでしょう。
被相続人の死後に遺留分でトラブルが起こることを避けたい場合、生前に遺留分の放棄を行い、遺書で相続の分配を指定していれば、希望通りの相続が行いやすくなります。
相続人のメリット
被相続人だけではなく、相続によって財産を取得した人も遺留分侵害額請求をされずに済むため、相続における不安やストレスが軽減されるというメリットがあります。
一方で、遺留分を放棄する相続人の立場からすれば、本来得られるはずの最低限の相続が得られないため、損だと感じるかもしれません。
しかし、被相続人が死亡する前に遺留分放棄をするのであれば、その代償として相続が開始する前にある程度の資産を譲り受けることができるケースもあります。
遺留分放棄における注意点
遺留分放棄をすれば相続におけるトラブルを回避しやすくなるというメリットがありますが、いくつか注意すべき点があります。
遺留分放棄の手続きへ進む前に、注意点について理解しておきましょう。
放棄すれば撤回は難しい
家庭裁判所から遺留分放棄許可がされた場合でも、遺留分放棄許可を取り消す手続があります。
しかし、何らの事情の変化もないのに取り消すことはできません。
例えば、遺留分放棄の原因となった事情に変化が生じた場合や、遺留分放棄が本人の意思に反して行われていた場合などは取り消しが認められる可能性があります。
遺留分を放棄すれば、放棄した相続人は本来受けられる最低限の相続が受けられなくなるため、慎重に放棄については検討すべきです。
負債は相続される
遺留分放棄をしても相続権は失われるわけではありません。
そのため、被相続人に負債がある場合、その返済義務は相続されます。
遺留分放棄によって財産は相続しないものの負債だけを引き継ぐことになるケースもあるため、あらかじめ負債の有無に関して把握した上で放棄手続きをすべきです。
生前に放棄する場合は手続きが複雑である
遺留分放棄は被相続人の死亡後だけではなく、生前に手続きをすることも可能です。
ただし、生前に放棄する場合は家庭裁判所へ申立てを行う必要があり、手続きが複雑になります。
家庭裁判所から許可を得るにはさまざまな書類を集めて提出し、一定の要件を満たさなければなりません。
遺留分放棄に関する要件や手続きに関しては、次項より解説していきます。
遺留分放棄の手続き
遺留分放棄をする場合、手続きが必要になります。
遺留分放棄の手続きは、手続きを行うタイミングによって方法が異なります。
被相続人の死後
被相続人の死後に遺留分を放棄する場合は、意思表示のみで遺留分放棄が成立します。
特別な手続きを行う必要はありません。
遺留分放棄をするという意思表示をすれば成立するため口頭のみでも遺留分を放棄できますが、書面に残しておくことを推奨します。
書面に残していれば法的な効力を持つため、後でトラブルになることを避けられます。
被相続人の生前
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合は、家庭裁判所へ許可を求めるための申し立てが必要です。
このことは法律で定められており、「遺留分放棄の許可の申し立て」と呼ばれています(民法第1049条)。
遺留分放棄の許可の申し立ては、以下の流れで進められていきます。
家庭裁判所へ必要書類を
提出する
遺留分放棄の許可の申し立ては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
裁判所の窓口もしくは郵送で必要書類を提出します。
申立てに必要な書類は、以下の通りです。
- ・家事審判申立書
- ・土地財産目録
- ・建物財産目録
- ・現金・預貯金・株式等財産目録
- ・被相続人の戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)
- ・申立人の戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)
家事審判申立書は裁判所のホームページより入手できます。
また、申立てには収入印紙や連絡用の郵便切手が必要です。
料金は管轄の裁判所ごとによって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
照会書提出依頼の送付・提出
必要書類を提出して2~4週間ほどで、裁判所より照会書が届きます。
照会書には複数の設問が記されているので、正確に回答を記載します。
設問内容は生前贈与の内容や放棄の意思など、遺留分放棄に関することで、難しい設問はありません。
提出期限が設けられているため、期限内に家庭裁判所へ返送しましょう。
審問
照会書を提出したものの、提出した内容だけでは不十分だと判断された場合は審問が行われます。
審問といっても面接のようなもので、照会書に記載されていた設問内容と同じようなことが聞かれます。
具体的な放棄理由などを分かりやすく説明すると良いでしょう。
審議
照会書の返送後に家庭裁判所にて遺留分を認めるかどうか審議が行われます。
審議の結果は1・2週間ほど家庭裁判所より「許可審判書」として郵送で送られてきます。審判の結果に対し不服がある場合でも、遺留分放棄の許可の申し立てでは不服申し立てを行うことはできません。
遺留分放棄の許可の申し立てに
おける判断基準
被相続人の生前に遺留分放棄をするには家庭裁判所の許可が必要ですが、申し立てをすれば全てのケースで許可がおりるというわけではありません。
裁判所では以下の3つの要素を満たしているかどうかを基準とし、放棄を認める必要性があるか否か判断しています。
本人の自由意志であること
遺留分の放棄が、放棄する本人の自由意志に基づくものである必要があります。
何らかの圧力を受けたり強制されたりした場合、嘘など詐欺行為を受けた場合などは、遺留分の放棄は認められません。
遺留分は相続人を保護するための制度なので、他者の干渉や妨害行為があった場合は遺留分放棄の申し立ては却下されます。
遺留分の放棄に合理的な理由がある
遺留分を放棄するには、放棄することに合理的な理由が必要です。
相続人にとって遺留分の放棄は大きな影響をもたらすことになるため、放棄する合理的な理由の有無は大きな判断基準になるといえます。
例えば、すでに被相続人より十分な贈与を受けているので他の相続人と公平にするために遺留分を放棄する場合や、事業継承のために遺留分の放棄が必要な場合などが該当します。
遺留分の放棄に見合った代償がある
遺留分を放棄すれば相続人は最低限の相続の保障が失われるため、放棄を認めるには遺留分に見合った代償があるのかという点も判断材料のひとつになります。
例えば、放棄する遺留分が1,000万円ならば、1,000万円と同じくらいの生前贈与を受けてれば、放棄に見合った代償と判断されるでしょう。
ただし、遺留分より少ない財産を代償として受け取っていても、財産の提供時期や事情によっては不当とは判断されず、放棄が認められることもあります。
遺留分放棄をする際のポイント
遺留分放棄によって相続トラブルを予防できる可能性は高まりますが、遺留分放棄をしてもらうためには相続人に合意してもらわなければなりません。
遺留分放棄をしてもらうためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
負債を残さないようにする
借金などの負債は遺留分放棄をしても引き継がれるため、負債があれば遺留分放棄を受け入れてくれない可能性が高まります。
なぜならば、遺留分も受け取れずに負債だけ引き継ぐことになれば、遺留分放棄をした相続人にはデメリットしかないからです。
円満に遺留分放棄を進めるためにも、負債はできる限り返済しておきましょう。
生前贈与を公平に行っておく
遺留分放棄を受け入れてもらいやすくするためには、相続が公平に行われることを考慮する必要があります。
相続を公平にするためには、遺留分に見合った生前贈与が必要です。
生前贈与で遺留分に見合った財産を受け取ることができれば、相続人も納得して遺留分放棄を受け入れると考えられます。
まとめ
遺留分放棄は相続争いを避けるための方法の一種ですが、遺言書を作成している場合に効果が発揮されます。
遺留分請求が行われれば遺言書の意味がなくなってしまうケースもあるため、遺言書と遺留分放棄は一緒に進めることが大切です。
弁護士に相談すれば、遺言書や遺留分放棄の申立書の作成だけではなく、スムーズに手続きを進める上でのアドバイスやサポートも得られます。
遺留分請求に関する疑問や不安は、相続問題に強い弁護士にご相談ください。
・遺留分を弁護士に相談する7つの
メリットと2つの注意点
遺産相続の遺留分は一人で悩まず、まずは気軽にご連絡いただければと思います。