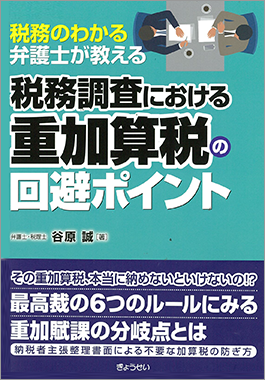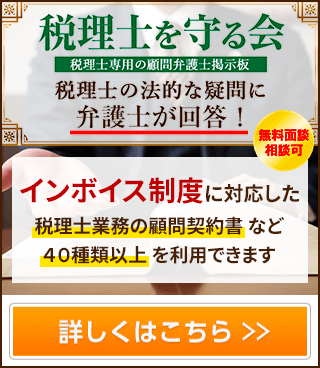ここでは、税務調査における事実の立証責任を取り上げます。
立証責任は、訴訟において、事実があるかどうか認定できない、という場合に、いずれか一方の当事者が負う不利益又は負担のことです。
最高裁判決は、所得税事案に関し、「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」(最高裁昭和38年3月3日判決、月報9巻5号668頁)としており、課税要件事実の主張立証責任は国にあるとしています。
したがって、税務調査において、課税要件事実を課税庁が立証できなければ、課税できない、ということになります。
下級審判例でも、一貫して、課税要件事実は、課税庁側にある、とされています。
●「本件算定方法が租税特別措置法66条の4第2項第2号ロ所定の再販売価格基準法に準ずる方法と同等の方法に当たることは、課税根拠事実ないし租税債権発生の要件事実に該当するから、上記事実については、処分行政庁において主張立証責任を負うものというべきである」(東京高裁平成20年10月30日判決)
●「本件においては、特定外国子会社等に当たるA社が措置法40条の4代4項所定の適用除外要件のうちの実体基準及び管理支配基準を満たすか否かが争点となっているところ、課税庁の属する被告側がA社が上記の各適用除外要件を満たさないことを主張立証する必要がある」(東京地裁平成24年10月11日判決)
●「国外に所在する子会社等の実体の把握についても、もともと、税金訴訟では、納税者側の事情が主張立証の対象となることが多い(国の事情や純然たる第三者の事情が主張立証となることは、通常は、想定されない)のであるから、主張立証責任を決めるに当たって、証拠への近さは、あまり重視すべきではないと考えられる」(東京高裁平成25年5月29日判決)
これに対し、必要経費などについては、納税者の領域内にあり、また、証拠を保全しておくことはそれほど困難ではないことが多いので、その立証は容易なことが多いと思われます。したがって、国側において、経費の不存在について一定の立証をした場合には、納税者が立証可能なはずなのに、合理的な立証ができないときは、国の立証が成功した、と判断される場合もありえます。
したがって、課税要件事実の立証責任が国にあるとしても、納税者としても、積極的に立証活動を展開していくことが必要です。
裁判例においても、以下のようなものがあります。
●「必要経費について、控訴人が行政庁の認定額をこえる多額を主張しながら、具体的にその内容を指摘せず、したがって、行政庁としてその存否・数額についての検証の手段を有しないときは、経験則に徴し相当と認められる範囲でこれを補充しえないかぎり、これを架空のもの(不存在)として取り扱うべきものと考える」(広島高裁岡山支部昭和42年4月26日判決行集18巻4号614頁)
●「被告が右の調査に基づく一応の立証を尽くした以上、被告の認定しえた額を超える多額を主張する原告が具体的にその支払額、相手方等を明らかにしえない限り、本件各土地の売買により発生した譲渡所得が原告に帰属するものと認められてもやむを得ないというべきである」(岡山地裁昭和44年7月10日判決、判例時報590号29頁)
また、一般経費については国に立証責任を課すものの、特別経費については、納税者に立証責任がある、とする裁判例があります。
(利息について)
「一般に必要経費の点も含め課税所得の存在については課税庁に立証責任があると解されるが、必要経費の存在を主張、立証することが納税者にとって有利かつ容易であることに鑑み、通常の経費についてはともかくとして、利息のような特別の経費については、その不存在につき事実上の推定が働くものというべく、その存在を主張する納税者は右推定を破る程度の立証を要するものと解するのが公平である。」(大阪高裁昭和46年12月21日判決、税務訴訟資料63号1233頁)
(訴訟費用について)
「所得の存在およびその金額について課税庁が立証責任を負うことはいうまでもないから、必要経費についても課税庁に立証責任があると解されるが、必要経費の存在を主張、立証することは納税者にとって有利かつ容易であるところからすると、公平の観念に照らし、通常の経費についてはともかく、訴訟費用のような特別の経費、すなわち、事実上不存在の推定が働くような特別の経費については、その存在を主張する納税者が石推定を破る程度の立証を要するものと解するのが相当である」(神戸地裁昭和53年9月22日判決、訴訟月報25巻2号501頁)
貸倒損失についても、「貸倒損失は、通常の事業活動によって、必然的に発生する必要経費とは異なり、事業者が取引の相手方の資産状況について十分に注意を払う等合理的な経済活動を遂行している限り、必然的に発生するものではなく、取引の相手方の破産等の特別の事情がない限り生ずることのない、いわば特別の経費というべき性質のものである上、貸倒損失の不存在という消極的事実の立証には相当の困難を伴うものである反面、被課税者においては、貸倒損失の内容を熟知し、これに関する証拠も被課税者が保持しているのが一般であるから、被課税者において貸倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等について具体的に特定して主張し、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当である。」(仙台地裁平成6年8月29日判決、訟月41巻12号3093頁、仙台高裁平成8年4月12日判決、税務訴訟資料216号44頁)とされています。
しかし、この貸倒損失に関する裁判例の判断には疑問です。
法人税基本通達9-6-1は、貸倒損失の要件として、「(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」としていますが、金融機関は別として、法人が通常の商取引をするに際し、相手方の決算書等の交付を受けることはほとんどありません。また、取引の相手方が資産超過か債務超過かを知りうる手段は少ないでしょう。したがって、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続」していることについて、立証は困難と言わざるをえません。反対に、課税庁においては債務者に対して質問検査を行うことによって債務者が債務超過であるかどうかを立証するのは容易であるといえるでしょう。
また、同通達9-6-2は、「法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。」としていますが、「債務者の資産状況、支払能力」などは、課税庁の方が調査を容易にでき、かつ、立証が容易であるように思います。反面、納税者においては、債務者の資産状況や支払能力などを調査し、立証するのは困難な場合が多いように思われます。
したがって、貸倒損失について全て納税者が立証責任を負担するというのは妥当ではなく、貸倒の理由に応じて適切に立証責任を分配していくのが妥当だと考えます。