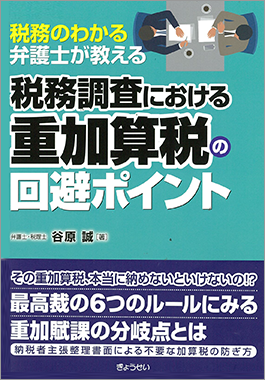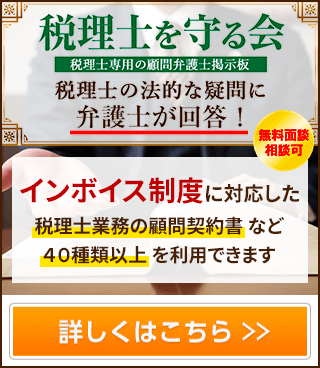東京地裁平成30年2月19日判決(TAINS Z999-0172)です。
税理士敗訴(損害賠償が認められた)
(事案)
被相続人A
相続人X、B、C、D、E
●Aは遺言により、全財産をXに相続させる旨意思表示をした。
●相続財産の中には、小規模宅地等の特例対象不動産が含まれていた。
●相続開始後B、Cから遺留分減殺請求の意思表示がされた。
●税理士は、X、D、Eの税務代理を受任したが、B、Cからは受任していない。
●税理士は、未分割として法定相続分に従った相続税申告を行い、同時に「申告期限3年以内の分割見込書」を提出して後日の更正請求を可能にする手続きを行った。
●全員分の相続税を相続財産の中から支出した。
●依頼者Xは、Xが支出したB、C分の相続税額その他の損害を被ったとして損害賠償請求をした。
(判決)
●本件の場合、税理士は、
(1)小規模宅地等の特例を適用することなく法定相続分に従った共同相続として申告を行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することにより、後日の更正請求を可能にしておく、
(2)遺留分減殺請求を考慮することなく遺言により全財産を相続したものとして申告し、小規模宅地等の特例を適用した上で、遺留分減殺が解決した後に更正請求をする、のいずれかの方法を選択することになるものと解される
●上記(1)の方法を選択し、上記両名分の相続税を相続財産から支出した場合、遺留分減殺の解決が長期化すればその間は本来原告が負担すべき税額を超えた支出状態が継続することになる可能性がある上、訴外B及び訴外Cから更正請求についての協力を得られないなどの事態も想定されたと考えられる。上記事実関係の下では、(1)の方法は(2)の方法と比較してリスクが高かったというべきであり、これを採用するのであれば、当該リスクの存在について十分に説明した上で原告の同意を得て行う必要があった
⇒善管注意義務違反を認めた。
●税理士に対して支払った報酬の返還請求もなされたが、以下の理由により、返還義務はないとした。
●業務の性質上、既履行部分と未履行部分を量的に区別するのは困難であることに加え、本件損害が賠償されることにより、税理士が適切な業務を実施した場合と同様の利益状態が実現することからすれば、既払報酬の全部又は一部の返還義務を負うことはない
==================
以上です。
遺言がある場合には、法律上、相続開始と同時に遺言書の効力を生じます。
しかし、遺言によらない遺産分割をすることも可能とされており、その場合の各人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容によることとなります。
(国税庁Q&A、No.4176?遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税)
したがって、上記(1)(2)ともに取り得る手段とはなるのですが、遺留分減殺請求がされている以上は、すでに紛争状態となっていて、後日遺留分権利者からの協力が期待できない状態にあります。
したがって、税理士としては、遺言に基づく相続税申告をした上で、後日、更正の請求をする、という方法を選択すべき、あるいは助言をすべきであった、とされたものです。
なお、助言をした上でも、依頼者が(1)を選択する場合があります。
この場合には、助言したことを証拠化しておく必要があることはもちろんです。
参考記事:税理士の相続税のミスによる損害賠償責任
・弁護士による税理士損害賠償SOS
弁護士法人みらい総合法律事務所では、税理士損害賠償のご相談を受け付けています。