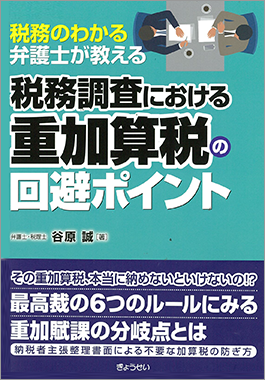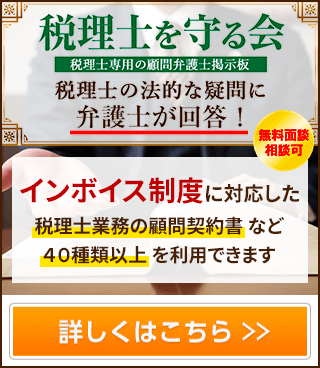目次
損害賠償請求を受けるケース
税理士がミスや間違いをして損害賠償請求を受けるケースはどのような端緒から始まるかについては、主に
(1)税理士が自分で気づくケース、
(2)依頼者から指摘されるケース、
(3)税務署から指摘されるケース、
の3つがある。
いずれにしても、慌ててミスを認めて依頼者に損害賠償金を支払うことは避けることが望ましい。当事務所の経験上、税理士としては損害賠償責任があると認識している場合でも、弁護士から見ると、損害賠償責任を争いうると判断できるケースがあるためだ。
したがって、損害賠償請求を受けた時は、冷静に、正しく対処する必要がある。
事実の確認と整理
税理士がミスや間違いをして損害賠償請求を受けたときに、まず行うことは、事実の確認である。事実と評価を明確に分け、「何が起こったか」という事実のみを時系列にするのである。そうすると、客観的に事案を見ることが可能になる。
また、後日、弁護士や保険会社に事案の内容を相談する際も、事実と評価が混在していると理解を得にくい。したがって、できる限り客観的に事実のみを時間や場所、登場人物などとともに時系列でのメモを作成することになる。
証拠の収集
時系列メモを作成したら、次は、証拠の収集である。後日裁判になった時は、事実関係は証拠によって判断される。過去の裁判例では、税理士が「説明した」と主張したにもかかわらず、裁判所が説明していない、と認定し、税理士が敗訴したものがあることからもわかるとおり、証明できない事実は裁判所では認定されないことがあることを認識しなければならない。
そこで、時系列メモを作成したら、その事実を証明する証拠を収集し、事実と証拠とを紐付けておくことが重要である。もし、証拠が依頼者の元にあるならば、できる早い段階で依頼者から証拠を得ておくことである。依頼者との関係が悪化したり、依頼者に弁護士が代理人として就任した後は、証拠を手に入れるのが困難になるからである。
また、担当したのが職員である場合には、その職員に事実関係のメモを作成させ、署名捺印を得ておくことも検討してよい。後日裁判になった場合には、当該職員が証人となるが、職員が退職等した場合には、証人として出廷してもらえなくなる可能性もあるためである。
法律通達、裁判例の検討
事実関係を整理し、証拠を収集したら、次に行うべきは、法律や通達、国税庁のQ&A、裁決例、裁判例等の検討である。今回、どの法律に違反したかどうかが問題となっているのか、その法律要件は何か、を正確に把握しておく必要がある。そして、過去に争われた事例において、税理士にどの程度の注意義務が課されているか、などを調査し、当該事案に当てはまるかどうか、検討することが必要となる。
この点は、後日、弁護士に相談する際の説明資料としても行っておくことが望ましい。
更正の請求、錯誤の主張、事業年度の変更
以上の検討により、税理士の注意義務違反が認められ、損害賠償責任が発生することが明らかになったら、依頼者の損害をできる限り少なくすることを検討することになる。
場合によっては更正の請求、錯誤無効の主張、事業年度の変更(消費税の場合)、課税期間の短縮(消費税の場合)などにより、依頼者に発生する損害をなくし、あるいは減らすことが可能になる可能性がある。
弁護士への相談
税理士が損害賠償責任を負担するかどうかについては、法律問題である。税理士は、税法の専門ではあるが、債務不履行や不法行為を規定する民法の専門家ではない。そして、損害賠償義務が成立するかどうかは、事実認定、法律の解釈適用という法律の専門的知識がなければ判断することができない。
したがって、自らの損害賠償責任が問題となったときは、法律専門家である弁護士に相談することが望ましい。その際には、すでに作成した時系列表、証拠との対比表などともに、依頼者との契約書を忘れずに持参することである。また、弁護士は税法に精通しているとは限らないので、当該事案において問題となる税法・通達・調査した判例等を持参し、弁護士の理解を得やすくした上で相談することが望ましい。
弁護士が税理士損害賠償の事案を扱うためには、
(1)税法の知識
(2)税理士の業務プロセスの知識
(3)過去の税理士損害賠償の裁判例の知識
が必要である。
当事務所が多数の税理士損害賠償事件を扱う中で、弁護士によってかなり攻撃防御の戦略が異なると感じているため、アクセス可能であれば、税理士損害賠償に関する知見を有する弁護士に相談することが望ましい。
税賠保険会社への通知
税理士職業賠償責任保険では、事故があったことを知ったときには、遅滞なく保険会社に報告をしなければならないと定められている。したがって、税賠保険に加入している税理士が事故があったことを知ったら、すぐに保険会社に報告しなければならない。
また、税賠保険の注意点としては、保険会社から支払い拒絶通知を受けたとしても、その判断が正しいかどうか、弁護士に相談することが望ましい。
保険会社に訴訟を起こして勝訴することもあるためである。
当事務所においても、地裁で勝訴した事例がある。
税賠保険会社が敗訴した裁判例を動画解説
税理士が損害賠償責任を負う注意義務の9類型
「税理士は、税務に関する専門家として、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする専門職であり(税理士法1条参照)、納税者から税務申告の代行等を委任されたときは、委任契約に基づく善管注意義務として、委任の趣旨に従い、専門家としての高度の注意をもって委任事務を処理する義務を負うものと解される。」(東京地裁平成22年12月8日判決、判例タイムズ1377号123頁)
そして、善管注意義務に違反し、依頼者に損害を生じさせた場合には、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになる。
税理士損害賠償責任に関する過去の裁判例を分析すると、問題となる注意義務の類型は9つに分類される。
①説明助言義務
②有利選択義務
③不適正処理是正義務
④前提事実の確認義務
⑤積極調査義務
⑥税法以外の法令調査義務
⑦租税立法遵守義務
⑧正しく事実認定をする義務
⑨第三者に対する義務
以下では、各注意義務が争われた裁判例を紹介するとともに、各注意義務毎に損害賠償責任を回避するためのポイントを検討する。
注意義務の類型別の裁判例とポイント
①説明助言義務
税理士は、依頼者に対して関連税法及び実務に関して、有益な情報および不利益な情報を提供し、依頼者が適切に判断できるように説明及び助言をしなければならない。この説明助言義務が争点となる場合には、(1)そもそも説明助言義務を負うか、(2)説明助言義務があることを前提として、説明助言をしたか、(3)説明助言に誤りがあるか、が争いになる。
(1)の説明助言義務を負うかどうかが争われた裁判例として、東京地裁平成20年11月17判決(TAINS Z999-0135)がある。これは、顧問契約を締結している税理士が、消費税課税事業者選択届出書を提出すべきとの助言義務があるにもかかわらず助言しなかったことにより、消費税課税事業者選択届出書を提出せず、免税事業者となり、3357万0960円の還付不能消費税額が生じたという事案である。
この事案において、裁判所は、「被告としては、原告が本件制度の存在を知らないこと又は失念していることを認識した場合はもちろん、被告がそのことを容易に認識し得るような場合には、被告は原告に対し、本件制度の存在を説明する義務を負うと解するのが相当であり、また、原告が本件制度を実際に知っていたか否かにかかわらず、原告が本件届出書を提出して課税事業者となった方が課税上有利になる可能性があることを本件届出書提出期限までに認識し、又はそのことを容易に認識し得た場合も、被告は原告に対し、本件制度について注意を喚起する義務を負う」としたが、結論としては、税理士の説明助言義務を否定した。
本件のような紛争を回避する方法としては、消費税に関する各種届出の要否を判断する責任は依頼者が負う旨契約書に記載しておく方法がある。
次に、(2)の説明助言義務があるとして、説明助言をしたかどうかが争いとなった事案として、東京地裁平成24年1月30日判決(TAINS Z999-0131)がある。この事案は、税理士が相続税申告業務を受任したところ、相続財産から海外財産が脱漏していたものである。この訴訟において、税理士は、「国内・海外を問わず、亡太郎の所有するすべての財産が申告の対象となることを説明した上で、すべての相続財産に関する資料を被相続人に提供するよう指示した」と主張した。しかし、判決では、税理士は、原告らに対して、被相続人の海外財産に関する資料の提供を求めたり、海外資産の有無についての調査を求めたりしたことはなかったと認定された。
ポイントとしては、税理士が実際には説明助言をしたとしても、訴訟において、それを立証できなければ、損害賠償責任が認められてしまう可能性がある、ということである。税理士が説明助言した客観的資料がなく、上記裁判例のように、実際に相続税の申告において、海外財産が脱漏している場合に、証人尋問だけで説明助言の事実を立証するのはかなりハードルが高い。
したがって、できる限り説明助言をしたことを証拠化しておくことが肝要である。また、業務を受任する場合に、必要な説明を記載した説明書ひな形を交付し、それに基づいて説明し、「説明を受けて理解した」旨の書面に署名押印を得ておくことも有用である。
通達によらない処理をする場合の説明助言義務については、さいたま地裁平成15年1月16日判決(TAINS Z999-0087)がある。この事例は、相続税申告業務において、相続財産である土地の評価について、宅建主任者である依頼者が評価した時価で評価して相続税申告をし、後日税務調査により当該評価が否認され、修正申告をせざるを得なくなって、過少申告加算税、延滞税等が生じたことから、税理士の説明助言義務違反が争われた事例である。
裁判所は、否認の可能性を指摘し、かつ、評価が適正であることを裏付ける不動産鑑定士の鑑定書を用意するよう助言・指導すべきであるとして、税理士の説明助言義務違反を認めた。
②有利選択義務
複数の選択しうる税務処理の方法がある場合において、法令の許容する限度で依頼者に有利な方法を選択する義務である。
有利選択義務について述べた裁判例に、神戸地裁平成14年6月18日判決(TAINS Z999-0052)がある。これは、相続税申告業務を受任した税理士が、財産評価基本通達における私道の評価を誤り、不利な評価方法を選択した事案である。
この事案において、裁判所は、「委任契約上、税理士として、相続税のための財産評価にあたり、財産評価基本通達を含む法令に則り、依頼者のためにできるだけ有利な評価を採用するようにする注意義務があり、そのため必要な質問や調査を尽くすべき義務があるというべきである。」と判示した。
東京地裁平成7年11月27日判決(TAINS Z999-0019)は、相続税の財産評価を誤るとともに、配偶者に対する税額軽減を適用せずに相続税申告書を作成、提出した事例について、税理士は、「税務の専門家として、租税に関する法令、通達等に従い、適切に相続税の申告手続をすべき義務を負うことはもちろん、納税義務者たる」依頼者の「信頼にこたえるべく、相続財産について調査を尽くした上、相続財産を適切に各相続人に帰属させる内容の遺産分割案を作成、提示するなどして、」依頼者に「とってできる限り節税となりうるような措置を講ずべき義務をも負う」と判示している。
大阪地裁平成20年7月29日判決(TAINS Z999-0118)は、法人税の確定申告に際し、租税特別措置法68条の2第1項4号に基づく、法人税にかかる同族会社の留保金課税を非課税とする特例制度が適用できるのに、できないことを前提として処理した事例において、税理士が、時間的余裕がなかった、という主張をしたのに対し、裁判所は、「与えられた作業時間が限られていたとしても、そのことは、」税理士に「対する委任事項から本件特例制度の適用の可否につき検討することが除かれていた理由とはいえない。専門家である」税理士において、「時間が限られてできないというのであれば、そのことを述べるべきである」として、税理士の注意義務違反を認めたものがある。
税理士には、この有利選択義務があるものの、特別の事情によって、依頼者が不利な方を選択する場合がある。この場合、後日、依頼者から、この有利選択義務を理由として、損害賠償請求がされる可能性もあるので、依頼者の希望によって、不利な処理を選択したものである旨の証拠を残しておくことが肝要である。
具体的には、複数の税務処理の有利不利を説明し、依頼者が不利な税務処理を希望したことによって、当該処理を選択したこと、当該処理をした結果、依頼者に損害が発生するが、税理士に対する損害賠償請求権を放棄すること、を書面にし、署名押印を得るという方法である。
③不適正処理是正義務
税理士は、税理士業務を行うに当たって、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない(税理士法41条の3)。また、依頼者の指示や説明などに不適正があった場合も、これを是正する義務がある。
不適正処理是正義務が争われた裁判例として、東京地方裁判所平成24年12月27日判決(TAINS Z999-0141)がある。これは、依頼者の説明内容に誤りがあったにもかかわらず、その説明に依拠して処理をした結果、損害が生じた事案である。裁判所は、「税務の専門家としての観点から、委任者の説明内容を確認し、それらに不適切な点があって、これに依拠すると適切な税務申告がされないおそれがあるときには、不適切な点を指摘するなどして、これを是正した上で、税務代理業務等を行う義務を負うと解される。」と判示した。
前述の留保金課税が問題となった大阪地裁平成20年7月29日判決(TAINS Z999-0118)は、「依頼者の指示が不適切であれば、これを正し、それを適切なものに変更させるなど、依頼者の依頼の趣旨に従って依頼者の信頼に応えるようにしなければならない。」と判示している。
ポイントは、依頼者の説明には、誤解や記憶違い、意図的な嘘などの可能性があるため、依頼者の説明を鵜呑みにせず、資料と整合しているか、矛盾点はないか、常に注意することが肝要である。過去の裁判例の傾向からは、依頼者から預かっている書類に記載がある内容については、税理士として確認する義務があると解釈されやすい。
また、依頼者から不適正な処理を強要されるような場合は、勇気をもって顧問契約を解約することも検討するべきである。税理士の顧問契約は、民法上の委任契約と解釈されることが多い(最高裁昭和58年9月20日判決参照)が、委任契約については、いつでも解除をすることができる(民法第651条1項)。但し、相手方に不利な時期(税務申告期限直前など)に解除をする場合には、損害賠償請求をされる可能性があるので注意されたい(同条2項1号)。
参考記事:税理士損害賠償請求事例を弁護士解説(不正発見報告義務)
④前提事実の確認義務
税理士は、税務処理の前提となる事実について、資料を精査し、関係者に質問することにより前提事実を解明すべき注意義務がある。
前提事実の確認義務が争われた裁判例として、大阪高裁平成8年11月29日判決(TAINS Z999-0012)がある。これは、譲渡所得税の申告に際し、譲渡資産が過去に買換え特例の適用を受けていたにもかかわらず、買換え特例がないものとして処理した事案である。
この事案において、裁判所は、税理士が依頼者に対し、「以前に不動産を譲渡したことがあるか」と質問したのに対し、依頼者が「ない」と回答し、また、不動産の譲渡関係資料もないとの回答があったことから、税理士がさらに課税庁まで出向いてまで調査する義務はない、として税理士の損害賠償責任を否定した。
この裁判例では、上記の会話内容が認定されているが、依頼者が「質問されたことはない」と主張することによって税理士の立証が困難になる場合がある。ポイントは、税理士が必要な調査を行うことは当然であるが、訴訟において、調査したことを立証できるよう調査のプロセスと結果を証拠化しておくことが肝要である。
⑤積極調査義務
税理士は、税務処理をするにあたり、依頼者の説明や資料が不十分であるなどの場合には、依頼者に対して積極的に質問したり、資料提示を求め、調査する義務がある。
積極調査義務が争われた裁判例として、東京地裁平成21年10月26日判決(判例タイムズ1340号199頁)がある。これは、所得税確定申告業務において、不動産賃貸業をしている依頼者から提出された資料に礼金の収入等の漏れがあったにもかかわらず、積極的に調査をせずに確定申告書を作成した事案である。
裁判所は、「本件各確定申告書等の根拠となっている本件各資料の内容を精査すれば、礼金等の収入の有無や必要経費の内容や金額について疑問をもち、」依頼者に対して、「これらについて説明を求め、追加資料の提出を促すことは容易であった」と判示して、税理士の損害賠償責任を認めた。
ここでも、依頼者の説明や提出資料に漫然と依拠して業務を行うのではなく、資料の精査をすることが重要であるといえる。
東京地裁平成22年12月8日判決(TAINS Z999-0133)は、依頼者の作成した会計帳簿の勘定科目の適用誤りに気づかず、そのまま申告書を作成してしまった事例に関し、「税務申告の代行の依頼を受けた税理士は、委任者の作成した資料に基づき、委任者の指示に従って申告書等を作成する場合には、上記のような委任契約に基づく善管注意義務の一環として、税務の観点から委任者の作成した資料を確認し、その内容に不適切な点があり、これに依拠すると適切な税務申告がなされないおそれがあるときには、不適切な点を指摘するなどして、これを是正した上で申告を代行する義務を負うものと解される。」とした上で、依頼者の人材派遣の方法等の業務内容が大きく異なっていないにもかかわらず、控除対象仕入税額が著しく増加していることは一見して不自然であるにもかかわらず、十分な調査確認をしなかったとして、注意義務違反を認めた。
⑥税法以外の法令調査義務
税理士は税務の専門家として、税法を調査する義務があることは当然であるが、税務処理をする前提として、税法以外の法令の適用が必要となる場合があり、この場合に税理士は、税法以外の法令の調査義務を負う。
税理士の法令調査義務が争われた裁判例として、東京地裁平成26年2月13日判決(TAINS Z999-0145)がある。これは、相続税申告業務において、税理士が、相続人の1人の国籍について、関係者からアメリカと日本の二重国籍であると供述を得たことから、日本国籍を有するものとして、相続税の申告をしたところ、実は日本国籍を喪失していた、という事案である。
この事案において、裁判所は、「確かに、税理士は、税務に関する専門家であるから、一般的には租税に関する法令以外の法令について調査すべき義務を負うものではない」とした上で、相続税申告にあたっては、相続人が日本国籍を有しない制限納税義務者かどうか確認する必要があり、日本国籍を有するかどうかは、「国籍法」が規定していることから、税務の専門家としては、一般人であれば相続人が日本国籍を有しない制限納税義務者であるとの疑いを持つに足りる事実を認識した場合には、相続人が日本国籍を有するか否かについて確認すべき義務を負う旨判示した。
税理士が税法以外の法令調査義務を負う場合、どの程度の調査を行う義務があるのかについて争われた裁判例として、那覇地裁沖縄支部平成23年10月19日判決がある。これは、相続税申告業務において、税理士が、相続人が相続していない不動産について相続財産に含めたことにより過大な相続税の納税を余儀なくされた事案である。税理士が所有権の移転原因をどこまで調査すべきかについて判断された。
この事案において、裁判所は、「税理士は、税務の専門家であって、法律の専門家ではないから、ある財産を遺産に含めて相続税の課税対象として処理する場合に、所有権の移転原因を厳密に調査する義務があるとまではいえず、税務署が納税行為の適正を判断する際に先代名義の不動産の有無を考慮している現状にも照らせば、Yが本件土地に関する調査義務に違反したということはできない。」と判示し、税理士の損害賠償責任を否定した。
ポイントとしては、税理士は、税務処理の前提として税法以外の法令の適用がある場合には、その法令を調査確認すべき義務を負うが、法律の専門家のような厳密な法令調査義務を有するものではなく、税理士として尽くすべき調査を行っていれば、善管注意義務違反になるものでない、という点である。
⑦租税立法遵守義務
税理士は、租税立法の文言に直接的に反する行為をしてはならないことはもとより、租税立法の趣旨に反する行為をしてはならない義務を負う。また、仮に通達に反する助言をする場合には、通達に反する旨、及び後日依頼者に不利益が生ずる可能性があること、後日の税務調査において、処理の妥当税を立証できる証拠を収集しておくよう助言する義務がある。
租税立法遵守義務が争われた裁判例として、大阪高裁平成10年3月13日判決(判例時報1654号54頁)がある。これは、相続税申告業務において、依頼者から、財産評価基本通達に反する処理を求められ、それに従って評価して相続税の申告をした、という事案である。
裁判所は、「基本通達と異なる税務処理を指導助言したりする場合において、基本通達が国税庁長官が制定して税務職員に示達した税務処理を行うための基準であって法令ではないし、個々の具体的事案に妥当するかどうかの解釈を残すものであるから、確定申告をするに当たり形式上基本通達に反する税務処理をすることが直ちに許されないというものではないものの、税務行政が基本通達に基づいて行われている現実からすると、当該具体的事案について基本通達と異なる税務処理をして確定申告をすることによって、当初の見込に反して結局のところ更正処分や過少申告加算税の賦課決定を招くことも予想されることから、依頼者にその危険性を十分に理解させる義務があるというべきである。」と判示している。
これに対し、財産評価基本通達に則った処理が総則6項により否認された東京地裁平成10年11月26日判決(TAINS Z999-0047)がある。
裁判所は、「納税者間の課税の公平が著しく損なわれる上、富の再配分機能を通じて経済的平等を実現するという相続税法の立法趣旨から大きく逸脱することは明らかである」とした上で、「考案した本件相続税対策は、租税立法の趣旨を大きく逸脱しており、課税実務上到底認め難いものであること、右対策が考案されたころには、いわゆる節税商品については、形式的に通達に従っていても税務当局から否認される流れが出始めていたこと」などから、税理士は、「対策が税務当局から否認されるおそれがあることは十分に予見することが可能であったというべきであ」る、として、税理士の注意義務違反を認めた。
租税立法遵守義務におけるポイントは、以下のとおりである。
① 税理士は、法令及び法令の趣旨を遵守する義務を負う。
② 通達と異なる処理を行う場合には、依頼者に生ずる可能性のある不利益を精査し、依頼者に十分説明し、理解を得ておくこと、その証拠を残しておくこと、当該処理を正当化できる証拠を収集するよう助言する義務を負う。
⑧正しく事実認定をする義務
税理士が業務を行う場合には、事案に適用すべき各種税法に関する法令を解釈し、事実を認定し、法令に事実をあてはめることになる。そこで、事実を正しく認定しなければ誤った処理となり、依頼者に損害を与える可能性がある。したがって、税理士は、正しく事実認定をする義務がある。
事実認定義務が争われた事案に、前述の神戸地裁平成14年6月18日判決(TAINS Z999-0052)がある。相続税申告業務を受任した税理士が、財産評価基本通達における私道の評価を誤った事案であるが、この事案において、裁判所は、「必要な質問や調査を尽くすべき義務があるというべきである。」と判示した。その上で、税理士が現地調査をしたこと、現場の状況から不特定多数の者の利用がされていることを想定することは、著しく困難であること、税理士が、本件私道部分全体が車庫の専用通路と判断したとしても、その判断が不合理であるということはできないこと、などから、税理士の損害賠償責任を否定した。
正しい事実認定に努めることは当然であるが、事実認定が誤っていたからといって当然に税理士に損害賠償責任が発生するわけではない。事実の調査において、税理士としての善管注意義務を尽くした調査を行っていれば、損害賠償責任は否定される。そして、裁判では、(1)税理士がいかなる調査をしたか、(2)いかなる資料に基づいて検討したか、(3)どのように判断したか、が検討されるため、必要な調査をした上で、これらの資料を証拠として残しておくことが肝要である。
⑨第三者に対する義務
税理士が作成した税務書類は、依頼者により金融機関や大口債権者に提出され、それをもとに判断されて融資や取引等が行われることがある。しかし、税務書類に誤りがあったために、債権の回収が不可能になり、損害が生じた場合には、債権者は、損害の原因を作ったのが税理士であるとして、税理士に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をする場合がある。これが、税理士の第三者に対する義務である。
第三者に対する義務が争われた裁判例として、仙台高裁昭和63年2月26日判決がある。これは、税理士が作成した内容虚偽の確定申告書の写しの記載を真実と信じて、保証、担保の提供などをした者が、保証履行等により損害を被った事案である。
裁判所は、税理士は、依頼者が「これを利用して融資先を欺いて甲社の金融を得ることを知りながら、乙社の実情を粉飾し、このような虚偽の内容を記載した書類を作成したものであること、すなわち、」税理士「はこれにより乙社に対して融資をするものが損害を受けるかもしれないことを予見しながらあえてこのような虚偽の内容を記載した書類を作成したものであることが認められる。」として、税理士の損害賠償責任を認めた。
本件は、故意に内容虚偽の確定申告書を作成したものであるから、損害賠償責任が発生するのは当然であるが、故意に内容が真正でない税務書類を作成した場合には、税理士法第45条1項により懲戒処分の対象ともなる。
また、相当の注意を怠って内容が真正でない税務書類を作成した場合には、税理士法第45条2項により懲戒処分の対象ともなる点に留意したい。
税理士損害賠償請求を受けたら弁護士に相談
税理士は、税務の専門家として高度の注意義務を負っている。この点、冒頭に掲載した東京地裁平成22年12月8日判決(判例タイムズ1377号123頁)は、「税理士は、・・・・専門家としての高度の注意をもって委任事務を処理する義務を負うものと解される。」と判示している。
実際、過去の裁判例を見、また、筆者が扱った税理士に対する損害賠償請求訴訟における裁判官の印象では、裁判所は、税理士に対し、相当高度の注意義務を要求しているように感じる。
筆者は、これまで多くの税理士損害賠償に関する相談を受けてきたが、普段ならしないであろうミスを、ちょっとした不注意でしてしまった、という事例が多い。したがって、上記9つの注意義務を意識した上で、慎重を期して業務に取り組むことが肝要である。
税理士がミスをして損害賠償請求を受けた時は、訴訟前の内容証明郵便の段階から弁護士に相談することをおすすめする。
安易な事情説明書を依頼者に交付すると、後日、弁護士に依頼しての訴訟戦略に悪影響を及ぼすことがあるので、注意が必要である。
税理士損害賠償の問題は、税務の問題ではなく、損害賠償という法律問題であるという意識を持つことをおすすめする。
・弁護士による税理士損害賠償SOS
弁護士法人みらい総合法律事務所では、税理士損害賠償のご相談を受け付けています。