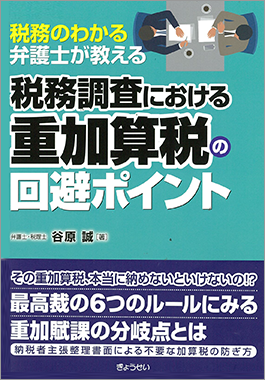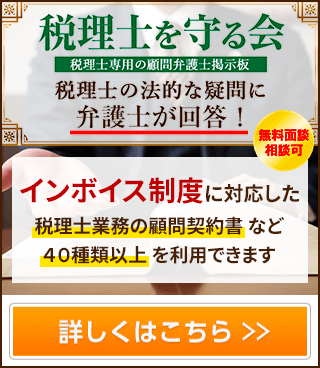目次
税務調査における録音についての論点
・税務調査で隠して録音してよいか。
・隠し録音は証拠になるか。
・税務調査で録音が税務職員に発覚して制止されても録音できるか。
・録音を制止しなかったら、どうなるか。
・録音の強行と税賠・懲戒処分
・制止されても録音が適法となる場合
税務調査で隠して録音してよいか。
まず、税務調査において、税務職員に無断で録音してよいか、ということですが、無断録音に、刑罰を適用する法律はありません。
したがって、税務調査過程を録音して、特に刑罰に処せられることはありません。
隠し録音は証拠になるか。
そうすると、無断録音が後日の民事裁判に証拠として採用されるか、という点です。
この点、大分地裁昭和46年11月8日判決は、対面での無断録音を違法収集証拠として排除しましたが、現在の裁判実務では、対面で無断で録音しただけではただちに証拠から排除されていません。
どのような場合に無断録音が違法となるかについて、東京高裁昭和52年7月15日判決(D1ーLaw.com 27650664)は、以下のように判示して、証拠能力を肯定しています。
========================
証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。
そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当つては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、
これを本件についてみるに、右録音は、酒席における石上らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。
=========================
では、どのような場合に録音テープが証拠から排除されるかですが、東京地裁令和3年5月12日は判決(D1-Law.com判例体系〔29064944〕では、次のとおり判示して、録音テープを証拠から排除しています。
=========================
本件録音テープの内容及び弁論の全趣旨によれば、本件録音テープは、本件調停の様子を調停委員会等の許可を得ることなく録音したものと認められる。そこで、本件録音テープの証拠能力について付言する。
家事調停の手続は、公開しないものとされている(家事事件手続法33条)。これは、家事調停とは、家庭に関する事件について、調停委員会が、当事者の言い分を聞き、紛争の実情に応じて当事者を説得し、その主張を互いに歩み寄らせて合意に導くことを目的とした手続であるところ、
その目的を達成するためには、同手続を非公開とし、個人や家庭の秘密等を保持するとともに、調停委員会も当事者も他人に気兼ねなく胸襟を開いて話合いができるようにすることが不可欠であることによるものと解される。
このような制度趣旨に鑑みれば、調停期日における発言を無断で録音し、又はその録音を他の手続等で利用することは、上記の趣旨を著しく損なうものであって、許されないというべきである。
したがって、本件録音テープを証拠として提出することは、訴訟法上の信義則に反して許されないというべきであり、その証拠能力を認めることはできないから、これを証拠から排除するのが相当である。
========================
また、対面ではない無断録音については、大阪地裁令和5年12月7日判決は、運送会社のトラック運転手が、職場の休憩室において、約4ヶ月間に20回程度、1回当たり3時間程度にわたり、他人に気づかれない一に録音機を設置して無断録音した事例において、録音を違法収集証拠として排除しています。
税務調査で録音が税務職員に発覚して制止されても録音できるか。
実際問題、税務調査において、納税者あるいは税理士が税務調査過程を録音しようとすると、録音を制止されることがほとんだと推測します。
では、税務職員は税務調査において、納税者あるいは税理士による税務調査過程の録音を制止する権限を有するのでしょうか。
この点、税務調査に関しては、
「質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」(最高裁昭和48年7月10日決定)とされ、税務調査をどのように行うかについては、税務職員の裁量を広く認めています。
したがって、税務調査について録音を許すかどうかも、一般的には税務職員の合理的な選択に委ねられていると考えられます。
録音を停止しなかったら、どうなるか
では、税理士が、税務職員から録音を制止したのに、停止しなかったら、どうなるでしょうか。
この場合、帳簿不提示として調査を打ち切られ、青色申告承認取消処分、仕入税額控除否認をされる可能性があります。
(青色申告承認取消処分)
最高裁平成17年3月10日判決(TAINS Z255-09954)
=======================
税務調査において、帳簿提示を拒否した事案で、青色申告承認取消処分をした。「法人税法126条1項は、青色申告の承認を受けた法人に対し、大蔵省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録すべきことはもとより、これらが行われていたとしても、さらに、税務職員が必要と判断したときにその帳簿書類を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に、帳簿書類を保存しなければならないこととしているというべきであり、法人が税務職員の同法153条の規定に基づく検査に適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかった場合は、同法126条1項の規定に違反し、同法127条1項1号に該当するものというべきである。
========================
(仕入税額控除否認)
最高裁平成16年12月16日判決(百選第6版89事件)
========================
消費税法30条7項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する帳簿又は請求書等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、同法62条(当該職員の質問検査権)に基づく税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、同法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たる
========================
録音の強行と税賠・懲戒処分
そして、税理士が税務調査において録音を強行した場合には、さらに問題が生じます。
税理士が、税務調査の拒否を助言して、仕入税額控除否認され、納税者が税理士に対して損害賠償を求め、それがみとめられた事例です。
千葉地裁令和3年12月24日判決です。
また、青色申告承認取消で税理士に対する損害賠償が認められた事例もあります。
東京地裁平成19年11月30日判決です。
調査拒否をして青色申告承認取消となった場合でも同じく税理士の損害賠償責任が認められる可能性が高いでしょう。
制止されても録音が適法となる場合
しかし、どのような場合でも税務調査において録音が認められないわけではありません。
税務調査に違法性が認められるような場合です。
京都地裁平成12年2月25日判決があります。
これは、国税調査官らに調査にあたり違法な行為があった事案です。
==========================
「調査に際して、第三者の立ち会いを求めたり、写真撮影等をしたことについても、同様の理由から、再度違法な調査がなされないようするため、第三者の立ち会いを要求し、調査の様子を撮影・録音することにやむを得ない面があると考えられるから、原告が前記のとおり調査に非協力的な対応をしたことを原告の責にのみ帰せしめることはできない。」
「課税庁は、本件処分をなすまでの全調査過程を通じて、帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上当然要求される程度の努力を尽くしたものと認めることはできない。」
==========================
以上の各論点を念頭に税務調査に対応するようにしましょう。