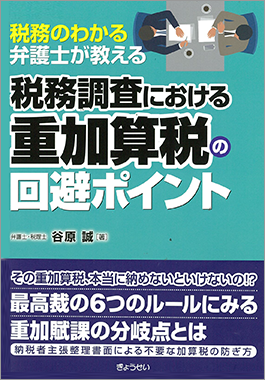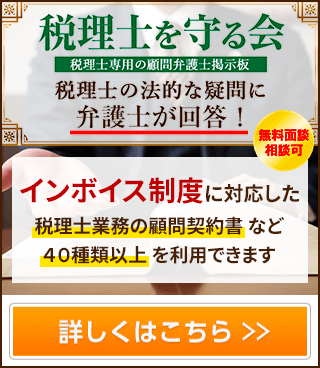目次
仙台地裁平成24年2月29日判決(TAINS Z262-11897)
【動画解説】従業員がリベートを受け取っていた場合の重加算税の論点
事案
原告Xは、旅館業及び飲食業などを目的とし、旅館Aを経営する内国法人です。社員乙は、平成8年10月に原告Xに入社した後、和食、洋食及び中華料理部門の総責任者である調理部調理課長から調理部副支配人、総料理長兼調理部支配人となり、副総支配人に就任しました。社員丙は、調理部和食調理課長から、最終的に総料理長に就任しました。
社員乙は、食材納入時に仕入先からリベートを受け取り、丙と分けていました。
そこで、課税庁が、本件リベートを原告Xの収入であると認定した上で、重加算税の賦課決定処分をしました。
判決
(1)本件各処分は、本件手数料に係る収益が原告に帰属することを前提に、訴外乙らが本件手数料を横領したことを理由にしているものであるから、本件手数料に係る収益が原告に帰属したといえない場合には、訴外乙らによる横領はその前提を欠くこととなり、原告の訴外乙らに対する損害賠償請求権も発生しなくなる結果、原告には本件手数料相当額の益金等が生じないこととなる。
そして、収益の帰属について、法人税法11条が、法律上収益が帰属する者が単なる名義人であって、それ以外の者が実質的に収益を享受する場合に、その者を収益の帰属主体とする旨を定め、消費税法13条も同様の規定を設けている趣旨(実質所得者課税の原則)に鑑みれば、本件手数料に係る収益が原告に帰属するか否かの判断に当たっては、本件手数料を受領した訴外乙らの法律上の地位、権限について検討するとともに、訴外乙らを単なる名義人として実質的には原告が本件手数料を受領していると見ることができるか否かを検討することが相当である。
(2)本件手数料は、訴外丁が、訴外乙らの指示に従って商品原価にリベート額を上乗せした額で本件食材を納入し、納入後に訴外会社が受領した代金からリベート相当額を訴外乙らに支払う形で交付されていた。
(3)原告においては、本件食材の仕入れに関して入札制度を採用し、総務部仕入課仕入係が発注業務を担当しているため、調理場から直接納入業者に発注をすることは禁止されており、調理部調理課に所属する訴外乙らに仕入業者の選定権限や仕入金額の決定権限は付与されていなかった。なお、本件食材の仕入れに係る入札制度は、訴外会社以外の業者が入札しなくなったため、事実上行われなくなった。
(4)原告においては、就業規則上、「会社の許可なく、職務上の地位を利用して、外部の者から金品等のもてなしを不当に受けた時」は解雇する旨の規定があるほか、訴外乙らを含む従業員にもリベートの受領が禁止されている旨が周知されていた。
(5)訴外乙らは、訴外丁からリベートを受領するに際し、塩竈市やF町等、の建物からは離れた所在地にある飲食店の、あまり人目につかないような場所で授受を行っていた。
(6)訴外乙らは、受領した本件手数料を部下との食事会やコンペ等に費消していたほか、原告の指示なく、自らの判断でBにおける備品等の購入に充てていた。
(7)原告は、Bの建物新築後の平成8年ころから本件各事業年度までに、売上げ減少が続く一方、金融機関に対する借入金返済の増加等もあって、経営成績が悪化し、損失を累積させて、資金繰りも困難な状況となったことから、金融機関との取引関係維持のために、役員報酬等のカットを含む大幅な経費削減を行いつつ、減価償却費の計上を一部にとどめるなどして対応してきた。
(8)本件手数料は、原告における本件食材の仕入れに関して授受されていたものであるところ、原告における本件食材の仕入れに関しては入札制度が設けられていることや、仕入課仕入係に発注権限が存在しており、調理課に所属する訴外乙らには本件食材の発注権限がないことからすれば、訴外乙らが、本件食材の仕入れに関する決定権限を原告から与えられていたとは認められない。これらの事実に加え、原告においては、就業規則上もリベートの受領が禁止されており、訴外乙らを含む従業員にその旨周知されていたこと、訴外乙らは、訴外丁からリベートを受領する際、塩竈市やF町等、Bの建物からは離れた所在地にある飲食店の、あまり人目につかないような場所で授受を行っていたことなどを併せ考えると、訴外乙らが、本件食材の仕入れに関して授受されていた本件手数料について、原告から法的な受領権限を与えられていたと認めることはできない。
(9)そうすると、訴外乙らは、個人としての法的地位に基づき訴外丁から本件手数料を自ら受け取ったものと認められるところ、自己の判断により、受領した本件手数料を費消していたというのであるから、訴外乙らが単なる名義人として本件手数料を受領していたとは認め難い。
(9)したがって、本件手数料に係る収益は原告に帰属するものとは認められない。
ポイント
従業員の行為が問題となるケースでは、「隠ぺい・仮装」の前に、「実質所得者課税」について検討し、その後に「隠ぺい・仮装」があったかどうか、が検討される、という二段階構造になることになります。
納税者の従業員による着服、リベート事案においては、収益が納税者に帰属するのか、あるいは、従業員個人に帰属するのか、について、以下の点を検討すべきだと考えられます。
①当該収入は、個人としての法的地位に基づき得たものであるか、あるいは納税者の従業員としての法的地位に基づき得たものであるか
②納税者の従業員として金員の受領権限があったか
③納税者は、従業員のリベート受領を禁止していたか
④従業員は、仕入業者の選定や仕入金額の決定に権限を有していたか
⑤受領した金員が従業員によって私的に消費されていたか
⑥納税者がリベートの受領について知らなかったか、または、知り得なかったか
⑦着服と対象となった行為は、納税者の業務に関する取引であったか
国税不服審判所平成30年4月24日裁決、TAINSF0-2-828
事案
・請求人は土木建築請負業等を営む会社で、当時営業部長等の地位にあった元従業員が下請業者からリベートを受領していた
・課税庁は、請求人に帰属し、また当該金員を収益に計上しなかったことは、事実の隠ぺいに該当するとして、各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分を行った
(論点)
①従業員の得ていたリベートの収益は、会社に帰属するのか、従業員に帰属するのか(実質所得者課税)
②収益を会社に帰属するとして、会社の仮装又は隠ぺいがあったか
判決
(収益の帰属)
・本件元部長は、請求人の営業部長又は総括部長という、代表取締役に次ぐ地位にあった
・外注先及び発注金額を実質的に決定し、本件施工会議を取り仕切るなど、請求人の重要な業務に関する実質的な権限を有していた
・外注先が請求人から当該工事を受注したことに対する謝礼として、また、今後も工事を受注できることを期待して、上記の地位及び権限を有する本件元部長に対して支払われた
→請求人会社に帰属する
(重加算税)
・本件元部長が預金口座を利用するなどして受領し、請求人の収益に計上しなかった行為は、隠ぺい仮装行為に当たることが明らかである。
・本件元部長は、請求人の営業部長又は総括部長という代表取締役に次ぐ地位にあり、外注先及び発注金額を実質的に決定し、本件施工会議を取り仕切るなど、請求人の重要な業務に関する実質的な権限を有していた。
(代表者が知らない点)
・代表者が本件各金員を元部長が受領していたことを知らなかったとしても、外注先からの金員の受領は想定し得ないことではなく、本件元部長が本件各金員を受領した事実を把握することが特に困難であったとは認められないから、請求人において本件元部長の行為を是正することは可能。
・代表者は、従業員らによる外注先からの金品の受領について調査し、対策を講じるなどをせず、その結果として、本件元部長が5年間という長期間にわたり本件各外注先から本件各金員を受領し続けていたものというべきである。
→本件元部長の行為を請求人の行為と同視できる。
ポイント
納税者が隠蔽又は仮装を知らない場合に関しては、最高裁平成18年4月20日判決(判例時報1939号12頁、TAINS Z256-10374 )があります。
(1)納税者が税理士に納税申告の手続を委任した場合
(2)納税者において当該税理士が隠ぺい仮装行為を行うこと若しくは行ったことを認識し、又は容易に認識することができたこと(認識可能性)
(3)法定申告期限までにその是正や過少申告防止の措置を講ずることができたこと(回避可能性)
(4)納税者が防止せず隠ぺい仮装行為が行われた
→納税者の行為と同視できる
そして、「課税処分に当たっての留意点」(平成25年4月 大阪国税局 法人課税課、TAINS H250400課税処分留意点、179頁)には、以下の記述があります。
「代表権を有する者が行った不正行為は会社の行為となるが、その他の会社関係者が行った不正行為の結果、過少申告が生じた場合であっても、その不正行為を会社の行為と同視して重加算税を賦課できる場合がある。従業員であっても、会社の主要な業務を任され、長期にわたる不正や多額な不正など会社が通常の注意をすれば容易に発見できる不正行為を管理監督しなかったために、これを見過ごし、結果としてこれを起因とする過少申告が生じた場合には、会社の行為と同視することができる」
「不正行為者がどの範囲まで業務を任され、当該業務がどのようにチェックされていたか等について、特に次の①から③までについて関係者に対する『質問応答記録書』を作成するなどして証拠化しておく必要がある。
①重要な事務を担当していたこと
②当該従業員に業務を任せきりにしていたこと
③法人が何らかの管理・監督をしないまま放置していたこと」
したがって、以下のような反論を検討することになります。
①法人が隠蔽又は仮装行為を知ることが容易ではないこと(巧妙な隠蔽等)
②当該従業員が重要な事務を担当していないこと
③当該従業員に業務を任せきりにしていないこと(二重チェック、報連相)
④法人が何らかの管理・監督体制を整えていたこと(社内規則、上司によるチェック体制、監査等)