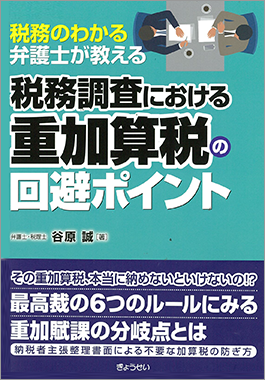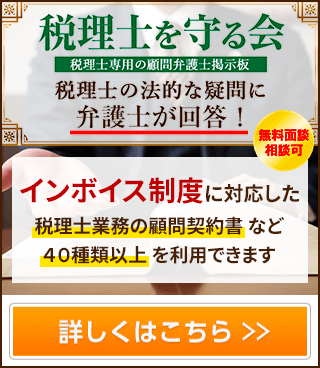今回は、親の事業(歯科医院)に子(歯科医師)が参加した場合、収入は、親に帰属するか、それぞれに帰属するか、という論点です。
東京高裁平成3年6月6日判決(TAINS Z183-6725)です。
(事案)
原告は歯科医師であり、歯科医院を営んでいる。
原告の子であるAは、歯科医師試験に合格後、当該歯科医院にて診療に従事していた。昭和57年3月に、A名義の個人事業の開業届出書を税務署に提出した。
原告は、昭和57年および58年分の所得税について、歯科医院の総収入および総費用をAと折半して申告した。
税務調査があり、Aは独立の事業者ではなく、原告の専従者であり、医院からの事業収入は全て原告に帰属する、として更正処分及び過少申告加算税決定処分をした。
原告は、税務訴訟(処分取消訴訟)を提起した。
(判決)
【所得の帰属の判断】
親子が相互に協力して一個の事業を営んでいる場合における所得の帰属者が誰であるかは、その収入が何人の勤労によるものであるかではなく、何人の収入に帰したかで判断されるべき問題であつて、ある事業による収入は、その経営主体であるものに帰したものと解すべきであり(最高裁昭和37.3.16第2小法廷判決、裁判集民事59号393頁参照)
従来父親が単独で経営していた事業に新たにその子が加わつた場合においては、特段の事情のない限り、父親が経営主体で子は単なる従業員としてその支配のもとに入つたものと解するのが相当である。
【考慮要素】
原告夫婦とA夫婦及びその子は、同一建物の1階と2階に住み分けており、独立の出入り口はないなどから、Aは全く別個の世帯とは認められない。
Aが開業にあたり必要とした医療器具、医院改装の費用は原告の負担であり、売買契約等の契約者も原告であり、借入にあたり、原告所有土地建物に担保設定医院の経理上Aと原告の収支が区分されていない
同医院の収入が昭和56年から飛躍的に増大していることが認められるとはいえ、本件で問題になつている昭和56年から同58年にかけての医院の実態は、Aの医師としての経験が新しく、かつ短かいことから言つても、原告の長年の医師としての経験に対する信用力のもとで経営されていたとみるのが相当であり、したがつて、医院の経営に支配的影響力を有しているのは原告であると認定するのが相当である。
原告とAの診療方法及び患者が別であり、いずれの診療による収入か区別することも可能であるとしても、原告が医院の経営主体である以上、その経営による本件収入は、原告に帰するものというべきである。
==================
以上です。
子が歯科医師という資格を有し、治療を担当していたとしても、父親が全体の経営主体であり、収入金額すべてが父親の収入になる、という結論です。
親の事業に子が参加した場合には
(原則)
従来父親が単独で経営していた事業に新たにその子が加わつた場合においては、特段の事情のない限り、父親が経営主体で子は単なる従業員としてその支配のもとに入つたものと解する
その上で、例外として、「特段の事情」を検討する、という順番になります。
国税不服審判所に対する審査請求・税務訴訟は、ご相談ください。