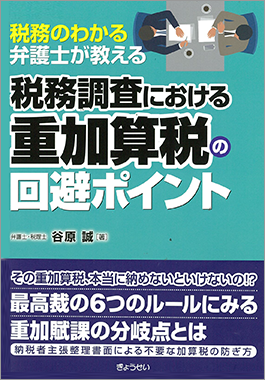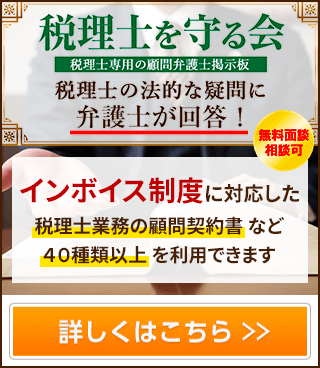税理士がミスをして損害賠償請求を受けた事例について解説します。
税理士の注意義務については、様々な類型があるが、ここでは、助言義務違反を問われた損害賠償請求事例について解説します。
目次
- 1 税理士の助言義務とは
- 2 税理士損害賠償請求事例
- 2.1 消費税の課税形態の助言義務で税理士損害賠償事例(税理士勝訴)
- 2.2 重加算税の説明義務違反で税理士損害賠償請求事例(税理士一部敗訴)
- 2.3 顧問会社役員への助言義務違反で税理士損害賠償事例(税理士敗訴)
- 2.4 顧問先の役員への助言義務違反で税賠(税理士勝訴)
- 2.5 物納の説明助言義務違反で税理士損害賠償請求事例(税理士敗訴)
- 2.6 資本金の助言義務違反と税理士損害賠償請求事例(税理士敗訴)
- 2.7 納税猶予の助言義務違反で税理士損害賠償請求事例(税理士勝訴)
- 2.8 延納の助言義務違反による税理士損害賠償事例(税理士勝訴)
- 2.9 住宅ローンの特別控除の助言義務で税理士損害賠償(税理士敗訴)
- 2.10 売買契約に対する助言義務で税理士損害賠償事例(税理士勝訴)
税理士の助言義務とは
税理士は、善管注意義務に基づき、依頼者に対して関連税法及び実務に関して、有益な情報および不利益な情報を提供し、依頼者が適切に判断できるように説明及び助言をしなければならない。これを税理士の説明助言義務といいます。
この説明助言義務については、税理士が
①説明助言義務を負うか、
②説明助言義務を負うとして、説明助言したかどうか、
で争われることになります。
過去の裁判例では、②に関し、税理士が「説明助言した」と主張するものも多いですが、裁判実務においては、税理士の側で「説明助言した」と証明できない場合には、説明助言の事実が否定される傾向にあります。
したがって、税理士が無用の損害賠償請求を防止するためには、説明助言したことを証拠化して残しておくことが重要です。
税理士が損害賠償請求を受けた時の対応も確認しておきましょう。
参考記事:税理士がミスをして損害賠償請求を受けた時の対応を弁護士解説
税理士損害賠償請求事例
消費税の課税形態の助言義務で税理士損害賠償事例(税理士勝訴)
東京地裁平成26年3月26日判決(TAINS Z999-0156、税理士勝訴)です。
(事例)
ホテル事業を行う会社X社並びにそのグループ会社ら36社が、税理士及び会計法人に対し、グループ会社における消費税の課税形態の選択に関して、適切な課税形態を判断し、助言すべき義務を怠ったことにより、不適切な課税形態が選択されて、消費税の還付を受けられず、不要な納税をしたことによる損害を被ったと主張して、損害賠償請求をしたものです。
(裁判所の判断)
●消費税の課税形態に関する判断は、当該事業者の翌期・翌々期の売上げ及び仕入れという事業の見通しに従って行われるべきものであって、いったん課税事業者ないし簡易事業者の選択をすると2年間はそれをやめることができないのであるから、その判断は当該事業者に委ねられているところであり、税務申告等に関与する税理士ないし税理士法人が決定し得るところではないというべきである。
●したがって、税務申告等に関与する税理士ないし税理士法人については、依頼者である事業者から個別の相談又は問い合わせがない限り、その事業者について、事業の見通しを積極的に調査し、又は予見した上で、当該事業者の消費税の課税形態の選択について助言又は指導を行うべき義務は原則としてないものというべきである。
但し、法人税・消費税の申告業務等を受任している税理士法人としては、依頼者から消費税の課税形態に関する個別の相談若しくは問い合わせがある場合又は個別の相談若しくは問い合わせがなくとも依頼者から適切な情報提供がされるなどして、税務に関する行為によって課税上重大な利害得失があり得ることを具体的に認識し、若しくは容易に認識し得るような事情がある場合には、依頼者に対し、当該行為の助言、指導等をするべき付随的な義務が生じる場合もあり得るというべきである。
(ポイント)
本件判決は、税理士及び会計法人の契約の「業務範囲」が問題となった事例ですが、業務範囲に「節税コンサルティング」「経営コンサルティング」などと記載してあったら、助言義務が認められた可能性があります。
税理士が業務を行う場合には、必ず契約書を締結し、かつ、業務範囲を明確に定めることが肝要です。
重加算税の説明義務違反で税理士損害賠償請求事例(税理士一部敗訴)
>
所得税確定申告において、税理士が説明助言義務違反を理由に損害賠償請求された事例である前橋地裁平成14年12月6日判決(TAINS Z999-0062、税理士一部敗訴)です。
(事例)
●税理士の担当職員は、依頼者らに対し、現金出納帳、預金通帳、請求書、領収書などの原始記録を提示するよう求めたが、依頼者らは、これを拒んだ。
●依頼者らは、税理士に対し、依頼者らが作成した平成5年度の申告書の控え、生命保険料や損害保険料の控除証明書のみを提示して、同6年度についても同5年度と同様に申告するよう要請した。
●担当職員は、他の方法も提案したが、依頼者らはこれも拒んだ。
●そこで、担当職員は、それ以上原始資料の提示を求めることなどを断念して、依頼者らの指示通り申告した。
●後日、国税庁が強制調査し、重加算税その他追加納税が発生した。
●そこで、依頼者らは、税理士から重加算税等の説明を受けていなかったとして、説明助言違反を理由と損害賠償を請求した。
(裁判所の判断)
●依頼者の指示どおりの申告をした場合に、依頼者らが将来脱税を指摘されて重加算税や延滞税などを課せられる危険があることを何ら説明しないまま、依頼者の指示どおりに所得税等確定申告手続を行ったことは、税務に関する専門家である税理士としての立場から、依頼者に対し不適正の理由を説明し、法令に適合した申告となるよう適切な助言や指導をするとともに、重加算税などの賦課決定を招く危険性があることを十分に理解させ、依頼者が法令の不知などによって損害を被ることのないように配慮する義務に違反しており、税理士の債務不履行になる。
●依頼者らの責任は重く、過失相殺として9割を減ずる。
●9割の過失相殺がされましたが、賠償額は、238万1,370円となりました。
(ポイント)
税理士の助言義務には、依頼者に将来不利益が生ずる可能性がある場合に、その不利益内容を説明する義務があるので、注意したいところです。
また、説明したことを証拠として残しておくことも肝要です。
顧問会社役員への助言義務違反で税理士損害賠償事例(税理士敗訴)
顧問会社の役員個人からの税務相談に対して誤った回答をしたことにより税理士損害賠償となった東京地裁平成12年6月30日判決(税理士敗訴)を解説します。
(事例)
●A社と被告税理士は、税務顧問契約を締結しており、原告は、A社の取締役である。
●被告税理士は、A社との税務顧問契約に付随して、原告個人の確定申告業務及び個人の税務相談を行っていた。
●原告は、被告に対し、自己の居住用不動産をA社に売却した場合、3000万円の限度での譲渡所得の特別控除の適用を受けられるか相談した。
●被告からは、適用可能との回答を得たため、原告は建物をA社に売却したが、同族会社への売却のため、特別控除を受けられなかった。
●原告が税理士に対し、損害賠償請求をした事例。
(裁判所の判断)
●顧問契約が存在しないならば、原告から相談を受けた際に、原告個人の相談は受けられない旨相談の受理を拒否すれば足りるのであって、右相談に応じたこと自体本件顧問契約の存在を裏づける事情である。
●無償でも顧問契約は成立する。
●原告と被告との間には、顧問契約が成立している。
●助言を誤った被告には損害賠償義務がある。
(ポイント)
顧問契約をしている会社の役員から個人的な税務相談をされることも多いと思います。
その場合、助言を間違えると、本件のように、委任契約が成立しているとされ、損害賠償責任が発生する可能性があります。
顧問先の役員への助言義務違反で税賠(税理士勝訴)
委任契約成立の有無が争われた事例です。
東京地裁平成27年5月19日判決(判例秘書登載)です。
(事案)
●税理士は、A社、B社と顧問契約を締結していた。
●原告Xは、両社の代表取締役であり、Xの妻である原告X2は、両社の取締役である。
●X及びX2は、共有の居住用不動産を売却し、譲渡損失が生じたが、損益通算ができないものであった。
●原告らが被告税理士Yに対し、相談したところ、Yは、居住用不動産買換特例の適用を受けることで損益通算ができる可能性があると回答した。
●Xらは、Yの助言に基づき、A社から借り入れることとし、その後B社からの借入に変更したが、それぞれYに対し、特例の適用ができるかどうか、確認した。
●Xらが不動産を購入し、買換特例の適用を受けることを前提とした確定申告書を作成し、税理士Yに確認を求めたが、Yからは、特段の問題意識は伝えられなかった。
●後日税務調査があり、特定の適用が否認され、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。
●なお、Xらは、税理士Yに対し、過去に不動産や株式について、何度か税務相談をしたことがあった。
(争点)
(1)原告らと被告との間の税務顧問契約の有無
(2)原告らと被告との間の委任契約の有無及びその内容
(3)不動産の売却に関する損益通算に関して、原告らに対して、被告が誤った説明をしたか。
(裁判所の判断)
(1)原告らと被告との間の税務顧問契約の有無
過去に被告が無償で原告らの税務相談に応じたことがあるものの、その回数が多いわけではなく、かつ、その多くは被告と税務顧問契約がある会社との関係がある事柄の税務相談であること、原告らは、本件における不動産の売却を踏まえた原告らの確定申告についても、被告に委任することなく行っていることからすると、直ちに、原告らと被告との間で包括的な税務顧問契約が成立していたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(2)原告らと被告との間の委任契約の有無及びその内容
相談料の有無・金額の確認等をした形跡はないこと、経理担当者から損益通算の適用の有無を正確に判断するための売買契約書、過去の確定申告書等の資料を送付されていないこと、原告らからは、税理士事務所職員に対し、損益通算をした場合の試算がされたものが送付された過ぎないことからすると、職員において損益通算の可否についての確定的な回答が得られるものではないことは明らかであり、業務としての税務相談の回答を求めたものと認めることができない。
3)不動産の売却に関する損益通算に関して、原告らに対して、被告が誤った説明をしたか。
不動産の損益通算に関して、原告らと被告との間には何らの契約関係も認めることができないのであるから、被告に契約上の義務違反を認めることができない。また、税理士事務所職員は、確定的な回答をしているわけでもなく、A社の経理担当者も確定的な回答を求めたと認めることはできないのであるから、その回答の適否如何を問わず、税理士事務所職員に過失は認められないのであって、被告に債務不履行も不法行為も認めることはできない。
===================
以上です。
本件では、顧問先会社の代表者との顧問契約や税務相談の委任契約を否定しました。
しかし、役員との無償の顧問契約を認定した裁判例もあります(東京地裁平成12年6月30日判決、TAINS Z999-0066)。
したがって、あくまで事例判断であり、かつ、本件事実関係と同様の事案においても、顧問契約や委任契約が否定されるとは限らないことをご注意ください。
なお、委任契約は、無償でも成立します。
したがって、やはり、税賠対策は、必須です。
物納の説明助言義務違反で税理士損害賠償請求事例(税理士敗訴)
相続税申告業務における物納の助言指導義務違反の税理士損害賠償の事例である名古屋地裁平成28年2月26日判決(TAINS Z999-0170、税理士敗訴)です。
(事例)
●納税者が株式その他の財産を相続したが、納税者は、相続税を現金納付できなかった。
●納税者は、株式を3回に分けて売却し、相続税を納税したが、売却した株価は、リーマンショックにより、相続開始時よりも下落していた。
●そこで納税者は、株式を物納していれば避けられたにもかかわらず税理士が物納について説明しなかったために納税額の損害を被ったとして、税理士法人に対して損害賠償請求をした。
(判決)
●財産目録の調製が完了して、遺言執行者において遺言の執行段階に入っており、相続税の概算が算出された段階では、税理士には、納税の方法について委任者に確認し、必要な助言指導を行う義務が発生しているというべきである。
●原告が物納についてある程度の知識を有していたこと、原告が投資により、より有利な資産を得る目的で資産運用を行っていた事実に照らせば、原告が積極的な投資意欲を有していたものと認められ、第3回売却についても、投資目的での売却という要素が否定できないことに照らせば、原告の過失割合は3割と認定するのが相当である。
(ポイント)
過去の裁判例では、相続税額がある程度の金額の時は、納税者の納付の可否について確認し、現金納付が無理そうであれば、延納・物納制度について説明する義務がある、とされる傾向がありますので、注意が必要です。
資本金の助言義務違反と税理士損害賠償請求事例(税理士敗訴)
消費税の助言義務違反で税理士損害賠償請求をされた東京地裁平成27年5月28日判決(税理士敗訴)です。
(事例)
●原告は、個人で医院を開業していた医師が、設立した資産の総額1億74万9000円の医療法人である。
●医師が被告税理士に対し、医院を法人にする旨を相談し、税理士が医療法人の設立手続の一部についての事務を委任する契約を締結した。
●医師は、医療法人の資産総額を1億74万9000円としたが、被告税理士が原告設立時に原告の資本金を設立後2期分の消費税の免除を受けられるなど税務上有利とするために、1000万円未満とするよう助言していれば、消費税の免除を受けられたとして、損害賠償請求をした。
(裁判所の判断)
●原告の設立の主な目的は節税であったことが認められ、そうであるとすれば、医師から相談を受け、設立手続の一部に協力する旨の本件契約を締結した被告としては、その目的に沿うよう、甲野に対し、資産総額についても正しく説明・指導する義務があったと認められる。
●税理士は、医師に対し、消費税については、原告は個人経営から法人成りした経緯から、2期分の免除の適用はない旨、誤った認識に基づく回答をし、設立の際に正しい説明をしたことや、甲野の強い希望で資本金額を1億円以上としたことについては全く触れなかったことが認められる。
(ポイント)
本件では、税理士は、原告代表者が「資産総額だけでも他のクリニックに勝ってブランド化したい。」「設立から2期分の消費税の免税が受けられなくとも、課税される消費税が経費となるならそれでかまわない。」「運転資金が潤沢にあった方が運営しやすい。」などと述べて、資産総額を1億円超とした、と主張しました。
しかし、裁判所は、それを認めませんでした。
依頼者が課税上不利な選択をすることがありますが、その事実を税理士が立証しなければ税理士が説明したことは認められにくいです。
なぜなら、自ら不合理な選択をするとは考えにくいためです。
したがって、依頼者が課税上不利な選択をする場合には、特に説明助言の証拠を残しておくことが肝要です。
納税猶予の助言義務違反で税理士損害賠償請求事例(税理士勝訴)
相続税申告において、納税猶予の説明義務に違反したとして損害賠償請求された横浜地裁平成元年8月7日判決(税理士勝訴)です。
(事例)
●原告他9名は、被告税理士に相続税申告手続を委任したが、その際、農地の納税猶予の適用を依頼した。
●相続税申告期限の日に税理士は遺産未分割で申告手続をしたが、その際、農地の納税猶予の適用申請をしなかった。
●原告らは、本件納税猶予は農地についてのみ一部分割をしていれば適用を受けられたにもかかわらず被告税理士が説明を怠ったことにより適用不可となったとして、損害賠償請求をした。
(判決)
●税理士は、納税猶予の説明助言をすべき義務があるのに、これを起こった。
●遺産分割の協議は、難行していた。
●不動産を本家側、分家側でどのように分配するかで難航しており、相続税の軽減の問題は二次的な問題であった。
●申告期限内に右一部分割協議が成立し得たものと推認することは困難であった。
●税理士が説明したとしても、損害は回避できなかった。
(ポイント)
本件では、税理士に納税猶予の説明義務違反があったと認めたものの、説明したとしても、損害を回避できなかった、として税理士勝訴となりました。
しかし、このような場合でも、一応説明しておくことは必要と考えます。
延納の助言義務違反による税理士損害賠償事例(税理士勝訴)
神戸地裁平成10年12月9日判決です。
(事案)
相続人6人に相続税申告手続を依頼された。
申告期限において未分割だったため、法定相続分で当初申告をした。
税理士が延納手続を取らなかったため、納税のために借入をせざるを得なくなり、借入金利息等の損害を被ったとして損害賠償請求をした。
(判決)
税理士が原告一郎に送ったFAXには、次の記載があった。
「延納申請をすることは出来る。」「申請のためにいろいろと書類をととのえる必要があるが、依頼があれば用意するので早急に連絡を願う。」
被告は、原告一郎に対し、延納手続について一応の説明はしている。しかるに、それに対し、原告らが被告に対し、延納手続を取るよう求めたことを認めるべき証拠はない。
延納が許可されるためには、納期限までに金銭で納付することが困難であることが必要とされるところ、原告花子は2億円も借り受けることができたことなどからすれば、そもそも原告らに、納期限までに金銭で納付することが困難な事由があったのかは疑わしい。
→税理士勝訴
(ポイント)
今回は、税理士が延納許可申請の説明をしたことの立証が成功し、税理士が勝訴しました。
決め手はFAXでした。
しかし、FAXがなく、口頭で説明していたら、どうでしょうか。
説明したかどうかが不明となります。
そして、延納許可申請の手続きは執られていません。
ということは、延納許可申請の説明を受けていたら、手続きを依頼していた、というような事情を立証されてしまうと、税理士が説明したことを立証するのは難しくなる、ということです。
このことからも、説明義務の場面では、証拠がとても重要ということになります。
住宅ローンの特別控除の助言義務で税理士損害賠償(税理士敗訴)
東京地裁令和4年05月16日判決で、税理士敗訴です。
(事案の概要)
(1)原告は、弁護士である。原告が勤務する法律事務所は、東京及び大阪に事務所を有している。
A税理士は、令和2年1月23日に死亡した。被告Y1はA税理士の夫であり、被告Y2はA税理士の子である。
原告弁護士は、平成29年12月頃、A税理士との間で、平成29年分以降の所得税等に係る確定申告業務を年間10万円の費用で継続的に委任する旨の委任契約を締結した。
原告弁護士は、仕事の拠点が大阪から東京に移ることから、平成29年9月20日、当時大阪に自宅として所有していたマンションの一室(以下、単に「自宅」という。)を、購入価額を上回る金額で第三者に売却し、平成30年1月30日に買主への引渡しを行ったところ、同売却に係る譲渡所得について、売買契約の効力発生の日の属する平成29年分の所得としてではなく、物件を引き渡した日の属する平成30年分の所得として確定申告をし、上記譲渡所得全額の1366万3371円について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例(租税特別措置法35条等。以下「売却時控除」という。)の適用を受けた。
(2) 原告弁護士が、令和元年10月29日、A税理士に対し、新居の購入を検討するに当たり、住宅ローン控除の適用を受けることが可能か(前記の売却時控除との併用の可否)といった税務上の疑問点についてメールで問合せをしたところ、A税理士は、翌30日、原告弁護士に対し、要旨、〈1〉売却時控除の適用を受けた年から2年以内に新居の引渡しを受ける場合には住宅ローン控除の適用は受けられない、〈2〉原告弁護士は自宅の売却に係る譲渡所得について平成30年分の所得として売却時控除の適用を受けているものの、同譲渡所得については平成29年分の所得としても申告が可能であったため、平成30年分の所得としてした税務申告を平成29年分の所得として申告し直すこと(以下「本件修正申告」という。)が可能である、〈3〉本件修正申告をすることにより、令和2年に新居の引渡しを受けるのであれば、住宅ローン控除と売却時控除の両方の適用を受けることができると回答した(以下、この回答を「本件助言」という。)。
(3)原告弁護士は、令和元年11月8日、A税理士との間で、本件修正申告に係る申告業務を報酬3万円で委任する旨の委任契約(以下「本件契約」という。)を締結した。
A税理士は、令和元年11月11日、B税務署に対し、原告弁護士の平成29年分の所得及び平成30年分の所得の各確定申告について、自宅の売却に係る譲渡所得の申告及び売却時控除の適用申請を平成30年分の所得としては行わず、平成29年分の所得として確定申告をする旨の申告(本件修正申告)をした。
(4)原告弁護士は、令和元年11月13日、スターツデベロップメント株式会社(以下「スターツ社」という。)に手付金として513万円を支払った上で、同月16日、スターツ社から、肩書地所在の土地付き建物(以下「本件物件」という。)を代金1億0636万円(うち建物価格(税抜き)は3567万円)で購入した。原告弁護士は、本件物件の代金のうち自己資金1006万円を除いた9630万円について住宅ローン(月々の返済額を約26万円とするもの。以下「本件住宅ローン」という。)を利用した。
(5)B税務署は、令和元年11月20日、A税理士に対し、国税通則法19条1項各号所定の修正申告の要件(確定申告書に記載した税額に不足額があること等)を満たしていないため、本件修正申告は認められないとの判断をした旨を伝えた。
A税理士は、令和元年11月22日、原告弁護士に対し、B税務署から本件修正申告は受理できないと告げられた旨をメールで連絡した。
原告弁護士は、本件修正申告が認められなかったため、本件住宅ローンに係る住宅ローン控除の適用を受けることができなかった。
(6)原告弁護士は、A税理士に対し、損害賠償請求をした。
【判決】
(争点〈1〉A税理士の本件契約に係る債務不履行責任の有無)
(1) 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするところ(税理士法1条)、税理士のこのような職責や業務の内容、性質を踏まえると、納税義務者から委任を受けて税務申告をするに当たっては、単に一定の申告業務をするにとどまらず、納税義務の適正な実現に向けて、その申告業務が関係法令等に適合するものであるか否かを十分に確認、調査すべき義務を負っていると解される。
(2)本件契約の目的である本件修正申告は、原告が令和元年に購入して令和2年に入居する新居の購入に際して利用する住宅ローンに係る住宅ローン控除の適用を受けられるようにするためにA税理士から提案されたものであったが、それ自体、国税通則法上の修正申告の要件を欠くものであった。
A税理士は、令和元年に購入して令和2年に入居する新居について住宅ローン控除の適用を受けることができるかとの原告からの問合せに対して本件助言をし、また、原告が、本件助言のとおりの修正申告(本件修正申告)をすることによって住宅ローン控除満額の適用を受けることができるかを改めて確認した際も、A税理士は、本件修正申告をすることにより、売却時控除と住宅ローン控除の両方の適用を受けられる旨回答しているところ、原告は、A税理士のこのような対応を受けて、令和元年に購入して令和2年に入居する新居の購入に際して利用する住宅ローンに係る住宅ローン控除の適用を受けることを企図して、本件契約を締結したことが認められる。
そして、上記の事実経過によれば、A税理士においても、本件契約の締結に当たり、原告が、令和元年に購入して令和2年に入居する新居について、住宅ローン控除満額の適用を受けることを企図しており、そのことが原告において本件契約を締結する主な動機となっていることを認識していたと認められる。
(3)そうすると、A税理士は、原告に対し、税理士として負う本件契約に係る債務(善管注意義務)として、単に本件修正申告に係る申告業務をするという義務にとどまらず、遅くとも本件修正申告をするまでに、原告の企図するところを踏まえつつ適正な申告業務を実現するために、原告が令和元年に購入して令和2年に入居する新居の購入に際して利用する住宅ローンに係る住宅ローン控除の適用を受けられるか否か、すなわち、国税通則法上の要件等に照らし、自ら本件助言で提案した住宅ローン控除を受けるためにする本件修正申告が認められるものか否かについて確認、調査する義務を負っていたというべきである。A税理士の債務は本件修正申告に係る申告業務をすること自体であり、それを超えて本件修正申告が認められるか否かについてまで調査、確認する義務はないとする被告らの主張は、採用することができない。
それにもかかわらず、A税理士は、修正申告に係る要件を規定した基本的な法令等を確認、調査することなく漫然と本件修正申告をし、もって上記義務に違反し、その結果、本件助言により、本件修正申告が認められるものと信じていた原告は、B税務署が本件修正申告を受理しないことを明らかにするよりも前に、本件物件を購入するに至ったものである。
(4) したがって、A税理士について本件契約に係る債務不履行に基づく損害賠償責任が認められる。
(争点〈2〉原告の損害の有無及び額並びに相当因果関係の有無)
(1)原告は、本件物件を購入するに当たり、住宅ローン控除満額の適用を受けられることを重視していたと認められるところ、原告のこのような意向と認定事実を併せて考慮すれば、A税理士の本件契約に係る債務不履行がなければ、原告において、住宅ローン控除満額の適用を受けるため、本件物件の購入を見送った上で、遅くとも令和3年12月末までに入居するとの条件で同等物件を購入したと認めるのが相当である。
また、原告が同等物件を購入後すぐに手放したり、原告の収入が大きく減少したりすることをうかがわせる事情が見当たらない以上、原告において、同等物件を継続保有し、かつ、住宅ローン控除満額の適用を継続して受けられるだけの収入が維持されることが見込まれるものと認めるのが相当である。
したがって、原告には、同等物件を購入する際に利用したはずの住宅ローンに係る住宅ローン控除額相当の損害が生じたものと認められる。
(2)A税理士は、原告とのやり取りを通じて、原告が、本件物件を購入するに当たり、住宅ローン控除満額の適用を受けることを企図しており、住宅ローン控除満額の適用を受けることを主たる動機として本件契約を締結していることを認識していたものであるところ、同事実によれば、A税理士は、原告において、本件修正申告が認められず、令和元年に購入して令和2年に入居する新居の購入に際して利用する住宅ローンに係る住宅ローン控除の適用を受けられなかった場合には、住宅ローン控除満額の適用を受けるため、本件物件の購入を見送った上で、遅くとも令和3年12月末までに入居するとの条件で新居を購入したことを予見することができたと認められる。また、原告が住宅ローンを利用して購入した新居をすぐに手放したり、原告の収入が大きく減少したりすることをうかがわせる事情が見当たらないことについては、説示したとおりである。
そして、税務申告業務に係る税理士に対する信頼や本件修正申告がされるに至った経緯に照らすと、A税理士においては、本件修正申告をした旨を原告に連絡した場合、原告が直ちに本件物件の購入に向けて動く可能性があることも十分予見することができたものと認めるのが相当である。
(3)他方において、原告が、本件契約の締結の前後を通じ、A税理士に対し、具体的にどのような物件をいくらで購入する予定であるとか、また、いくらの自己資金を確保しており、いくら住宅ローンを利用する予定であるといった具体的事情を明らかにしていたことを認めるに足りる証拠はない。
(4)令和元年11月に生じたA税理士の本件契約に係る債務不履行と相当因果関係のある上記住宅ローン控除額相当の損害は、令和3年12月末日以降、10年間にわたって毎年40万円ずつ発生するものに限られることになるところ、中間利息5%を控除すると、以下の計算式により、294万1600円となる。
(計算式)
400、000円×(8.3064〔11年のライプニッツ係数(年金現価)〕-0.9524〔1年のライプニッツ係数(年金現価)〕)=2、941、600円
(争点〈3〉(過失相殺の可否)について)
(1)原告は、本件物件の購入に当たり、住宅ローン控除の適用を重視していたものであるところ、本件物件の金額に照らせば住宅ローン控除の税務上の効果は大きく、また、住宅ローン控除の適用を受けるためにする本件修正申告の内容はいささか技巧的なものといえ、そのような本件修正申告が認められるか否かは住宅ローン控除の適用の可否に直結する重大事であることからすれば、一定の調査能力及び実務経験を有する弁護士である原告には、本件物件の購入に当たり、相応の慎重さが求められたというべきである。それにもかかわらず、原告は、本件修正申告が認められたことを確認することなく、A税理士から本件修正申告をしたとの連絡を受けてからわずか5日後に本件物件を購入するに至っているのであって、このような経過に照らせば、過失相殺による減額は避けられないものというべきである(被告らによる過失相殺の主張が信義則に照らして許されないことを基礎づける事実を認めるに足りる証拠はない。)。
(2)そうすると、上記経過その他本件に現れた一切の事情を総合考慮して、損害の公平な分担の観点から、前記の損害額から2割の過失相殺をするのが相当である。
(ポイント)
(1)本件は、国税通則法第19条1項1号「先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。」の要件を欠くにもかかわらず、修正申告が可能と助言をした点に税理士の注意義務違反があると判断された事案である。
業務の際には、法令の要件を確認すべきである、という単純な事例である。
(2)しかし、知識が間違っていたとしても、原告弁護士の損害の発生を防止することはできた。本件で、原告弁護士が本件物件を購入するのは、住宅ローン控除の適用を受けることが前提であることは被告税理士も認識可能であった。
そのためには、修正申告が受理され、法的効果が実現することが前提であった。そうであれば、税理士としては、修正申告を先行させて、その効果の発生を待ってから本件物件を購入することを助言することもできたはずである。
そうすれば、修正申告が要件を満たしておらず、受理されないことが判明した時点で、令和2年中の本件物件購入を見送ることができたのであり、令和3年に不動産を購入するという選択が可能であったと思われる。
(3)本件で、裁判所も、過失相殺の判断において、「本件修正申告が認められるか否かは住宅ローン控除の適用の可否に直結する重大事であることからすれば、一定の調査能力及び実務経験を有する弁護士である原告には、本件物件の購入に当たり、相応の慎重さが求められたというべきである。」として、2割の過失相殺をしている。
売買契約に対する助言義務で税理士損害賠償事例(税理士勝訴)
東京地裁平成17年4月13日判決、税理士勝訴です。
(事案)
原告は、平成9年10月30日、所有不動産を譲渡する売買契約を締結した。
所有権移転登記は、平成9年11月28日まで。
引き渡しは平成10年1月14日。
原告は、被告税理士に所得税確定申告手続を委任したところ、税理士は、本件譲渡所得について、平成10年分として確定申告をし、それを前提として買換え特例の申請をした。
課税庁は譲渡所得は平成9年中であるとして更正処分をした。
(事情)
本契約書では、次のように定められていた。
原告が担保責任を負うのは中間金の受領日まで。
原告が本件不動産に対する公租公課を負担するのは中間金の受領日まで。
本件不動産の危険負担は、中間金の受領日に原告からB社に移転。
原告が平成9年11月28日までに受領した売買代金は、代金全額の約98.8パーセント相当。
そして、B社は、平成9年12月22日までに本件建物を取り壊し、本件土地に盛土をするなど本件土地の占有を開始していた。
⇒本件土地の引渡日は、平成9年11月28日であると認めるのが相当である。
(原告の主張)
(1)被告税理士は、本件不動産の売却による譲渡所得を平成10年分とするよう助言し、売買契約内容を点検する義務を受任した。
(2)契約上の義務がなくても、税理士は原告の顧問税理士であり、売買契約への関与状況からすると、売買契約を点検する条理上の義務がある。
(判決)
(1)課税庁に対する税理士の嘆願書には、税理士が売買契約書の作成に関与し、助言した旨の記載があるが、譲渡所得の計上時期を仮装隠蔽する意図がなかったことを明らかにする趣旨である可能性もあり、これのみで点検義務の受任を認定できない。
他の証拠によっても点検義務の受任を証明できていない。
⇒点検義務の受任はない。
(2)税理士は、本件売買契約の締結以前、いずれからも本件売買契約書又はその原案を示された事実は窺われない。
税理士は、本件土地の所有権移転登記手続をした点のほか、本件土地に盛土をして造成した点や庚らに転売された点など、本件譲渡所得の発生時期の認定に影響する重要な事情について報告を受けておらず、本件土地の引渡しの確認をした本件確認書の作成にも関わっていない。
⇒条理上の義務はない。
ポイント
ポイントとしては、まず、受任の際は、契約書を締結することです。
(受任の日が明確になり、それ以前のやりとりは、契約外のやりとり、あるいは契約の準備行為となるため)
次に依頼者のための嘆願書等は、後日、税理士損害賠償請求でブーメランのように不利な証拠となる場合があるので、真実のみを記載することにも注意が必要です。
最後に、所得の年度帰属が問題となりそうな時は、たとえば、「ご相談いただく場合には、売買契約書を必ず事前に見せてください」など、①まだ相談を受けていないこと、②売買契約書を確認しない限り助言できないことを前提としていること、など、証拠を残しておくことも検討しましょう。
・弁護士による税理士損害賠償SOS
弁護士法人みらい総合法律事務所では、税理士損害賠償のご相談を受け付けています。