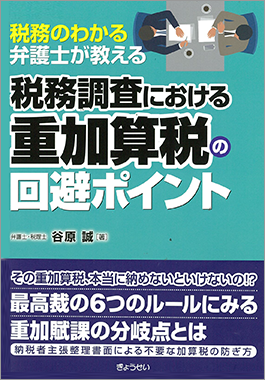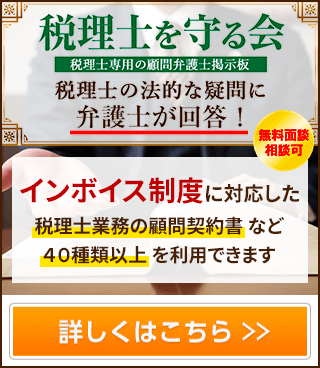分掌変更退職給与を分割支給した場合に、損金に算入できるかどうかが争われた東京地裁平成27年2月26日判決をご紹介します。
(事案)
本件役員は、昭和34年12月、仲間と共に、昭和51年3月、原告を創業し、設立時から平成19年8月31日までの間、原告の代表取締役の地位にあったが、同日付けで原告の代表取締役を辞任して、原告の非常勤取締役となった。
原告は、①本件役員に対する退職慰労金を2億5000万円(本件退職慰労金)とすること、②本件退職慰労金を分割支給することとし、第1回目(本件第一金員)の支払を同月31日とすること、③その余(本件退職慰労金残額)を3年以内(平成22年8月末まで)に支給することを決議した。なお、本件退職慰労金残額の具体的な分割方法までは決められていなかった。
原告は、平成19年8月31日、本件役員に対し、本件退職慰労金の一部として、7500万円(本件第一金員)を支払った。
原告は、本件第一金員が法人税法上の退職給与に当たるとして、本件第一金員を平成19年8月期における損金の額に算入して法人税の確定申告をした。
原告の平成19年8月期の損益計算書には、退職金として7500万円(本件第一金員)のみが計上されており、本件退職慰労金から本件第一金員を差し引いた残額1億7500万円(以下「本件退職慰労金残額」という。)は、平成19年8月期の損金として計上されておらず、上記貸借対照表において未払金等として計上されてもいない。
原告は、平成20年8月29日、本件役員に対し、本件退職慰労金の一部として、本件第二金員(1億2500万円)を支払った。
原告は、本件第二金員が法人税法上の退職給与(同法34条1項)に当たるとして、本件第二金員を平成20年8月期における損金の額に算入して、法人税の確定申告をした。
(争点)
本件第二金員を平成20年8月期の損金の額に算入することができるか否か。
(法人税基本通達)
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。
(判決)
本件通達(9-2-32)ただし書は、役員退職給与を分割支給する場合について直接言及したものではないものの、退職給与を複数年度にわたり分割支給した場合において、その都度、分割支給した金額を損金経理する方法についても、その適用を排除するものではないと解される。
本件通達ただし書は、短期的な資金繰りがつくまでは、役員退職給与の支払をしないということもあり得るという企業の実態を前提として設けられたものであり、企業が資金繰りに支障を来さないように役員退職給与を分割支給すること自体は、企業経営上の判断として、合理的なものであるということができる。
そして、原告は、本件退職慰労金を一括で支払う資金的余裕がなく、経常収支が赤字とならない範囲で支給するという目的から、本件退職慰労金を3年以内に分割支給することとしたのであり、原告の平成19年8月期の損益計算書及びその期末における貸借対照表の記載内容に照らしても、本件退職慰労金を3年以内に分割支給することとしたことが不合理であるということはできない。また、原告が、平成20年8月期以降の事業年度における所得金額を低く抑えるために、本件退職慰労金を分割支給することにしたというような事情をうかがわせる事実ないし証拠もない。
本件第二金員を平成20年8月期の損金に算入するという本件会計処理は、公正処理基準に従ったものということができる。
=====================
以上です。
本判決は、分掌変更退職給与の分割支給を認めています。
しかし、判決の書きぶりからは、無条件に分割支給を認めるものとは解釈できません。
株主総会において役員退職給与の分割支給を決議して、その事業年度に一部を支払い、その後の所得が多かった事業年度に分割支給して所得操作をするようなことは許されないと考えられます。
したがって、分割支給にした理由及び支給時期について、企業経営上の判断として合理性が必要となるものと考えます。